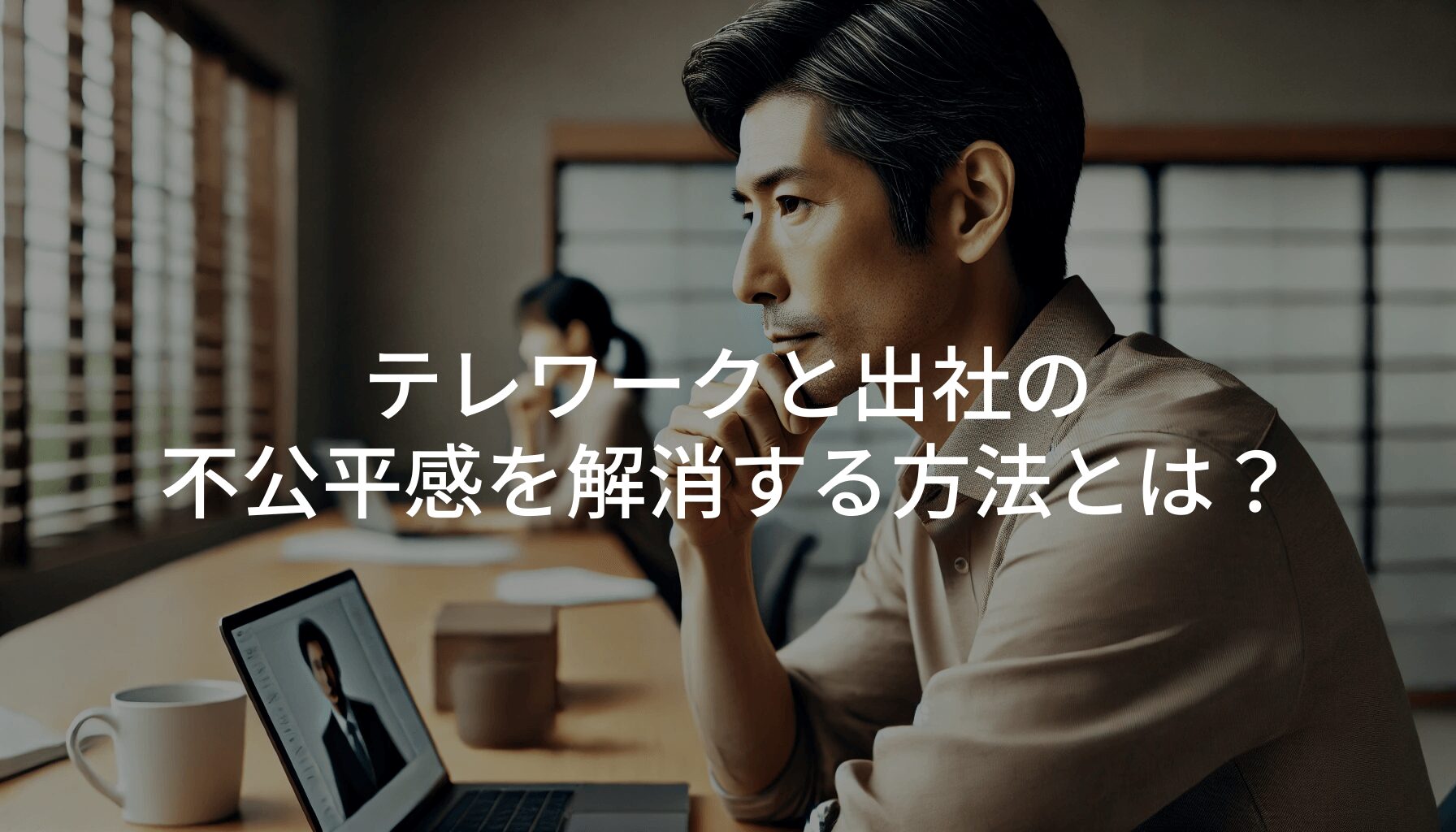業務内容の違いとはいえ、待遇の差がモチベーション低下につながることもありますよね。
このままでは、職場の不満が蓄積し、離職や人材流出につながるかもしれません。
そこで、今回はテレワークと出社の不公平感を解消する方法について紹介します!
この記事で分かること!
- テレワークできる部署・できない部署の違い
- 社員の不満を軽減する対策
- 企業が実践する成功事例
テレワークと出社の不公平感を感じる理由とは?
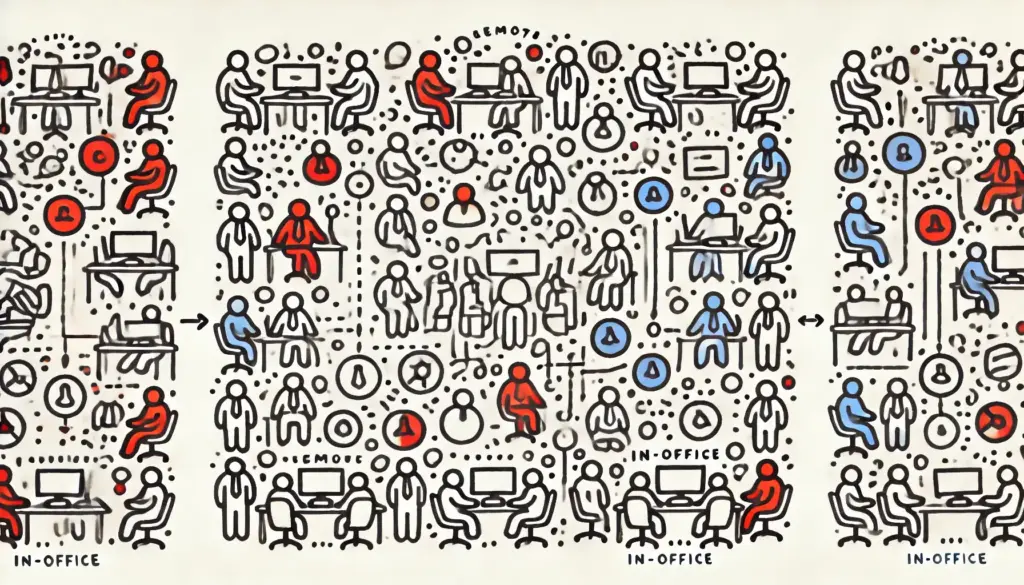
テレワークと出社勤務の間には、さまざまな不公平感が生じることがあります。
その理由を理解することで、適切な解決策を見つける手助けになります。
これらの要因を詳しく見ていくことで、問題の本質が明確になります。
給与や評価制度の違い
テレワークと出社勤務では、給与や評価の仕組みに差が生じることがあります。
特に、勤務態度や成果の可視性に違いが出るため、不公平感が生まれやすいです。
具体的な不公平の要因として、以下の点が挙げられます。
- 出社組の方が「働いている感」が伝わりやすい
- テレワーク組の成果が見えにくく、評価されにくい
- 出社組にだけ手当が支給されるケースがある
- 上司と対面で関わる機会が多い方が評価されやすい
例えば、ある企業では、テレワーク勤務者の評価が「目に見える成果」に偏る傾向がありました。
これにより、出社組は上司の目の前で業務に取り組むことで評価されやすくなり、逆にテレワーク組は成果を数値で示せないと不利になる状況が生まれました。
また、交通費補助や昼食補助などが出社組にのみ適用されるケースもあり、不満につながっています。
この問題を解決するためには、評価制度を透明化し、テレワークでも適切に成果を可視化する仕組みが必要です。
評価の公平性を保つには、「働き方」ではなく「成果」に基づく評価基準を設けることが重要です。
給与や評価制度の違いは、不公平感を生む大きな要因の一つです。
業務負担の偏り
テレワークと出社の環境の違いにより、業務負担が偏るケースがあります。
この偏りが、不公平感の原因になっています。
具体的には、以下のような問題が発生します。
- 出社組が雑務を担当する機会が増える
- テレワーク組が対応できない業務を出社組が負担する
- 急な対応が必要な業務は出社組に集中する
- テレワーク組はオンライン会議の時間が増えて業務時間が圧迫される
例えば、出社勤務の社員が郵便物の管理や来客対応を任されることが増えると、「テレワーク組は楽をしている」と感じることがあります。
一方で、テレワーク勤務の社員は、オンライン会議の頻度が高まり、業務が進めにくいという不満を抱えるケースもあります。
この問題の解決策として、業務の役割を明確にし、公平に分担することが重要です。
「出社している人がやるべき業務」「テレワークの人が対応できる業務」をリスト化し、偏りをなくすことで、不満の解消につながります。
業務負担の偏りは、適切なタスク管理で解決可能です。
コミュニケーション機会の格差
テレワークと出社勤務では、コミュニケーションの頻度や質に差が生じます。
これにより、テレワーク組と出社組の間で情報格差が生まれることがあります。
具体的な問題点として、以下のような点が挙げられます。
- 出社組の方が上司と会話する機会が多く、信頼を得やすい
- テレワーク組が重要な情報をリアルタイムで得られない
- 雑談やランチの場で生まれるアイデアにテレワーク組が参加できない
- テレワーク組が「疎外感」を感じやすい
例えば、出社組はオフィスでのちょっとした雑談から重要な情報を得られることがあります。
しかし、テレワーク組はそれに参加できず、知らないうちに話が進んでいることも珍しくありません。
また、会議がオンライン中心になると、テレワーク組は発言の機会を得にくくなり、存在感が薄れることがあります。
この問題を解決するには、コミュニケーションの機会を意図的に増やすことが大切です。
例えば、以下のような施策が効果的です。
- テレワーク組と出社組の交流を増やす雑談タイムの導入
- 情報共有をチャットツールや社内SNSで徹底する
- 会議ではテレワーク組が発言しやすいルールを設ける
- 対面とオンラインのハイブリッドミーティングを推奨する
コミュニケーション機会の格差をなくすことで、チーム全体の一体感が向上します。
「情報が行き届かない」「評価されにくい」という不満を解消するためにも、積極的な対策が求められます。
テレワークと出社の不公平感を解消するには、給与・評価、業務負担、コミュニケーション機会の差を是正することが重要です。
次の章では、具体的な待遇格差について詳しく見ていきます。
テレワークと出社で生じる3つの待遇格差

テレワークと出社勤務では、待遇に関する格差が生じることがあります。
特に「昇進・キャリア」「福利厚生」「労働時間」の3つの面での不公平感が問題視されています。
これらの待遇格差が社員のモチベーションに与える影響について詳しく見ていきましょう。
昇進・キャリア機会の不平等
テレワークと出社勤務の間では、昇進やキャリア形成の機会に格差が生じることがあります。
特に、テレワーク勤務者は上司との接点が少なく、評価されにくいという課題があります。
具体的な問題点として、以下のようなことが挙げられます。
- 出社組の方が上司と接する機会が多く、昇進しやすい
- テレワーク組の成果が可視化されにくく、評価が低くなりがち
- 管理職に求められるスキルが「対面でのリーダーシップ」に偏る
- テレワーク組は研修や教育の機会が少ない
例えば、ある企業では管理職のほとんどが出社組から選ばれ、テレワーク勤務者はキャリアアップの機会が制限されていました。
これは「上司の目に見える範囲で働いている人」が評価されやすい傾向があるためです。
結果として、テレワーク組のモチベーション低下や、優秀な人材の流出につながる可能性があります。
この問題を解決するには、評価制度を明確にし、成果を公平に評価する仕組みが必要です。
「出社の頻度」ではなく「業務の成果」に基づいた評価を行うことで、公平な昇進の機会を提供できます。
福利厚生や手当の違い
テレワークと出社勤務では、受けられる福利厚生や手当に差が生じることがあります。
特に、通勤手当やオフィス設備の利用に関する不公平感が問題になります。
具体的には、以下のような格差が発生しています。
- 出社組には通勤手当が支給されるが、テレワーク組には何もない
- 社食・カフェテリアなどの福利厚生が出社組だけに適用される
- テレワーク環境を整えるための補助が不十分
- オフィスにいる方が設備(会議室・複合機)を利用しやすい
例えば、通勤手当を受け取れないテレワーク勤務者が「オフィス勤務者だけが優遇されている」と感じるケースがあります。
また、社食を利用できる社員とできない社員の間で、実質的な給与格差が生まれてしまうこともあります。
この問題を解決するには、テレワーク勤務者にも適用できる新たな福利厚生を導入することが有効です。
具体例として、在宅勤務手当の支給や、テレワーク用の設備補助制度の導入が考えられます。
労働時間や残業の扱いの違い
テレワークと出社勤務では、労働時間や残業に関する扱いが異なることが多いです。
これが、不公平感の原因となるケースがあります。
具体的には、以下のような問題が発生しています。
- 出社組は定時後も業務を頼まれやすく、残業が増える
- テレワーク組は「仕事をしているか分からない」と思われ、長時間労働になりがち
- 残業手当の支給条件が出社組とテレワーク組で異なる
- 出社組の方が労働時間を厳密に管理される
例えば、テレワーク勤務者は「勤務時間内にどれだけ働いているか」が分かりにくいため、見えないプレッシャーを感じて長時間労働になりがちです。
また、出社勤務者は「目の前にいるから」と追加の業務を頼まれやすくなり、残業が増える傾向があります。
この問題を解決するには、労働時間の管理を適正化し、全社員が公平に働ける環境を整えることが重要です。
例えば、以下のような対策が考えられます。
- テレワークでも労働時間を可視化できるシステムを導入する
- 出社・テレワークに関わらず残業ルールを統一する
- 業務の切り分けを明確にし、特定の社員に負担が偏らないようにする
労働時間や残業の扱いを統一することで、不公平感を減らし、社員の満足度向上につながります。
テレワークと出社勤務の待遇格差は、昇進・福利厚生・労働時間の3つの要素で特に顕著です。
次の章では、企業が実践できる具体的な不公平感の解消策について紹介します。
企業が実践する!不公平感を解消する施策5選

テレワークと出社勤務の間に生じる不公平感を解消するために、企業が取り組むべき具体的な施策を紹介します。
社員のモチベーションを維持し、公平な職場環境を実現するためのポイントを押さえておきましょう。
これらの施策を導入することで、テレワークと出社勤務の間の格差を是正し、より公平な職場環境を実現できます。
明確な評価基準を設定する
テレワークと出社勤務の間で評価に差が生じないよう、明確な評価基準を設定することが重要です。
「オフィスにいる時間」ではなく「成果」に基づいた評価制度を導入することで、不公平感を減らせます。
具体的な施策として、以下のような方法があります。
- 「勤務態度」ではなく「成果物」を重視した評価基準を設ける
- テレワーク勤務者が適正に評価される仕組みを作る
- 評価項目を可視化し、社員に共有する
- 360度評価を導入し、同僚や部下の意見も反映する
例えば、ある企業では「業務の進捗率」「提出物のクオリティ」「チームへの貢献度」などの項目を数値化し、評価の透明性を高めることで、不満を解消しました。
明確な評価基準を設定することで、テレワークでも公平に評価される仕組みが整います。
コミュニケーションの機会を増やす
テレワーク勤務者と出社勤務者の間で情報格差が生じないよう、コミュニケーションの機会を増やすことが重要です。
特に、雑談や非公式な交流の機会を設けることで、チームの一体感を高められます。
具体的な施策として、以下のような方法が有効です。
- オンラインの雑談タイムを設ける
- バーチャルオフィスツールを活用し、気軽に相談できる環境を作る
- 定期的にハイブリッドミーティングを開催し、全員が発言できる機会を増やす
- 社内SNSを活用し、情報共有を徹底する
例えば、ある企業では「オンライン朝会」を導入し、テレワーク勤務者と出社勤務者が毎朝5分間雑談することで、チームの関係性を深めています。
コミュニケーションの機会を増やすことで、情報格差をなくし、職場の一体感を高められます。
業務量の調整と公平な分配
テレワークと出社勤務の間で業務負担に偏りが生じないよう、タスクの配分を適正化することが重要です。
誰かに負担が集中しないよう、業務の透明性を確保しましょう。
具体的な施策として、以下のような方法があります。
- 業務内容を可視化し、全社員が把握できるようにする
- タスク管理ツールを導入し、業務負担を平等に配分する
- 「出社組がやるべき業務」「テレワーク組が担当する業務」を明確に分ける
- 負担が偏らないよう、定期的に業務調整を行う
例えば、ある企業ではプロジェクトごとに業務量を数値化し、適切に配分することで不公平感を解消しました。
業務負担を適正化することで、社員がストレスなく働ける環境が整います。
ハイブリッドワークの柔軟な導入
完全なテレワークや出社勤務ではなく、ハイブリッドワークを導入することで、両者のバランスを取ることができます。
柔軟な勤務形態を採用することで、社員の満足度向上につながります。
具体的な施策として、以下のような方法が有効です。
- 出社とテレワークの割合を社員が選択できるようにする
- 週に数回の出社日を設け、チームの一体感を維持する
- プロジェクトごとに最適な働き方を決める
- オフィスを「協業の場」として活用し、テレワークと組み合わせる
例えば、ある企業では「週2日出社・週3日テレワーク」の方針を採用し、社員の働きやすさを向上させました。
ハイブリッドワークを柔軟に導入することで、不公平感を軽減できます。
福利厚生を統一する
テレワークと出社勤務の間で生じる福利厚生の違いをなくすことで、不満を減らすことができます。
全社員が公平に恩恵を受けられる制度を整えましょう。
具体的な施策として、以下のような方法があります。
- 通勤手当に代わる「在宅勤務手当」を導入する
- 食事補助を電子クーポン化し、全社員が利用できるようにする
- テレワーク用の備品補助制度を整備する
- オフィスの設備をテレワーク勤務者も利用できる仕組みを作る
例えば、ある企業では「食事補助を電子チケット化」し、出社組・テレワーク組のどちらも平等に利用できるようにしました。
福利厚生を統一することで、社員の不満を解消し、公平な職場環境を実現できます。
次の章では、他社の成功事例を紹介します。
他社事例に学ぶ!公平なハイブリッドワークの実現法
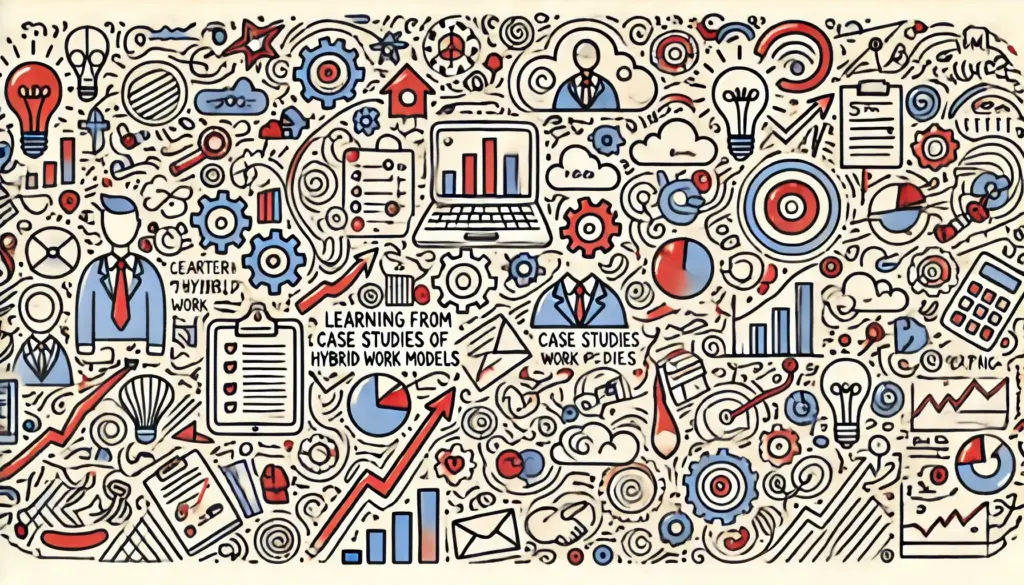
テレワークと出社勤務の不公平感を解消するために、実際に企業がどのような取り組みを行っているのかを見ていきましょう。
成功事例を参考にすることで、自社に適した施策を導入するヒントが得られます。
それでは、各企業の具体的な施策を詳しく見ていきましょう。
A社:評価基準の透明化で不満を解消
A社では、テレワーク勤務者と出社勤務者の間で評価基準に差が生じていました。
特に、出社勤務者の方が上司と接する機会が多いため、評価が有利になりがちでした。
この問題を解決するために、A社は以下の施策を導入しました。
- 「勤務態度」ではなく「成果」に基づく評価制度を導入
- 評価項目を明確にし、全社員に公開
- オンラインでの業務報告を義務化し、テレワーク組の成果も可視化
- 360度評価を取り入れ、同僚や部下の意見も反映
この結果、テレワーク勤務者の評価が適正に行われるようになり、不公平感が解消されました。
また、評価基準が明確になったことで、全社員が納得感を持てる仕組みが構築されました。
B社:テレワークと出社の業務分担を最適化
B社では、出社勤務者に雑務が集中し、テレワーク勤務者が業務負担の少ない状況が発生していました。
このため、出社組から「テレワーク組ばかりが楽をしている」という不満が出ていました。
この問題を解決するために、B社は以下の施策を導入しました。
- 業務をリスト化し、「出社向け業務」「テレワーク向け業務」を明確に区分
- 雑務をアウトソーシングし、出社組の負担を軽減
- タスク管理ツールを導入し、業務の進捗を可視化
- 業務負担が偏らないよう、定期的に調整を実施
この結果、業務の公平な分配が実現し、出社組とテレワーク組の間の対立が解消されました。
また、タスクの可視化により、業務の進捗状況が明確になり、チーム全体の生産性も向上しました。
C社:オンラインと対面のバランスを取る制度を導入
C社では、テレワーク勤務者が情報不足になりやすく、出社勤務者との間にコミュニケーションの格差が生じていました。
その結果、テレワーク勤務者が「会議で発言しにくい」「社内の動きが見えにくい」といった課題を抱えていました。
この問題を解決するために、C社は以下の施策を導入しました。
- 「週1回の全社オンラインミーティング」を導入し、全社員が情報を共有
- 出社勤務者もオンラインツールを活用し、テレワーク組と同じ環境で仕事をする機会を増やす
- オンラインと対面のハイブリッド会議を導入し、全員が公平に発言できる仕組みを整備
- 社内SNSを活用し、情報のやり取りをテキストベースで記録
この結果、テレワーク勤務者と出社勤務者の間の情報格差が解消され、コミュニケーションが円滑になりました。
また、オンライン会議のルールを明確にすることで、テレワーク組が発言しやすい環境が整いました。
まとめ:公平な職場環境を作るために
テレワークと出社勤務の間に生じる不公平感は、給与・評価・業務負担・コミュニケーションの格差が原因となっています。
これらの課題を解決するためには、以下のような施策が効果的です。
- 評価制度を透明化し、テレワーク勤務者の成果も公平に評価する
- 業務負担を適正に分配し、出社組・テレワーク組の負担を均等にする
- コミュニケーションの機会を増やし、情報格差をなくす
- 福利厚生を統一し、全社員が公平に利用できるようにする
- ハイブリッドワークを導入し、柔軟な働き方を可能にする
企業がこれらの施策を実施することで、社員の満足度が向上し、組織全体のパフォーマンスも高まります。
公平な職場環境を実現するために、まずは「どのような不公平感が生じているのか」を見直し、自社に合った改善策を導入していきましょう。
テレワークと出社勤務が共存する時代において、公平な制度設計が企業の成長のカギを握っています。
テレワークと出社の不公平感をなくすには?
今回は、テレワークと出社の不公平感をなくすための対策について紹介しました。
この記事のポイント!
- 給与や評価、業務量の偏りが課題
- コミュニケーション強化が解決のカギ
- 企業の成功事例を活用できる
テレワークと出社の不公平感は、給与や評価、業務量の偏りが原因でした。解決のためには、評価制度の明確化や業務量の調整、コミュニケーション機会の確保が重要です。他社の成功事例を参考にすることで、自社に適した解決策を見つけられます。

まずは評価制度の見直しから始めて、より良い職場環境を作ってみてください。