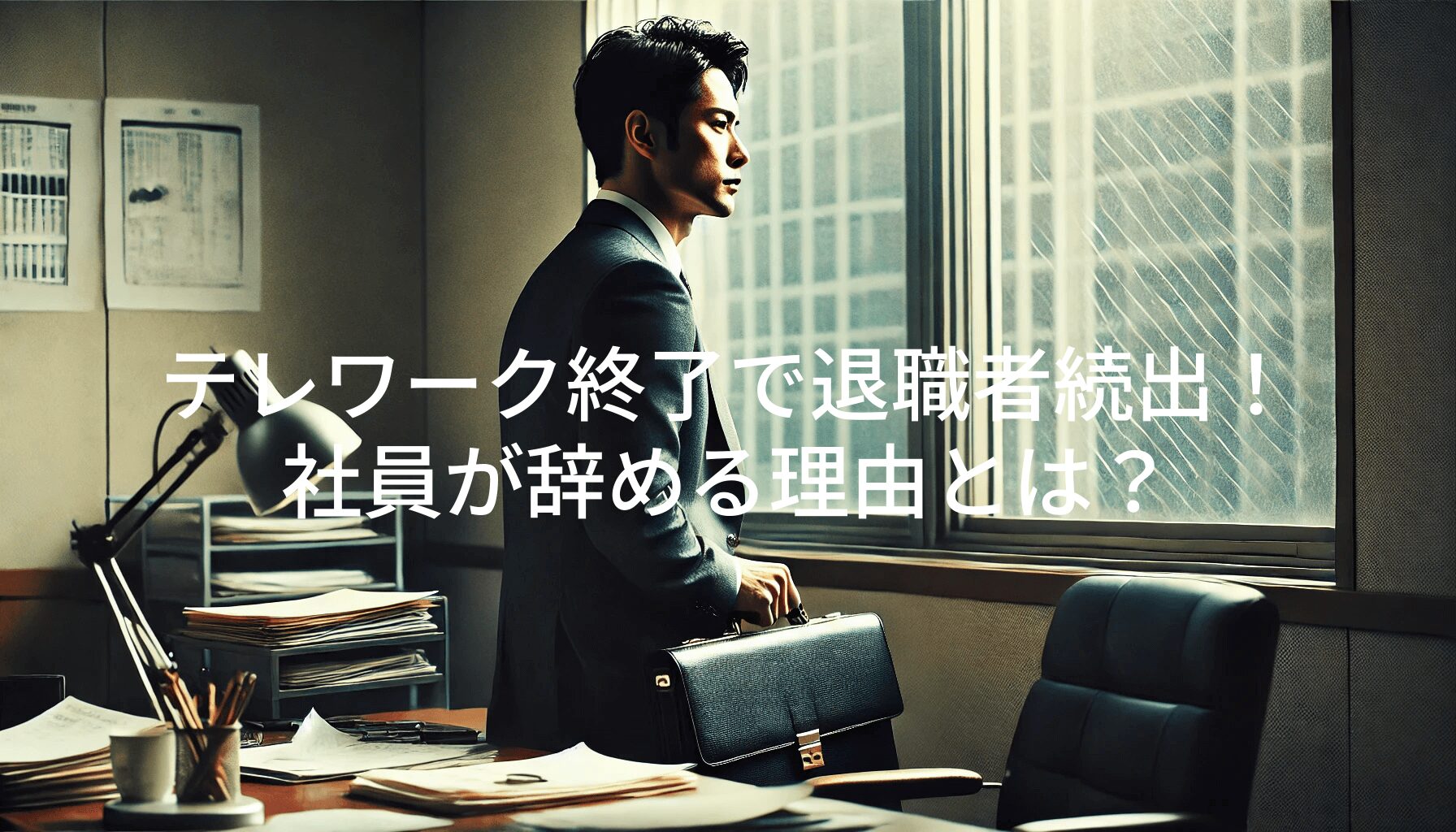テレワーク廃止は、社員のワークライフバランスを大きく崩し、離職率の上昇や採用競争力の低下を招きがちです。本記事では、退職者が増える理由と離職を抑える実務策を、テンプレ(そのままコピペ可)付きで解説します。さらに、在宅と相性の良い職種/スキルや、学び直し→在宅職へ移る最短ルートも整理し、読了後に迷わない導線を用意しました。
【先に結論】「テレワーク できない 辞める」と感じたら、在宅と相性の良い職種×給付金対応スクールを3分で比較
この記事で分かること
- なぜ「テレワーク廃止→退職者増」になるのか(心理/通勤/業務効率/家族都合/評価)
- 辞めない会社に変える対策(制度/オペ/周知を三位一体で運用する15選+社内テンプレ)
- 従業員の現実的な選択肢(配慮申請→配置転換→学び直し→在宅職への移行/退職手順)
テレワーク できない 辞める|増える離職の“構造”を先に理解する

結論から言えば、拙速な完全オフィス回帰は、短期的に統制感を得られても、中長期では人材流出・採用難・生産性低下・ブランド毀損に跳ね返る可能性が高いです。背景には次の構造要因があります。
- 自律性の喪失:リモート期間に育った意思決定の余地が失われ、納得度が低下
- 通勤コストの復活:体力/時間/金銭の“通勤税”が戻り、家庭シフトと衝突
- 紙/押印/口頭依存の逆流:非同期・ドキュメント文化が弱まり、ムダが増殖
- 採用市場での相対劣位:在宅可を標準にする競合へ候補者が流れる
テレワーク廃止がもたらす心理的インパクト
【解説】人は急激なコントロール喪失に敏感です。とくにリモート期間に培われた自己決定性(自律性)が奪われる感覚は離職動機になりやすい。まずは“出社の価値”を言語化して共有し、納得をつくる必要があります。
心理負担の主因(チェック)
- 裁量縮小:業務の細かな手戻り/指示増加
- 勤務拘束:通勤+会議の“時間税”増
- 家族負担:送迎/介護/通院などとの衝突
- 評価不安:理由なき「出社=貢献」評価の復活
【補足】まずは「目的から逆算した出社」を定義し、対面の必然性(創発/オンボ/ナレ共有)を明文化しましょう。
通勤再開がもたらすストレス
【解説】片道60〜90分の移動は可処分時間を削り、睡眠短縮→集中低下→パフォーマンス悪化の連鎖に。以下の打ち手で緩和します。
通勤ストレス軽減の打ち手
- ラッシュ回避の時差出勤
- 半日在宅(午前リモート→午後出社等)
- 打合せ集約のコア出社日設計
- ペーパーレス/電子契約の徹底
【補足】「午前:集中作業」「午後:対面MTG」のように、業務モードを時間で切り分けると効果が高いです。
ワークライフバランス崩壊と不満
【解説】ワーママ/介護層/通院持ちの社員は離職リスクが高い層。制度で守るのが近道です。
制度で守る(例)
- フレックスタイム(コア短め)
- 在宅併用(週1〜3日/半日在宅)
- 短時間勤務(期間限定も可)
- 勤務地配慮(サテライト/在宅前提配属)
【補足】「配慮は特例」ではなく、制度として誰でも使える状態にするのが定着の鍵です。
出社方式 切替の比較と影響度(保存版)

| 方式 | 離職リスク | 生産性 | 採用競争力 | 運用のコツ |
|---|---|---|---|---|
| 週5出社(全面回帰) | 高(家庭/通勤負担が集中) | 中〜低(移動/会議増) | 低(応募減の傾向) | 対面の必然性を明文化/紙業務廃止 |
| ハイブリッド(在宅併用) | 中〜低 | 中〜高(集中×協働の最適化) | 高(母集団拡大) | コア出社日/半日在宅/会議集約 |
| フルリモート(職種限定) | 低(適職なら) | 高(深い集中を確保) | 高(全国採用が可能) | 成果指標/非同期運用/情報共有自動化 |
≫ 在宅と相性の良い職種へ移るなら|給付金対応スクール比較(表)を先にチェック
テレワーク をやめたら社員が辞めた ——週5出社に戻した会社の末路

「見える化できるから管理が楽」「若手は対面で育つ」などの善意の仮説が、現場では会議増・移動増・紙復活を招き、逆に成果が下がるケースは少なくありません。方針を実装に落とすときは、制度×オペ×周知をセットで回すのが絶対条件です。
運用の失敗パターン(やりがち)
【解説】“方針発表→各自で工夫して”は機能しません。ルールと仕組みまで落とす必要があります。
失敗パターンを避けるチェック
- 会議の目的/成果物が曖昧=時間が溶ける
- 録画/議事録/資料の一元化がない=属人化
- 評価が“出社回数”寄り=行動の歪み
- 紙/押印が生存=在宅の阻害要因
【補足】“会議は最小、成果は最大”。アジェンダ→記録→自動配信の型を徹底しましょう。
辞めない会社にする対策15選(制度/オペ/周知)

ここからは、制度(枠組み)×オペ(やり方)×周知(納得形成)をワンセットで回す具体策を提示します。H3配下は編集ガイドに沿い、「解説 → 箇条書き → 補足」の順に統一しています。現場実装のしやすさを最優先に、コピペ可の定義文やテンプレを多数用意しました。
制度(働き方の枠組み)5選
【解説】制度は“誰でも使える前提”で設計し、例外運用に依存しないことが離脱抑制の鍵です。就業規則/社内規程/申請経路を一本化し、評価との整合性まで定義して初めて現場が動きます。
制度5選(保存版)
- 短めコアのフレックスタイム:コアは11:00–15:00。ラッシュ回避×家事/送迎と両立。
- 半日在宅/週2在宅の標準化:午前集中→午後対面など、時間で場を最適化。
- サテライト/在宅前提の配属:職種×業務特性で在宅適性を判断し人員を配置。
- 手当のハイブリッド設計:通勤費と在宅手当を両立。費用の不公平感を抑制。
- 評価から“出社回数加点”を除外:成果×プロセスで評価を設計。
【補足】制度の理解度は「使われているか」で測定します。申請件数/承認率/差し戻し理由をダッシュボードで可視化し、ボトルネックを毎月潰しましょう。
オペレーション(業務の回し方)5選
【解説】制度を用意しても、会議/情報/意思決定のオペが旧来のままだと“使われない制度”になります。非同期ファーストを前提に、会議は「目的→準備→成果物」で回すのが基本形です。
運用5選(会議/非同期/紙撤廃)
- 会議は3点セット:目的・アジェンダ・成果物(決定/タスク)を事前提示。
- MTG集約日:対面の価値が出る打合せを午後帯に集約、午前は無停止ゾーン。
- ペーパーレス/電子契約:押印・紙配布を原則廃止、在宅阻害要因を撲滅。
- 非同期運用:議事録・録画・資料を自動配信し、欠席の学習コストをゼロへ。
- 成果指標の明確化:KPI→KR→タスクの粒度で指示を言語化。
【補足】「会議で決めないことを決める」(情報共有/相談だけの会議を禁止)を明文化すると、実働時間が一気に回復します。
周知/コミュニケーション(納得形成)5選
【解説】方針は“伝わって初めて運用”です。FAQ・事例・サーベイの3点で摩擦を下げ、「声が上がる前に拾う」仕組みを常設します。
周知5選(納得形成の型)
- 出社の目的を定義:創発/オンボ/顧客同席など、業務価値で説明。
- 制度Q&A/事例の社内公開:よくある質問を文章/動画で。
- 月次サーベイ:不満の早期検知→1on1でフォロー。
- 1on1定例化:10〜15分でもOK。観察→仮説→次の一手。
- トライアル→棚卸し→告知:変更は試行と学びを明記。
【補足】周知文は“何が/なぜ/いつから/どう変わる”の順で。次節にコピペ可テンプレを用意しました。
「テレワーク できない 辞める」を防ぐ社内周知テンプレ(コピペ可)
【解説】現場配信にそのまま使える文章を、用途別に3種。目的→変更点→試行→測定→窓口の骨格は共通です。
テンプレA:方針変更(試行導入)
件名:【重要】出社方針の見直しと今後の働き方(1か月試行のお知らせ) 本文: 全社員のみなさま 当社は「対面の価値(創発・育成)」を最大化しつつ、皆さんの生産性と生活を守るため、 以下の方針を1か月試行します。 ・半日在宅(午前/午後いずれか)または週2日在宅を選択可 ・コア出社日:火・木(顧客同席/育成/創発を優先的に設定) ・会議は目的・アジェンダ・成果物を事前共有(記録は自動配信) ・紙/押印は原則廃止、電子契約/ワークフローへ統一 試行後にサーベイを実施し、改善点を反映して正式運用します。 ご意見は人事窓口または匿名フォームへお寄せください。
テンプレB:会議運用の刷新
件名:【会議運用の標準化】目的/アジェンダ/成果物の徹底 本文: プロジェクトの生産性向上のため、会議運用を以下に標準化します。 1) 目的と意思決定事項を冒頭で明記 2) アジェンダは24時間前に共有 3) 成果物(決定/担当/期限)を必ず文書化 4) 録画/議事録は自動配信、欠席者の学習コストをゼロへ 5) 共有のみの会議は原則禁止(資料は非同期で配布)
テンプレC:評価の方針
件名:【評価方針】出社回数を評価項目から除外します 本文: 公平な評価実現のため、評価指標を「成果/プロセス/コンピテンシー」に一本化します。 出社回数や対面頻度は評価項目に含めません。KPI→KR→タスクの整合で評価します。
【補足】テンプレ配信後は、Q&Aスレッドを同時に立て、質問と回答を蓄積しましょう。属人化が減り、離職要因の早期発見にも繋がります。
従業員向け:退職を決める前に“負担を下げる”段階的ステップ

会社の方針が固くて動きづらいときは、身を守りながら選択肢を広げる設計が重要です。ここではステップごとに、根拠→実務で示します。
STEP1:体調と可処分時間を取り戻す
【解説】通勤再開直後は、睡眠/食/運動の乱れが顕在化しやすい時期。まずは土台の復旧を。
今日からできる4つ
- 睡眠固定:起床時刻を固定、90分サイクル×5〜6を目安に。
- 移動で歩く:1駅分/階段で日中の覚醒をキープ。
- 面談/産業医:先送りせず、体調不安は記録を残して相談。
- 予定の断捨離:残業/会議の“やらないことリスト”を作成。
【補足】体調記録は勤怠/面談メモ/受診記録と紐づけると、配慮申請の説得力が増します。
STEP2:時差/半日在宅/配置転換の相談
【解説】配慮は“お願い”ではなく、業務を止めないための設計案。先に案を示すのがコツです。
合意形成のコツ
- 影響最小化:午前集中×午後対面など時間で場を使い分け。
- 計測:成果/期限/レビュー方法を事前合意。
- 期限つき試行:まずは1か月、延長も条件付きで。
【補足】合意プロセスはメール/社内チャット/ワークフローで必ず証跡を残しましょう。
申請メール/チャットのテンプレ(コピペ可)
【解説】要請→代替案→評価方法→期限の順で簡潔に。以下は使い回しやすい定型です。
在宅/時差の一部調整(メール)
件名:勤務形態の一部調整のご相談(半日在宅/時差出勤) 本文: ◯◯部 ◯◯様 △△です。通勤負担と家庭都合が重なり、体調面の不安があるため、 「午前リモート+午後出社」または「週2日在宅」を1か月試行させてください。 影響最小化のため、下記の通り業務設計を見直します。 ・午前:資料作成/分析の集中作業(成果物:◯◯レポート) ・午後:対面MTG/レビューに参加(議事録即日共有) ・評価:週次の成果レビューで確認 ご検討をお願いいたします。
チャット定型(短文)
@上長 様 通勤負担が増えたため、来月の1か月間「午前在宅+午後出社」を試行させてください。 午前は◯◯の資料作成、午後は対面レビューに集中します。週次で成果確認お願いします。
【補足】可否の回答も必ず記録に残し、人事/産業医の窓口へ連携ルートを確保しましょう。
STEP3:退職を視野に入れた計画作成
【解説】配慮が通らない/改善の見込みが薄い場合は、退職を“プロジェクト”として設計します。感情ではなく、手順×証跡×期限で安全に。
退職計画の要素
- 退職日/逆算表:有休消化/引継ぎ/最終出社日。
- 引継ぎ台帳:案件/手順/関係者/ファイルパス。
- 証跡整理:就労記録/メール/議事録/診断書等。
- 次の一歩:在宅適性の高い職種リサーチ/学び直し。
【補足】体調悪化やハラスメント時は、無理をせず退職代行や外部支援を検討。安全最優先です。
在宅と相性の良い職種×必要スキル(学び直しの道筋)

“テレワーク できない 辞める”と感じた方に向け、在宅前提でも成果を出しやすい4職種を整理します。求められるスキル・評価軸・学び方を具体化し、給付金対応スクール比較への自然導線を設計しました。
Webマーケター(広告/SEO/解析)
【解説】分析/仮説出し/資料化は非同期と相性が良好。レビュー文化を作れば在宅でも育成可能です。
要件・評価・学び方
- 要件:GA4/タグ/CRM/BI、広告運用、LP改善/ライティング。
- 評価:CV/CPA/ROAS、改善の再現性、ナレ共有。
- 学び:小規模案件→レビュー→再現。給付金対応スクール比較で時短。
【補足】“数字と言語化”の両輪(レポート→提案)を磨くと在宅での評価が上がります。
カスタマーサクセス(CS)
【解説】オンボーディング/定例はオンラインで回せます。スクリプトとプレイブックの整備が鍵。
要件・評価・学び方
- 要件:ヒアリング/課題定義、オンライン面談スキル。
- 評価:継続率/NRR/オンボ完了率。
- 学び:録画/トークスクリプトで反復、ケース演習で定着。
【補足】録画ライブラリで新人の立ち上がり時間を短縮できます。
インサイドセールス(IS)
【解説】架電/メール/MA運用などツール前提の職種。KPIが明確で在宅評価もしやすい領域です。
要件・評価・学び方
- 要件:CRM/MA、トークスクリプト運用、パイプライン管理。
- 評価:架電数/通話時間/商談創出/SQL。
- 学び:ロープレ→フィードバック→録音のセルフレビュー。
【補足】在宅のほうが集中KPIが上がるケースが多く見られます。
データアナリスト
【解説】集中仕事の代表格。要件定義とレビューを集約すれば、非同期でも品質を担保できます。
要件・評価・学び方
- 要件:SQL/BI/統計、可視化/説明力、ドキュメンテーション。
- 評価:意思決定貢献度/再現性/スピード。
- 学び:ミニ案件→レビュー→ナレ共有でポートフォリオ化。
【補足】レビューの非同期化(プルリク/コメント)が生産性を底上げします。
≫ 在宅適性が高い職種へ最短で移る|給付金対応スクール比較(表)を見る
ケーススタディ:小さな設計変更で“辞めない組織”に寄せる

事例A:営業組織|会議集約×半日在宅で残業▲12%
【解説】提案書作成/CRM入力は集中が要るため午前在宅へ。午後は対面商談とレビューを固めました。
施策(チェック)
- 週2日の午前在宅を標準化
- レビュー会議は午後に集約
- 提案書テンプレ刷新(章立て/採点表)
- CRM入力フィールドの最小化
【補足】午前の無停止ゾーンが生まれ、資料品質と提出スピードが両立しました。
事例B:情シス|非同期運用×録画ライブラリで一次対応を削減
【解説】口頭説明の属人化を断ち、3〜5分のHowTo動画とテンプレ回答で自己解決率を向上。
施策(チェック)
- 問い合わせTOP20の短尺動画を整備
- チャットのスニペット(定型)を用意
- 更新履歴と担当者を明記
- 週1回10分のナレ棚卸し会を運用
【補足】在宅/出社いずれでも同等の学習体験になり、教育コストが逓減しました。
事例C:人事|1か月トライアル→サーベイ→正式化
【解説】一発正解を狙わず、仮説→試行→学びで改善。反発は“対話不足”で起きます。
施策(チェック)
- 方針告知→1か月試行→サーベイ→改定
- 指標:残業/採用/離職/満足度を可視化
- FAQを社内ページ化(改定履歴を残す)
- 匿名の意見箱を常設
【補足】「不満の芽」を拾える設計が、離職の連鎖を止めます。
社内規程の雛形(そのままベース化OK)
【解説】規程は“使える粒度”で整備することが重要です。抽象的すぎると実装できず、細かすぎると現場が運用できません。以下は最小構成のたたき台です。自社状況に合わせて条文を追加すればすぐに使えます。
第1条(目的) 本規程は、当社の業務特性に応じ、出社と在宅を適切に組み合わせることで、生産性向上と従業員の安全・健康・私生活の調和を図ることを目的とする。 第2条(適用範囲) 全従業員に適用する。ただし雇用形態/職務内容により運用を定める。 第3条(定義) 1. ハイブリッド勤務:出社と在宅を併用する勤務形態 2. 半日在宅:午前または午後のみ在宅で就労する形態 3. コア出社日:対面協働の価値を最大化するための指定日 第4条(勤務形態) 1. コア出社日を原則週2日設定する。 2. 在宅勤務は週1〜3日を上限の目安とし、業務特性により柔軟に運用できる。 3. フレックスタイム制(コア11:00-15:00)を適用する。 第5条(申請・承認) 1. 在宅/半日在宅の利用は、前日までに上長へ申請する(緊急時はこの限りでない)。 2. 申請は所定フォーマット(チャット/ワークフロー)を用いる。 第6条(情報セキュリティ) 1. 社外持出禁止データの在宅作業を禁止する。 2. VPN/多要素認証/暗号化ストレージを必須とする。 3. 紙資料の持出は原則禁止し、必要時は記録を残す。 第7条(評価・労務) 1. 評価は成果/プロセス/コンピテンシーに基づき、出社回数を評価項目に含めない。 2. 労働時間は勤怠システムで管理し、時間外労働は事前申請を要する。 第8条(見直し) 本規程は、運用状況/サーベイ結果/法令等を踏まえ、定期的に見直す。
【補足】評価指標に“出社回数”を含めないことを明文化するだけでも、社員の安心感は大きく変わります。
従業員向け:メール/退職手順のテンプレ(コピペ可)

在宅/時差勤務の配慮をお願いするメール
【解説】依頼を通すコツは、成果を最優先に考えていると伝えること。単なる「お願い」ではなく「業務設計の改善案」として提示します。
メール文例(コピペ可)
件名:勤務形態の一部調整のご相談(半日在宅/時差出勤) 本文: ◯◯部 ◯◯様 いつもお世話になっております。△△です。 現在、通勤負担と家庭都合が重なり体調面の不安があるため、 「午前リモート+午後出社」または「週2日在宅」を試行させていただけないでしょうか。 成果への影響を最小化するため、下記の通り業務設計を見直します。 ・午前:資料作成や分析を在宅で集中 ・午後:対面会議や顧客対応に合わせて出社 ・議事録やタスクは即日共有 まずは1か月の試行で評価いただき、必要に応じて改善します。 ご検討のほどよろしくお願いいたします。
退職意思を伝えるメール
【解説】退職意思は、引継ぎ計画を添えることで摩擦を最小化できます。感情ではなく、プロセスを重視して伝えるのが安全です。
退職通知メール例(コピペ可)
件名:退職のご報告 本文: ◯◯部 ◯◯様 △△です。私事で恐縮ですが、一身上の都合により◯月末を目処に退職させていただきたく存じます。 引継ぎ計画(担当業務/資料/スケジュール)は別紙にて準備いたしました。 お手数ですが、手続きのご案内をいただけますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。
もし体調やメンタルが限界なら、無理は禁物です。
よくある誤解と反論への答え方
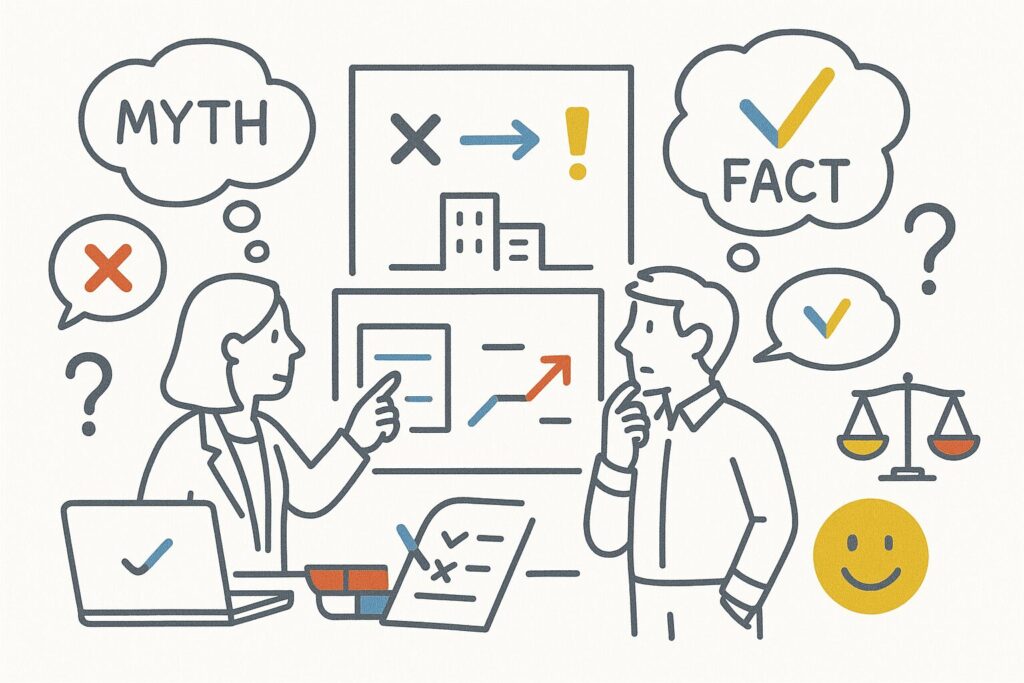
「出社のほうが生産性が高い」
【解説】業務の性質によります。非同期で進むタスクは在宅が効率的。一方で創発やオンボは対面が有効。大事なのは「内容×場の最適化」です。
見極めの視点
- 個別集中タスク:在宅(ドキュメント作成/分析/コーディング)
- 創発・相談・育成:対面(ワークショップ/ペア作業)
- 顧客同席:対面優先(関係構築/合意形成)
「管理が楽になる」
【解説】出社で“見える化”はしやすくなりますが、ムダな会議や移動が増えて逆に時間を失うことも。成果物ベースのマネジメントへ移行すべきです。
「若手は出社で育つ」
【解説】育成は仕組み次第。1on1/メンター制度/録画ライブラリ/コードレビューなどを組み合わせれば、在宅でも十分に育成可能です。
健康・メンタルのセルフケア(従業員向け)

【解説】出社負担が大きい時期は、まず睡眠/食事/運動/相談の基礎を整えることが最優先です。セルフケアが崩れると、判断力も鈍ります。
今日からできる4つ
- 睡眠:90分単位×5〜6サイクルを基準に、起床時刻を固定する
- 運動:移動に「歩く」を足す(1駅分/階段)で日中の覚醒度を上げる
- 相談:産業医/保健師/心療内科の利用を先送りしない
- 記録:体調や相談内容をメモし、次の面談に活かす
【補足】自力で難しいときは、支援窓口や外部サービスの早期利用を検討してください。
まとめ:出社の“価値”を設計し、離職の連鎖を断つ
要点
- 完全オフィス回帰は離職/採用難/生産性低下を招きやすい
- 制度(フレックス/半日在宅)×オペ(会議最適化)×周知(納得形成)の三位一体運用が鍵
- 従業員側は配慮申請→配置転換→退職準備の段階ステップで安全に。
FAQ
テレワーク をやめたら社員が辞めた のはなぜ?
- テレワーク をやめたら社員が辞めた のはなぜ?
- 自律性の喪失、通勤負担の復活、家庭都合との衝突、評価の不公平感が重なるためです。
週5出社に戻した会社の末路は?
- 週5出社に戻した会社の末路は?
- 離職増・採用難・生産性停滞に直面しやすく、競合に人材や商談が流れるリスクがあります。
ハイブリッドでも業務が回らない時の対策は?
- ハイブリッドでも業務が回らない時の対策は?
- 会議の目的と成果物の明確化、MTG集約日、非同期運用、紙/押印の撤廃で改善します。
従業員が今日からできることは?
- 従業員が今日からできることは?
- 体調管理、時差/半日在宅の申請、証跡の保存、退職準備の4ステップです。
退職を決めたら何から着手すべき?
- 退職を決めたら何から着手すべき?
- 退職日/引継ぎ計画の確定、社内申請、私物整理、受給や次職の準備です。
出社命令に合理性が感じられない時は?
- 出社命令に合理性が感じられない時は?
- 目的や業務価値の説明を求め、代替案を提示し、合意形成を図ります。
在宅手当が廃止されて通勤費だけ増えたら?
- 在宅手当が廃止されて通勤費だけ増えたら?
- 費用負担の変化を可視化し、ハイブリッド手当等の再設計を人事に提案します。
新人のオンボーディングは在宅併用でも可能?
- 新人のオンボーディングは在宅併用でも可能?
- 可能です。録画/資料/メンター/ペア作業を組み合わせ、必要日に対面セッションを設けます。
上司が申請を却下し続ける場合は?
- 上司が申請を却下し続ける場合は?
- 理由の明文化を求め、人事や産業医にエスカレーションし、記録を残します。
退職代行を使うタイミングはいつ?
- 退職代行を使うタイミングはいつ?
- 体調悪化やハラスメントで交渉が難しい場合は早めが安全です。証跡と引継ぎ計画を準備しましょう。