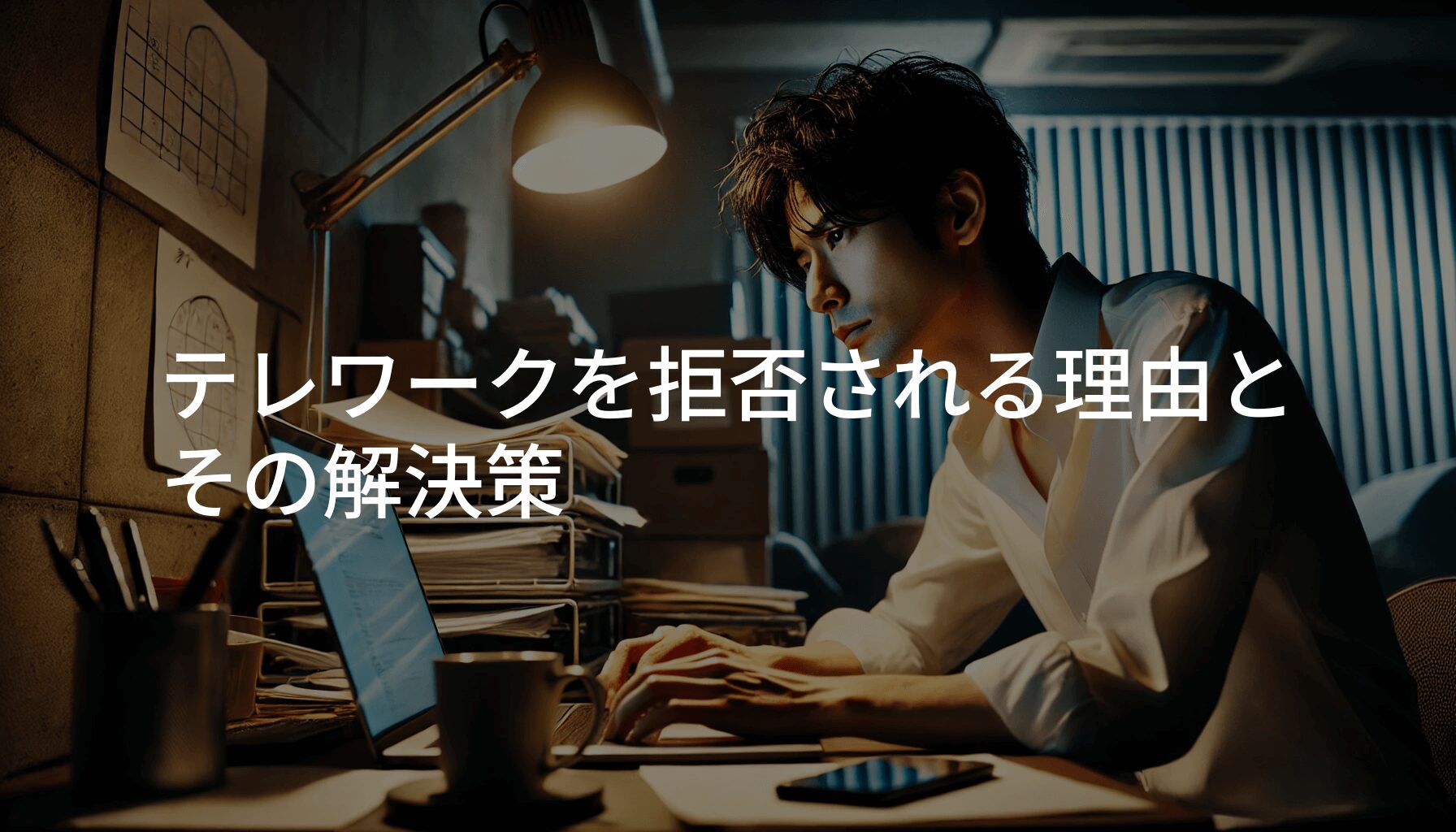通勤の負担を減らしたいし、仕事の効率も上がるはずなのに納得いかないよね。
このまま放置すると、ワークライフバランスが崩れ、モチベーションも下がるかもしれません。
そこで、今回はテレワークを拒否される理由とその解決策について紹介します!
この記事で分かること!
- 会社がテレワークを拒否する理由
- 上司を納得させる説得方法
- テレワークを実現するための行動
なぜテレワークをさせてもらえないのか?その理由を解説
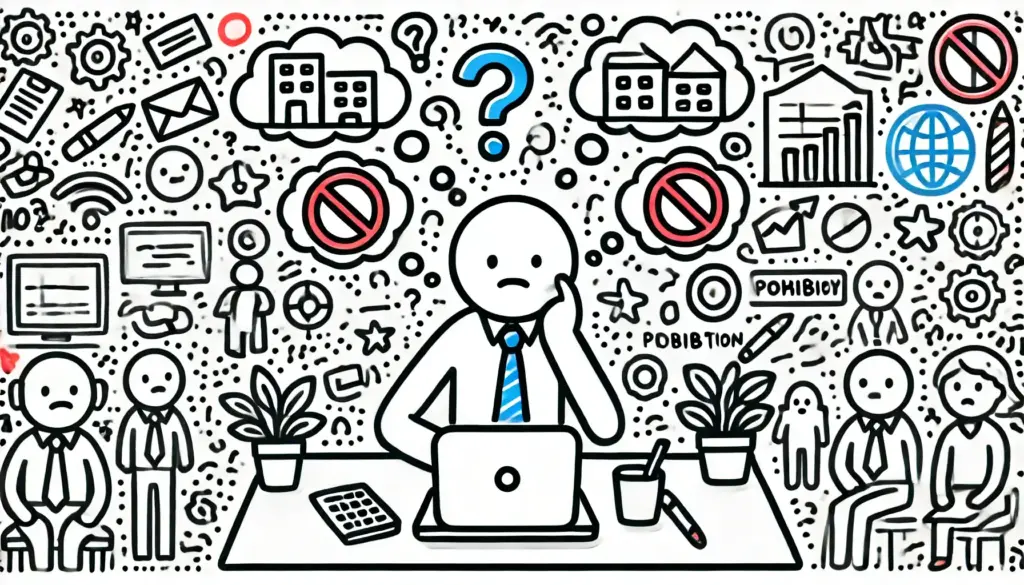
テレワークを希望しても、会社や上司が許可してくれないケースは少なくありません。
企業側の立場から見ると、テレワークを認めないのには明確な理由があります。
これらの理由を理解し、適切に対処することでテレワークの実現が可能になります。
会社の制度が整っていない
テレワークが導入されていない会社の多くは、制度や環境が整っていないことが原因です。
企業がテレワークを導入するには、就業規則の改訂やシステムの整備が必要です。
特に、次のような課題がハードルになっています。
- テレワークに関する就業規則が未整備
- 業務に必要なクラウド環境やVPNが未導入
- 労働時間の管理が難しいと考えられている
- セキュリティ対策が不十分
たとえば、ある中小企業ではテレワークを導入しようとしたものの、社内規則の改訂が進まず、正式な制度として認められませんでした。
また、クラウドツールの導入コストを負担できず、従業員全員のリモートワーク環境を整備できないケースもあります。
このような場合、従業員としては「個別にリモートワークを試験導入する」などの提案をするのが有効です。
上司に「コストを抑えてテレワークを試す方法」を提示することで、制度整備が進む可能性があります。
会社の制度が整っていない場合は、小さな一歩から始めるのが現実的です。
業務の生産性が下がると考えられている
上司や経営陣が「テレワークでは生産性が落ちる」と考えていることも、許可が下りない理由の一つです。
特に、目に見える形で仕事をしていないと「サボっているのでは?」と思われることがあります。
会社がテレワークを敬遠する主な理由は以下のとおりです。
- 勤務態度を直接確認できない
- オンラインでは進捗管理が難しい
- 対面の方が業務スピードが速いと考えている
- テレワークの効果を測る評価基準がない
実際、ある企業では、テレワーク導入後に一部の社員の業務進捗が遅れ、社内から不満が出ました。
しかし、問題の原因を調査すると「業務フローの最適化不足」や「ツールの活用不足」が影響していたことが判明しました。
このような懸念に対しては「成果ベースの評価制度を導入する」「業務の進捗を見える化するツールを提案する」などの対策が有効です。
上司が生産性の低下を理由にテレワークを拒否している場合は、データを示して反論するのが効果的です。
テレワークで生産性が向上した事例を調査し、具体的な提案を行いましょう。
コミュニケーション不足を懸念されている
テレワークでは対面での会話が減るため、コミュニケーション不足が懸念されることが多いです。
特に、業務上の相談や指示の伝達が円滑に行えないことを理由に、テレワークが敬遠されることがあります。
企業が抱える具体的な不安は次のようなものです。
- 社員同士の雑談や情報共有が減る
- 質問や確認がしにくくなる
- オンライン会議では細かいニュアンスが伝わりにくい
- チームの一体感が薄れる
例えば、ある営業チームでは、テレワーク中に案件の進捗が共有されず、情報の遅れが原因で取引先との調整ミスが発生しました。
このような問題に対処するためには、以下のような工夫が有効です。
- 毎朝オンラインで短時間のミーティングを行う
- チャットツールを活用し、気軽にやり取りできる環境を作る
- 業務の進捗を可視化するシステムを導入する
- 定期的に対面での会議や交流会を実施する
上司に対して、これらの対策を提案することで、コミュニケーション不足への不安を和らげることができます。
「テレワークでも円滑に情報共有できる」という実例を示せば、導入の可能性が高まるでしょう。
管理職の意識がテレワークに否定的
テレワークを認めてもらえない大きな要因の一つが、管理職の意識です。
特に、従来の働き方に慣れている上司ほど、「オフィスにいないと仕事をしていない」と考える傾向があります。
管理職がテレワークを否定する主な理由は以下のとおりです。
- 部下の勤務状況を直接確認できない
- 成果よりも「働いている姿」を重視している
- オンラインでのマネジメントに慣れていない
- 新しい働き方を受け入れるのに抵抗がある
例えば、ある企業では、管理職がテレワークに消極的だったため、導入が遅れていました。
しかし、試験的にテレワークを実施し、業務報告や進捗管理を徹底することで、徐々に信頼を得ることができました。
管理職の理解を得るためには、以下のアプローチが有効です。
- テレワークでも成果を出せることをデータで示す
- 週次や月次の報告制度を整え、不安を解消する
- 他社の成功事例を紹介し、導入のメリットを説明する
- 試験的に短期間のテレワークを提案する
上司の意識を変えるには時間がかかるため、段階的にアプローチしていくことが重要です。
まずは「1週間に1回のテレワーク」など、小さな試みから始めるのが現実的でしょう。
過去にテレワークで問題が発生した
会社がテレワークを許可しない背景には、過去の失敗事例が影響している場合があります。
実際にテレワークを導入したものの、運用がうまくいかずに撤退した企業もあります。
よくある問題点として、以下のようなケースが挙げられます。
- 一部の社員がサボるようになった
- 業務効率が低下し、取引先からクレームが入った
- セキュリティ問題が発生し、情報漏洩のリスクが高まった
- 適切な評価制度がなく、給与査定が難しくなった
例えば、ある企業では、テレワーク中に社員が副業をしていたことが発覚し、社内で問題になりました。
また、機密情報の取り扱いが徹底されておらず、データ漏洩のリスクが指摘されたケースもあります。
過去の失敗が原因でテレワークが難しくなっている場合、次のような解決策を提案できます。
- 勤務状況を適切に管理できるツールを導入する
- セキュリティ対策を強化し、ルールを明確にする
- 成果ベースの評価制度を整え、適正な査定を行う
- 小規模な部署から段階的に再導入する
「過去に失敗したから無理」と決めつけず、問題点を改善できる方法を提示することが重要です。
特に、具体的な成功事例を示すことで、再導入の可能性を高めることができます。
上司が納得するテレワークのメリットと説得方法

テレワークを導入することで、企業や従業員の双方にさまざまなメリットがあります。
上司を説得するには、単に「自分がテレワークをしたい」と伝えるだけではなく、会社にとっての利点を明確に示すことが重要です。
上司の懸念を払拭し、納得感を得られるような具体的な提案を行いましょう。
仕事の効率が向上する理由を伝える
テレワークの導入により、仕事の効率が上がることをデータとともに説明すると、説得力が増します。
オフィス勤務と比較して、以下のような点で業務効率が向上することがわかっています。
- 通勤時間がゼロになり、業務に集中できる
- オフィスの雑音や突発的な会話がなくなり、集中力が高まる
- 自分のペースで仕事ができ、生産性が向上する
- 適切な時間管理により、無駄な残業が減る
例えば、ある企業では、テレワークを導入した結果、従業員の生産性が平均20%向上し、業務効率が改善されたと報告されています。
上司に対して「テレワークを導入すれば業務効率が上がる」というデータを示し、メリットを強調しましょう。
コミュニケーションツールの活用を提案する
テレワークの最大の懸念点の一つが「コミュニケーション不足」です。
しかし、適切なツールを導入すれば、対面と同じレベルの情報共有が可能になります。
具体的には、以下のようなツールを提案すると効果的です。
- SlackやChatworkを活用し、迅速な情報共有を実現
- ZoomやGoogle Meetを使用して、定期的なオンライン会議を実施
- タスク管理ツール(Trello、Asanaなど)で進捗を可視化
- VPNやセキュリティ対策ソフトを導入し、安全な環境を確保
例えば、ある企業では、SlackとZoomを組み合わせることで、オフィス勤務時と同じレベルのコミュニケーションを維持できるようになりました。
上司に対して「これらのツールを活用すれば、コミュニケーション不足の問題は解決できる」と提案することで、テレワークの導入を後押しできます。
成果ベースの評価制度を説明する
上司がテレワークに反対する理由の一つに「勤務態度を直接確認できない」という懸念があります。
しかし、テレワークでは「成果ベースの評価制度」に移行することで、公平な人事評価が可能になります。
具体的には、以下のような評価基準を提案すると説得しやすくなります。
- 業務の進捗を明確にし、成果を定量的に評価する
- 勤務時間ではなく、アウトプットの質を重視する
- 報告・連絡・相談を徹底し、上司との信頼関係を築く
- 定期的な評価面談を実施し、仕事の状況を確認する
例えば、ある企業では、テレワーク導入後に「目標達成率」と「納期遵守率」を評価基準として設定した結果、公平な人事評価が可能になりました。
上司に対して「成果ベースの評価制度を導入すれば、テレワークでも適正な評価ができる」と説明することで、納得を得られやすくなります。
会社のテレワーク拒否に対する労働者の権利とは?
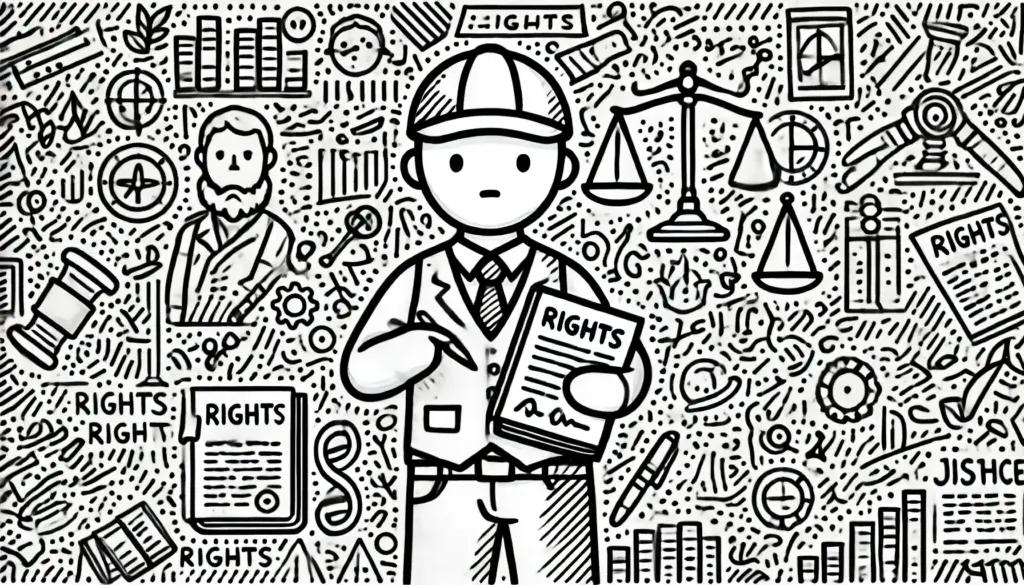
会社がテレワークを許可しない場合でも、労働者には一定の権利があります。
法律や就業規則を確認することで、適切な対応ができる可能性があります。
会社の方針だけで諦めず、法律や社内制度を活用できるか確認しましょう。
労働基準法から見るテレワークの可能性
労働基準法には、テレワークを義務化する規定はありません。
しかし、労働者の健康や安全を守るため、企業には「労働環境の整備義務」があります。
特に、次のような点がテレワーク導入の根拠になり得ます。
- 長時間通勤が健康に悪影響を及ぼす可能性がある
- 育児や介護との両立を支援する必要がある
- 感染症対策としてリモートワークを推奨すべき状況がある
- 労働者の安全を確保する観点から在宅勤務を認めるべきケースがある
例えば、新型コロナウイルスの流行時には、厚生労働省が企業に対してテレワークを推奨しました。
このような状況では、会社が一方的に拒否することは適切ではないと考えられます。
法的な根拠を示しながら、テレワークの必要性を訴えることが重要です。
就業規則の確認ポイント
テレワークの可否は、会社の就業規則に大きく左右されます。
事前に確認すべきポイントは以下の通りです。
- テレワークに関する明確な規定があるか
- 勤務場所に関する制限が記載されているか
- フレックスタイム制度の有無
- 会社が「出社義務」を定めているか
例えば、ある企業では就業規則に「業務遂行に支障がなければ、在宅勤務を認める」と記載されていました。
このような記載がある場合、会社側に交渉する余地があります。
逆に、「業務は原則オフィスで行う」と明記されている場合は、個別の例外措置を提案する必要があります。
労働組合や社内相談窓口の活用
会社がテレワークを一切認めない場合、労働組合や社内相談窓口を活用することも一つの方法です。
労働組合を通じて交渉を行うことで、より多くの従業員が働きやすい環境を実現できる可能性があります。
労働組合や相談窓口の活用方法として、以下の手順を検討しましょう。
- 社内の労働組合があるか確認する
- テレワークの必要性を組合に相談する
- 同じ意見の同僚と協力して要望を提出する
- 社外の労働相談機関(労働局など)に問い合わせる
例えば、ある企業では労働組合がテレワーク導入を求めた結果、試験的に週1回の在宅勤務が認められました。
一人で交渉するのが難しい場合は、組合や第三者の力を借りるのも有効な手段です。
テレワークを導入しない企業の事情とその対策

企業がテレワークを導入しないのには、経営側の事情が関係している場合もあります。
会社の立場や懸念を理解し、具体的な解決策を提示することで、テレワーク導入の可能性を高めることができます。
企業の事情を理解しつつ、現実的な対応策を考えていきましょう。
業務上テレワークが難しい職種の特徴
すべての職種がテレワークに適しているわけではなく、業務内容によっては難しい場合があります。
特に、次のような職種ではテレワークの導入が困難とされています。
- 工場や物流センターでの現場作業が必要な職種
- 対面での接客や販売を行う職種
- 医療や介護など、直接人と関わる業務
- 機密性の高い情報を取り扱う業務
例えば、製造業の現場作業員は、設備を操作する必要があるため、リモートワークは現実的ではありません。
しかし、事務作業やデータ入力業務を分離して、可能な範囲でテレワークを導入するケースもあります。
自分の業務のどの部分がテレワーク可能かを整理し、部分的な導入を提案するのが現実的なアプローチです。
企業が抱えるセキュリティリスクとは?
テレワークの導入を渋る理由の一つとして、セキュリティリスクへの懸念が挙げられます。
企業が考える主なセキュリティリスクは以下の通りです。
- 社外での業務による情報漏洩のリスク
- 個人端末の使用によるウイルス感染の可能性
- 社内ネットワークへの不正アクセス
- データの管理が徹底できない
例えば、ある企業では、従業員が自宅のWi-Fiを使って業務を行った結果、外部からの不正アクセスを受け、データ流出の危機に陥りました。
このようなリスクを回避するために、以下のような対策が必要です。
- VPNを導入し、安全な接続環境を整備する
- 会社支給のPCを使用し、個人端末の利用を制限する
- クラウドストレージを活用し、データ管理を徹底する
- 定期的なセキュリティ研修を実施する
これらの対策を提案することで、企業側の懸念を解消し、テレワーク導入を進めることができます。
テレワーク導入が進んでいる業界との比較
業界によっては、すでにテレワークが広く導入されているところもあります。
上司や経営陣を説得する際には、他業界の成功事例を紹介するのが効果的です。
特に、以下の業界ではテレワークが普及しています。
- IT業界(エンジニア・デザイナーなど)
- コンサルティング業界(リモートでのクライアント対応)
- メディア・ライター業界(記事作成や編集業務)
- マーケティング業界(データ分析や広告運用)
例えば、あるIT企業では、社員の90%がフルリモート勤務を実現し、通勤時間の削減により生産性が向上しました。
自社と同じ業界でテレワークを導入している企業の事例を調査し、「競争力を維持するために必要な施策」として提案すると、納得を得られやすくなります。
テレワークを希望する社員ができる行動3選

会社がテレワークを認めない場合、ただ待っているだけでは状況は変わりません。
個人でできる具体的な行動を起こすことで、働き方を改善できる可能性があります。
自分の状況に合った方法を選び、行動を起こしていきましょう。
会社に具体的な提案をする
テレワークを希望する場合、単に「やりたい」と伝えるのではなく、具体的な提案をすることが重要です。
上司を説得するために、以下のような資料を作成すると効果的です。
- テレワークのメリットを整理した資料
- 他社の成功事例やデータ
- 自分の業務でテレワークが可能な理由
- 導入時の問題点とその解決策
例えば、ある企業では、社員が「試験的に週1回のテレワークを実施する」提案を行い、上司が納得した結果、正式な制度化につながりました。
いきなり大きな変化を求めるのではなく、「まずは試験導入から」と段階的に提案することで、実現しやすくなります。
同僚と協力して働き方改革を促す
一人での交渉が難しい場合、同じ意見を持つ同僚と協力するのも有効な手段です。
複数人で意見をまとめ、会社に提案することで、経営層の関心を引きやすくなります。
働き方改革を進めるための具体的な方法は以下の通りです。
- テレワークを希望する社員でグループを作る
- 定期的に意見を交換し、課題を整理する
- 会社に対して正式な要望書を提出する
- 労働組合や社内の意見交換会で発言する
例えば、ある企業では、営業部の社員5人が合同で「移動時間を削減し、より多くの顧客対応ができる」とテレワーク導入を提案し、結果的に部分的な導入が実現しました。
個人の意見では難しくても、複数人の意見が集まると、会社側も無視できなくなります。
転職を視野に入れる
会社が頑なにテレワークを認めない場合、転職を視野に入れることも選択肢の一つです。
特に、次のような条件に当てはまる場合は、他の企業を検討する価値があります。
- 会社が一切テレワーク導入の可能性を示していない
- ワークライフバランスが崩れ、健康や家庭に支障が出ている
- 同業他社ではテレワークが一般化している
- 長時間通勤によるストレスが大きい
例えば、IT業界ではリモートワークが標準化されつつあり、テレワーク可能な求人が増えています。
転職活動をする際は、以下のようなポイントに注目するとよいでしょう。
- 企業のテレワーク実施率を確認する
- 求人情報に「フルリモート可」「在宅勤務可」の記載があるかチェックする
- 転職サイトやエージェントを活用して情報収集する
- 実際にテレワークをしている社員の口コミを調べる
転職は大きな決断ですが、働き方を柔軟に選べる企業に移ることで、より快適な環境を手に入れることができます。
「今の会社ではテレワークが無理」と判断した場合、前向きにキャリアを考え直すことも重要です。
まとめ
テレワークをさせてもらえない理由は、企業の制度や上司の考え方に起因していることが多いです。
しかし、適切なアプローチを取ることで、テレワーク導入の可能性を高めることは十分に可能です。
今回紹介したポイントを振り返りましょう。
- 会社がテレワークを拒否する理由を理解し、それに対応する
- 上司が納得できる形でメリットを説明する
- 法律や社内制度を活用して、可能性を探る
- 企業側の事情を踏まえた現実的な対策を講じる
- 自ら行動を起こし、必要なら転職も視野に入れる

まずはできることから行動を始めて、より良いワークスタイルを実現しましょう。