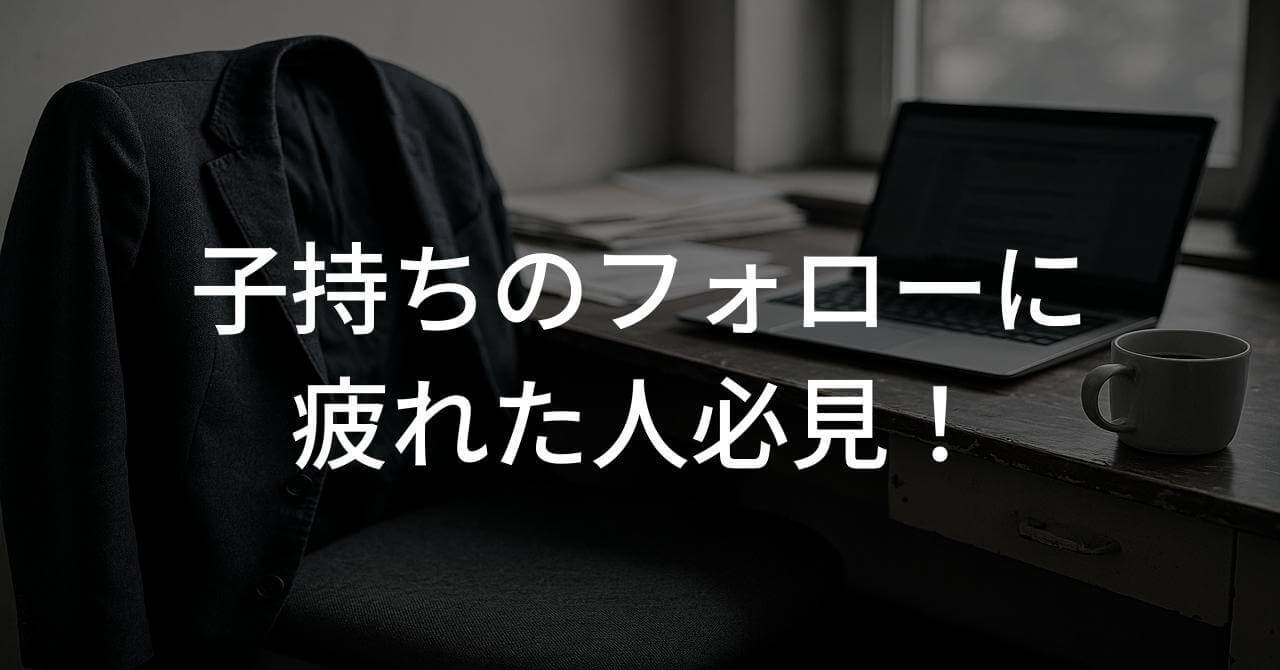月曜の朝。子育て中の同僚がまた「子どもが熱を出して…」と欠勤の連絡。
慌ただしく上司から指示が飛び、「○○さんの分も頼むね」と当然のように回ってくる業務。
その瞬間、「またか」「なんで私ばっかり…」と心の中でつぶやいたあなた。
――その感情、正しいです。あなたが抱える疲れと怒りは、甘えでも冷たさでもありません。
そこで、今回は
“頑張りすぎているあなた”が自分を守るための考え方と、少しでも業務負担を軽くするための実践策
について紹介します!
完全匿名・無料で退職相談する
この記事で分かること!
- 「子持ちのフォローに疲れた」と感じる心理の背景と社会的な構造
- 不満や怒りを抱え込まずに伝える言葉の工夫と行動のヒント
- 業務負担を軽減するために、職場で実践できる対処法と提案
「子持ちのフォローに疲れた…」その気持ちはあなた一人じゃない

突然の欠勤や早退で、あなたばかりが残業していませんか?
子育て中の同僚をサポートするのが当然のような空気に、疲れている人は少なくありません。
以下では、子持ちのフォローで感じるモヤモヤを分解し、解決の糸口を探ります。
予期せぬ欠勤・早退…なぜ“私ばかり”がフォローを?
同僚の突然の早退に、またか…とため息をついたことはありませんか?
「私ばかりが残って対応している」と感じると、疲れや怒りが蓄積します。
この負担の偏りは 仕事の属人化 が原因です。
- 業務の引き継ぎ体制がない
- 同じ人ばかりに仕事が集中
- 「急な欠勤=フォローが当然」
- 感謝の言葉がない
たとえば、ある営業職の女性は、育児中の同僚の代わりにクレーム対応まで請け負っています。
それでも「ありがとう」の一言すらなく、日々消耗していました。
このような状況が続けば、職場への信頼もやる気も失われてしまいます。
一人で背負わなくていい がこのパートのキーワードです。
「子持ち様」問題と不公平感の正体
ネットでもたびたび話題になる「子持ち様」問題。
これは、育児中の社員が優遇されすぎていると感じる不満の表れです。
背景には 制度と意識のギャップ があります。
- 子育て支援制度がフォロー側に還元されない
- 感謝や気遣いの言葉がない
- 周囲への負担を当然とする風潮
- 「助けて当たり前」という無意識の期待
フォローする側もまた生活があり、時間や体力に限界があります。
「子持ちだから仕方ないよね」と割り切れないのは自然なことです。
その不公平感は、制度の設計ミスや運用不足から生まれていることが多いのです。
疲れの原因は“制度不足”と“無自覚な期待”
制度があっても運用されなければ形骸化します。
また、上司や同僚が「誰かがなんとかしてくれる」と無意識に期待していると、負担が一部の人に集中します。
改善すべきは「一人が我慢する仕組み」そのものです。
人手が少なくても、以下の工夫で軽減は可能です。
- タスクの共有化・マニュアル化
- バックアップ担当の明確化
- 感謝や配慮の言葉を意識的に伝える
小さな工夫でも、疲弊を防ぐ効果は大きいのです。
人が足りない職場で「助け合い」は機能しない
根本的に人員が不足している職場では「助け合い精神」は破綻します。
常に誰かがフォロー役になり、消耗して辞めていく…という悪循環が起こります。
この環境下で「我慢し続ける」ことは解決策ではありません。
環境を変える=職場を選び直すことも現実的な選択肢 です。
“疲れた”を解消する現実的な抜け道を見る(無料)
不満を溜め込まないためにできる3つの対処法
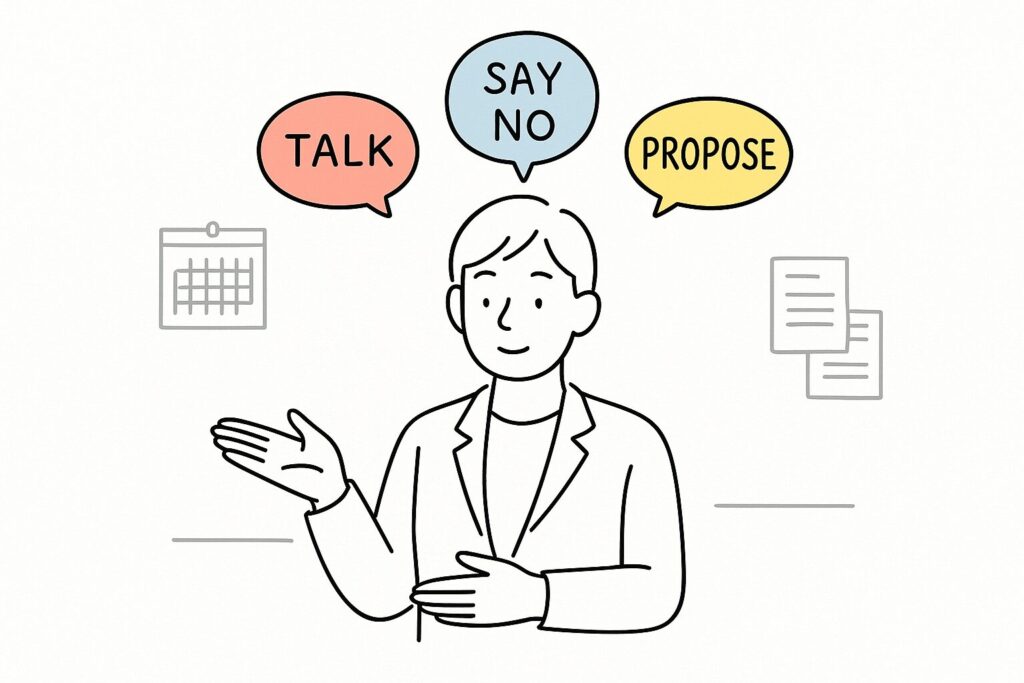
モヤモヤを抱えたまま働き続けるのは限界があります。疲れきる前に、自分のための対処を始めましょう。
上司に伝えるべき「具体的な困りごと」の言語化
「負担が大きい」と抽象的に伝えるのではなく、「毎週◯回残業が発生している」「休日に対応している」など具体的な事実を示しましょう。
言語化すれば、上司も改善に動きやすくなります。
自分の限界を守る「NO」の伝え方
全てを引き受けてしまうと、あなたの心身が先に壊れます。
「今日は既に納期がある仕事があるので対応できません」など、客観的な理由を添えて伝えると角が立ちにくくなります。
小さな改善でもOK!業務負担を減らす提案例
完璧な改革でなくても、以下のような改善で負担は軽くなります。
- 定例業務のシフト制導入
- 共有ツールで進捗を見える化
- 「誰でもできる仕事」を増やす
提案を一つ実現するだけでも、心理的な疲れは大きく減ります。
それでも変わらないなら?「職場を選ぶ」という現実的な選択
提案をしても改善が見られない職場は、あなたの努力で変わる見込みが低い可能性があります。
「今の場所で耐える」ことがゴールではありません。環境を変えることも立派な対処法です。
心が折れそうなあなたへ:共感とリカバリーのヒント

頑張りすぎてしまう人ほど、自分を責めがちです。
「イライラする自分は冷たいのでは?」と思うかもしれませんが、それは正常な反応です。
大事なのは、怒りや不満を正しく処理すること。信頼できる人に話す、記録する、専門の窓口を利用するなど、吐き出す方法を持ちましょう。
心が折れそうになったとき、外の視点やプロの力を借りることは甘えではなく、自分を守る行動です。
実際に「子持ちのフォローで疲れた」人のリアルな声
共感だけで終わらせないために、よくある3つのパターンを要点化しました。
ケースA:感謝がなく、当たり前化されている
- 同僚の突発休で必ず自分に仕事が回る
- 「助かった!」の一言がない日が続く
- → 当番制+見える化で偏りを是正
ケースB:上司が“良い人”だが采配が曖昧
- 「みんなで助け合おう」だけが指示
- 忙しい人に更にタスクが積まれる
- → 「事実×影響×要望」で配分ルールの明文化を依頼
ケースC:人手不足が恒常化している
- 誰かの欠勤で毎日が綱渡り
- 属人タスクが多く、引き継ぎ不可
- → 属人化の解除(手順書・教育)と、出口選択の検討
フォローが偏るのは法的に問題?労務・相談の視点

「偏った負担」は直ちに違法とは限りませんが、状況次第で職場環境配慮義務の不備やパワーハラスメント相当の言動が絡むこともあります。まずは社内外の相談先を把握しましょう。
- 社内:人事・労務、コンプラ窓口、産業医
- 外部:労働局総合労働相談コーナー、法テラス、自治体労働相談
参考:厚生労働省「ハラスメント対策」
公式ページ
相談準備のチェック:
・偏りが発生した日時/回数 ・巻き取った作業の具体 ・あなたの業務遅延/健康影響 ・上司へ伝えた事実と返答
これらを時系列で整理すると、社内外の窓口が動きやすくなります。
心理的安全性を取り戻す:セルフケアと境界線の作り方
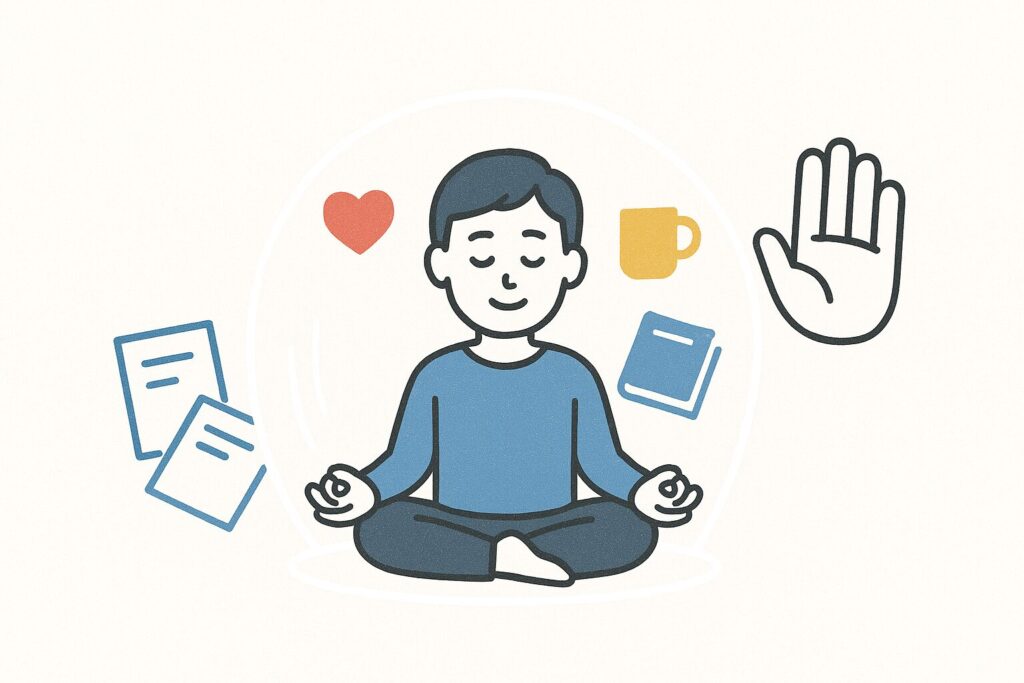
- 境界フレーズ:「いまは着手中の案件があり、◯時以降なら対応可能です」
- 時間を見える化:自分のカレンダーに“集中ブロック”を設定
- 回復ルーティン:終業前の5分ストレッチ/画面オフ15分
- 感情の棚卸し:一日3行で「出来た・助けた・疲れた」を記録
感情労働の負荷は可視化すると下がる傾向があります。小さな回復の積み重ねが、明日の交渉力になります。
フォロー疲れを減らした「現場の工夫」3つの実例
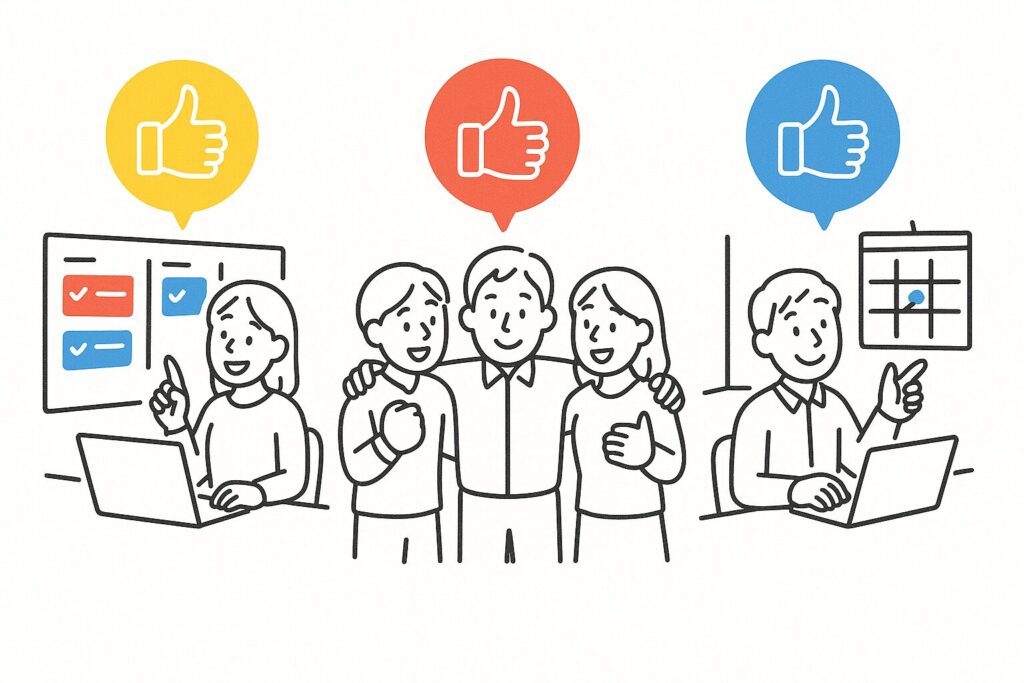
- 週替わりの“突発当番”制度
突発タスクはその週の当番が一次受け→翌朝に簡易振り返り。特定個人への固定化を防止。 - 10分マニュアル(誰でも出来る化)
属人タスクを「10分で読める手順書」に圧縮。新人や他部署でも応援に入れる状態を維持。 - “ありがとうログ”の運用
Slack/Teamsで「助け合い」を一行投稿。心理的報酬を可視化し、偏りやすい人の救済議論がしやすくなる。
人手不足でも回る仕組み+出口の作り方を確認(Part1)
そのまま使える:断り方・上司への伝え方テンプレ
① 角を立てずに断る(選択肢提示)
「いま納期前の案件が進行中で直ちには難しいです。◯時以降であれば着手可能です。急ぎでしたら、当番の◯◯さん or チーム窓口をご指定いただけますか?」
② 上司への相談(事実×影響×要望)
事実:直近2週間で◯回、◯◯さんの業務を引き継ぎました。
影響:自業務の◯◯レポートが毎回◯日遅延し、残業が週◯時間増えました。
要望:突発当番の週替わり運用と、10分手順書の整備をご検討ください。
③ チーム向けアナウンス(丁寧な線引き)
「突発対応は当番の一次受け→翌朝共有にします。個別DMではなく、チャンネル#supportへお願いします。緊急は@当番メンション可。22時~7時は通知オフです。」
見直しチェックリスト(保存推奨)

- 突発当番(週替わり)が決まっている
- 属人タスクに10分手順書がある
- 相談・依頼はチャンネル固定(私信NG)
- 偏りの回数を記録し、月次で見直す
- 「出来た・助けた・疲れた」を1日3行で記録
- 社内外の相談先をブックマーク済み
▶ 不公平を“仕組み”と“制度”で逆転する(Part1へ)
まとめ|「子持ちのフォロー疲れ」を、仕組みで減らす
- 事実ベースで伝えると、初めて“職場の課題”になる
- 見える化と当番制は、属人化を外す最短ルート
- それでもダメなら、あなたには選ぶ権利がある
制度活用・出口戦略の全体像を5分で把握できます。
よくある質問(追記)
Q. 感謝がなくて当たり前化したフォロー、どう線引きすべき?
当番制と見える化の導入が最短です。まずは事実×影響×要望(本文テンプレ)で上司に相談し、「突発は当番が一次受け」のルールを明文化。個別DMでの直接依頼は禁止し、チャンネル固定+翌朝共有にします。
Q. 断ったあとに陰口や圧が怖いです…
断り文は選択肢提示(◯時以降なら可能・当番へ依頼)で礼節を保ち、同時に記録(日時・内容・相手反応)を残してください。繰り返しの圧があれば、相談窓口に時系列で提出できる形にしておくと守られやすくなります。
Q. 人手不足で何も始められないときの“最小一歩”は?
「10分手順書」を1本だけ作る→週替わり当番を試験導入→“ありがとうログ”で心理報酬を見える化、の順が現実的。まずは最頻出タスク1本の誰でも化から始めるのがおすすめです。