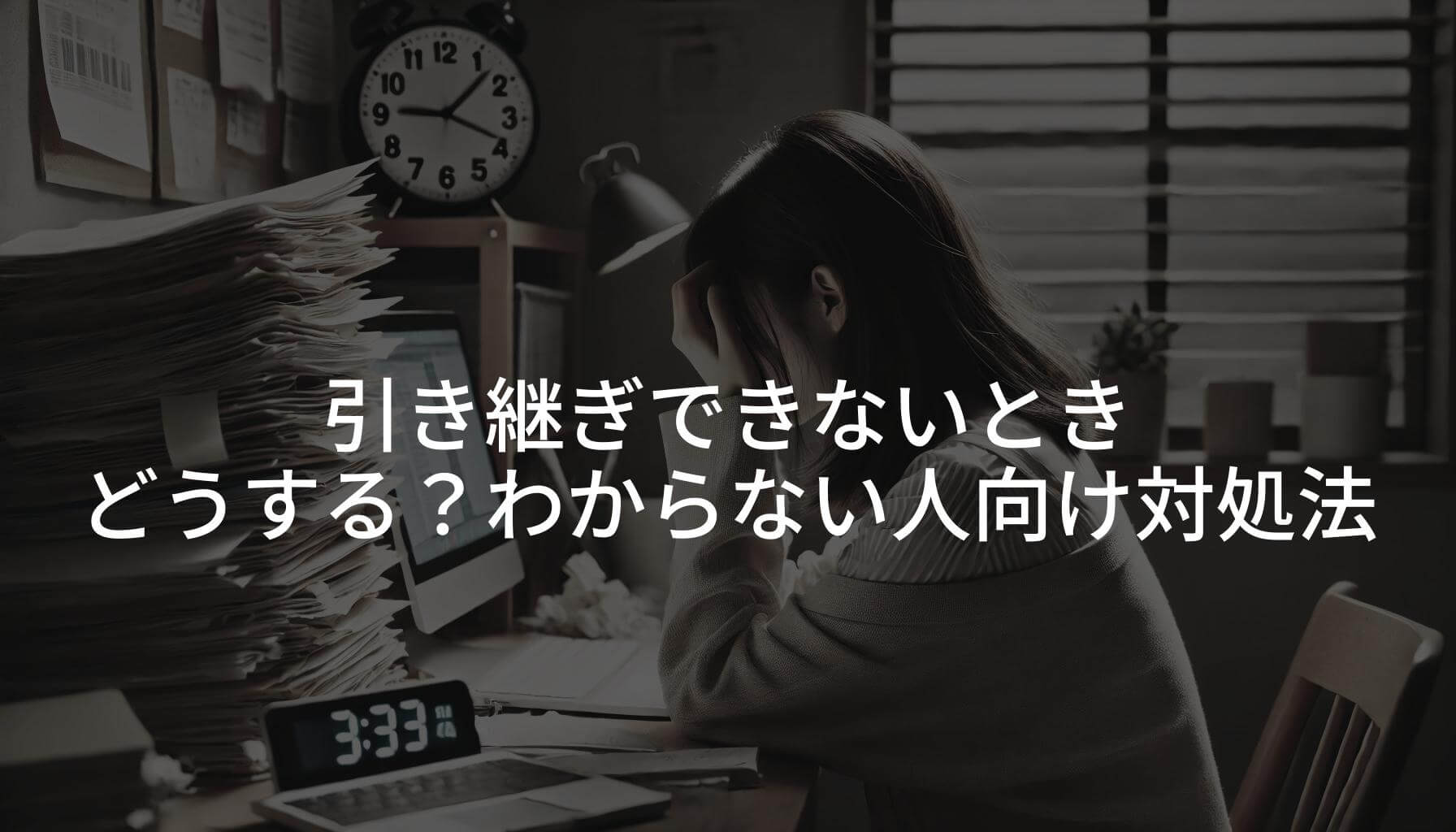この記事で分かること
- 今すぐできる「最低限の引き継ぎ」3ステップ(書き出す→一覧→締切)
- 引き継ぎが難しい時の現実的な選択肢(就業規則確認・簡略化・上司相談)
- もう限界なら?退職~再出発の具体策(給付活用×スキルUP=必勝退職コンボ)
結論:「全部きれいに渡す」は必須ではありません。“相手が走り出せる最低限”に絞ればOK。まずは①業務の棚卸し→②やること一覧→③期日と担当だけ作れば、今日から前に進めます。
次に、退職~再出発までの具体策(必勝退職コンボ)もチェックしておくと安心です。
教える余裕もないし、伝える内容が整理できないと不安になりますよね。
このままうまく引き継げなければ、人間関係まで悪くなるかもしれません。
そこで、今回は引き継ぎ・わからない・辞めたいと感じたときの対処法について紹介します!
引き継ぎがわからない原因は?つまずく人の共通点【先に答え:まず“業務の棚卸し”】
先に行動したい方は、退職~再出発のステップ(必勝退職コンボ)も合わせて確認してください。

引き継ぎがうまくいかない人には、ある共通点があります。
その共通点を知れば、自分の弱点にも気づけるようになります。
まずは、自分の状況と重ねて読んでみてください。
業務の整理ができていない
引き継ぎがうまくいかない人は、まず仕事の流れを整理できていません。
自分でも何をどうしているのか説明できず、伝えることが困難になります。
この問題の背景には、日々の業務を「感覚」で処理している傾向があります。
自分のやり方がマニュアル化されていないことが原因です。
- 頭の中で手順を記憶している
- やることリストがない
- 業務内容の棚卸しをしていない
たとえば、経理の仕事で日々の伝票処理を「手が覚えているから」と続けていたとします。
この場合、他の人にはその手順がわからず、正確に伝えるのが難しくなります。
マニュアルもないため、聞かれても都度答えるしかなく、手間もストレスも増えます。
その結果、引き継ぎが進まないどころか、自分自身も混乱してしまいます。
業務の流れを「見える化」することが、最初の一歩です。
まずは、今やっている仕事を簡単なメモでもいいので書き出してみましょう。
日々やっていることを書くだけで、引き継ぎの下地が作れます。
引き継ぎに困るなら、まずは業務を「書き出す」ことが大事です。
とにかく、自分の仕事を一覧にするのが最初のコツだよ!
教える余裕がない
忙しすぎて、教える時間も気力もない人は多いです。
引き継ぎを後回しにしてしまい、どんどん負担が増えてしまいます。
引き継ぎは、片手間でできるものではありません。
とはいえ、業務が立て込んでいると優先順位が下がりがちです。
- 月末で仕事が山積み
- 人手が足りない
- 教える側も異動や退職間近
たとえば、営業職で引き継ぎが必要なのに、期末目標に追われている状態だとします。
そんなとき、「あとで説明しよう」と後回しになってしまうこともあります。
結果的に、時間切れでほとんど引き継げず、トラブルに発展することもあります。
引き継ぎの準備は、スキマ時間に少しずつでも始めるのが大切です。
朝の10分、昼休憩前の5分だけでもいいのでメモを書き出していきましょう。
完璧を目指すより、「必要なことを簡単に伝える」視点が重要です。
いきなり全部やろうとしないで、少しずつ書き出してね!
質問されるのが苦手
教えるのが苦手な人は、質問されるのも苦手です。
何をどう説明したらいいか分からず、混乱してしまいます。
質問されるとプレッシャーを感じてしまうタイプもいます。
自分の説明が間違っていたらどうしよう…と考えてしまうからです。
- 説明に自信がない
- 話すのが得意でない
- 過去に失敗経験がある
たとえば、派遣社員で業務の説明をしていたときに、質問攻めにあって言葉が詰まったとします。
それ以来、「また質問されたらどうしよう」と考えて苦手意識が強くなります。
結果、引き継ぎの場面で避けたくなる気持ちが強くなってしまいます。
そんなときは、「これはまだ説明中だからあとで答えるね」と伝えるだけでOKです。
全部に完璧に答えようとせず、落ち着いて対応することが大切です。
自信がなくても、「伝えようとする気持ち」があれば十分です。
質問されたら「考える時間もらえる?」で大丈夫だよ!
引き継ぎの経験がない
そもそも、引き継ぎをするのが初めてという人も多いです。
その場合、何から手をつければいいか分からなくて当然です。
過去に教える側の立場を経験していないのが理由です。
人に何かを伝える準備や方法が、イメージしづらいのです。
- 教えられた経験しかない
- メモの作り方が分からない
- 「正解」が分からず不安
たとえば、事務職でずっとアシスタント業務だった場合。
指示を受けて動く立場が多かったので、自分で手順をまとめることに慣れていません。
引き継ぎといっても、具体的に何をどう伝えればいいのか悩んでしまいます。
そのときは、まず「誰に」「どんな順で」「何を」伝えるかを簡単に決めておきましょう。
話す前に「流れ」をざっくり考えるだけで、スムーズに進みやすくなります。
最初は誰でも不安だから、完璧を目指さなくていいよ!
人間関係に気を使いすぎる
引き継ぎの場面で、相手に気を使いすぎてしまう人もいます。
相手がどう思うかを考えすぎて、自分の話ができなくなってしまうのです。
相手に遠慮してしまい、伝えるべきことを控えてしまう傾向があります。
「こんなこと言ったら嫌われるかも」と考えてしまうのが原因です。
- 相手が年上で気を使う
- 態度が冷たいと感じる
- 言い方に自信がない
たとえば、新人の後任に説明しているときに「え、それ本当に必要ですか?」と返されたとします。
その瞬間に気まずくなって、それ以上説明するのをやめてしまう人もいます。
でも、引き継ぎは「情報を渡す」ことが目的なので、気持ちより内容を優先しましょう。
あなたの伝えることが、後でその人を助ける可能性もあります。
相手にどう思われるかより、「役に立つかどうか」が大事です。
言いにくいことも、事実として落ち着いて伝えて大丈夫です。
気を使いすぎて疲れるなら、「書いて渡す」のもアリだよ!
引き継ぎがわからない時は何から?最小コストで済ませる3ステップ
迷ったら「業務を書き出す→一覧にする→締切・担当を付ける」の順でOK。
| 目的 | やること | アウトプット | 時間目安 |
|---|---|---|---|
| 棚卸し | 1日の流れをメモ化 | 手書きメモ/写真で可 | 10~15分 |
| 一覧化 | 定型・不定期を分離 | やることリスト(箇条書き) | 10分 |
| 移行可能化 | 締切・担当・注意だけ追記 | 最小限の引継書(1枚) | 10分 |
- 業務名:
- 頻度:毎日 / 毎週 / 毎月(第◯営業日 等)
- 締切/期日:
- 担当/引継先:
- 注意点(例:締日、システムID、承認者)
退職~再出発の全体像は、必勝退職コンボで先に把握しておくと安心です。

難しく考えすぎず、「伝わるかどうか」を大事にしていきましょう。
ここからは具体的に、一つずつ詳しく解説していきます。
手書きで流れを書く
まず最初に試してほしいのは、紙に業務の流れを書き出すことです。
手書きにすることで、頭の中も整理されていきます。
紙とペンだけで、簡単に「仕事の地図」が作れます。
書くことで、伝える内容の順番や抜けが見えるようになります。
- 1日の流れを時系列で書く
- 業務ごとに区切ってまとめる
- 自分の言葉で説明をつける
たとえば、事務職の方が「午前中はメール対応、午後は請求書処理」と書き出していくとします。
その中で「この処理は〇〇の締め日まで」と書いておくだけでも、相手には伝わりやすくなります。
タイムスケジュールにするだけでも、全体像が見えて安心できます。
それをコピーして渡せば、簡易的なマニュアルになります。
手間もかからず、すぐに取りかかれる方法です。
まずは「書いてみる」だけで全然違うよ!
日報をもとにまとめる
過去に書いた日報やメモがあれば、それをもとに引き継ぎ内容をまとめましょう。
一から書くよりも、すでにある情報を使った方がスムーズです。
日報は、自分の行動記録としてとても使えます。
忘れがちな細かい作業や時期的な業務も思い出せます。
- 1週間分だけでも見返す
- 定型業務を抜き出す
- 不定期業務は補足メモをつける
たとえば、営業アシスタントの方が週1で発注対応をしているとします。
それが日報に「発注処理、取引先Aに確認」と書いてあれば、それを引き継ぎ資料に転記するだけです。
頻度や時間帯、注意点なども思い出せるので、効率的にまとめられます。
過去の記録は「第二の脳」なので、フル活用しましょう。
ゼロから作るより、日報を活かす方が楽だよ!
口頭で伝える前に練習する
口頭で伝えるのが不安な人は、事前に練習しておきましょう。
話す内容を整理するだけで、伝え方がぐっと変わります。
「話す練習」は引き継ぎ成功のカギになります。
声に出して説明することで、自分でも内容を再確認できます。
- 話す順番をメモにする
- スマホで録音して聞き返す
- 同僚に聞いてもらう
たとえば、パート勤務の方が「レジ締めの手順」を新人に伝えるとします。
前日に一度、自分で流れを読んでみて、詰まりそうな部分を確認します。
その場で焦らず話すために、ポイントをメモしておけば安心です。
練習することで余裕ができ、相手にも伝わりやすくなります。
ぶっつけ本番でなく、「少しだけ準備する」だけで全然違います。
心の準備ができてると、言葉も自然に出てくるよ!
引き継ぎなしでも辞めたい人の選択肢

どうしても引き継ぎが難しい、またはしたくないという場合もあります。
そのようなときに選べる現実的な方法を紹介します。
無理をせず、自分を守るための選択も大切です。
ここからは、引き継ぎが難しいと感じたときに取れる対処法を見ていきましょう。
就業規則を確認する
引き継ぎをするかどうかは、まず就業規則で確認しましょう。
会社によっては、明確に定めている場合もあります。
規則に「引き継ぎ義務あり」と書かれているかどうかがポイントです。
記載がない場合は、最低限の対応で済ませられる可能性もあります。
- 退職届提出後の業務内容
- 引き継ぎ義務の有無
- 退職までの日数
たとえば、派遣社員の契約書には「契約終了後の引き継ぎは任意」と記載されているケースもあります。
この場合、無理に詳細な引き継ぎを求められることは少なくなります。
自分の義務と会社のルールを照らし合わせて判断しましょう。
就業規則が不明な場合は、人事や総務に確認するのが確実です。
ルールを知ることが、自分を守る第一歩です。
まずは会社のルールをチェックしておこうね!
なお、引き継ぎの扱いは会社規程や契約条件で異なります。最新の制度・手続きは
厚生労働省の一次情報
も確認しつつ、社内の就業規則・担当部署に照会しましょう。
上司に事情を伝える
引き継ぎが難しい理由がある場合は、必ず上司に直接伝えましょう。
黙っていると、責任逃れだと思われてしまうリスクがあります。
正直に状況を話すことが信頼につながります。
無理に抱え込まず、相談することで対応の幅も広がります。
- 体調不良で引き継ぎが困難
- 心の余裕がない
- 業務量が多すぎる
たとえば、家庭の事情で早退が多くなっている状態の中での引き継ぎ。
それを伝えずに進めようとすると、仕事も引き継ぎも中途半端になってしまいます。
上司に状況を共有するだけで、業務調整やサポートの提案が受けられることもあります。
我慢せずに、少しだけ勇気を出して相談してみてください。
伝えるだけで、気持ちもラクになりますよ。
言いづらくても、まずは話してみると動き出すよ!
内容を簡略化して伝える
全部を詳しく引き継ぐ必要はありません。
大事なポイントだけを「かんたんに」まとめて伝える方法もあります。
最低限で伝われば、それで十分です。
相手が必要な情報を後から補足できるようにしておくのがコツです。
- やることの一覧だけ作成
- 日付・担当者だけ記載
- 補足は口頭でOK
たとえば、事務パートで「伝票入力・在庫チェック・月末処理」の3つを担当していた場合。
それを箇条書きで書き出し、納期や締切だけメモすれば充分伝わります。
細かい注意点は、後で聞かれたときに答えれば大丈夫です。
完璧じゃなくても、「最低限」で回る仕組みを意識しましょう。
ラクに伝える方法を選んでOKだよ!
最低限だけ文書にまとめる
紙1枚でも構わないので、最低限の情報をメモにして渡しましょう。
それだけで、引き継ぎが「形」になります。
口頭よりも、紙に書いてある方が残ります。
あとで見返せるので、相手の安心感にもつながります。
- 1枚にまとめる
- 業務名と担当だけ書く
- 重要な日付・締切を記載
たとえば、派遣社員で週に1度の発注作業をしている場合。
「木曜13時に〇〇社に発注」と1文だけでもメモにして渡すと役立ちます。
引き継ぎが十分にできない状況でも、文書にすることで「責任感」を示せます。
忙しくても、短時間でできる対応です。
完璧じゃなくても、文書にしておくと安心だよ!
まとめ|引き継ぎがわからない→辞めたい時は「最低限の引き継ぎ」で十分
- 全部きれいに渡す必要はない。最小構成(棚卸し→一覧→締切)でOK
- 難しい時は、就業規則の確認・上司相談・簡略化で現実対応
- 退職後が不安なら、必勝退職コンボで再出発プランを具体化