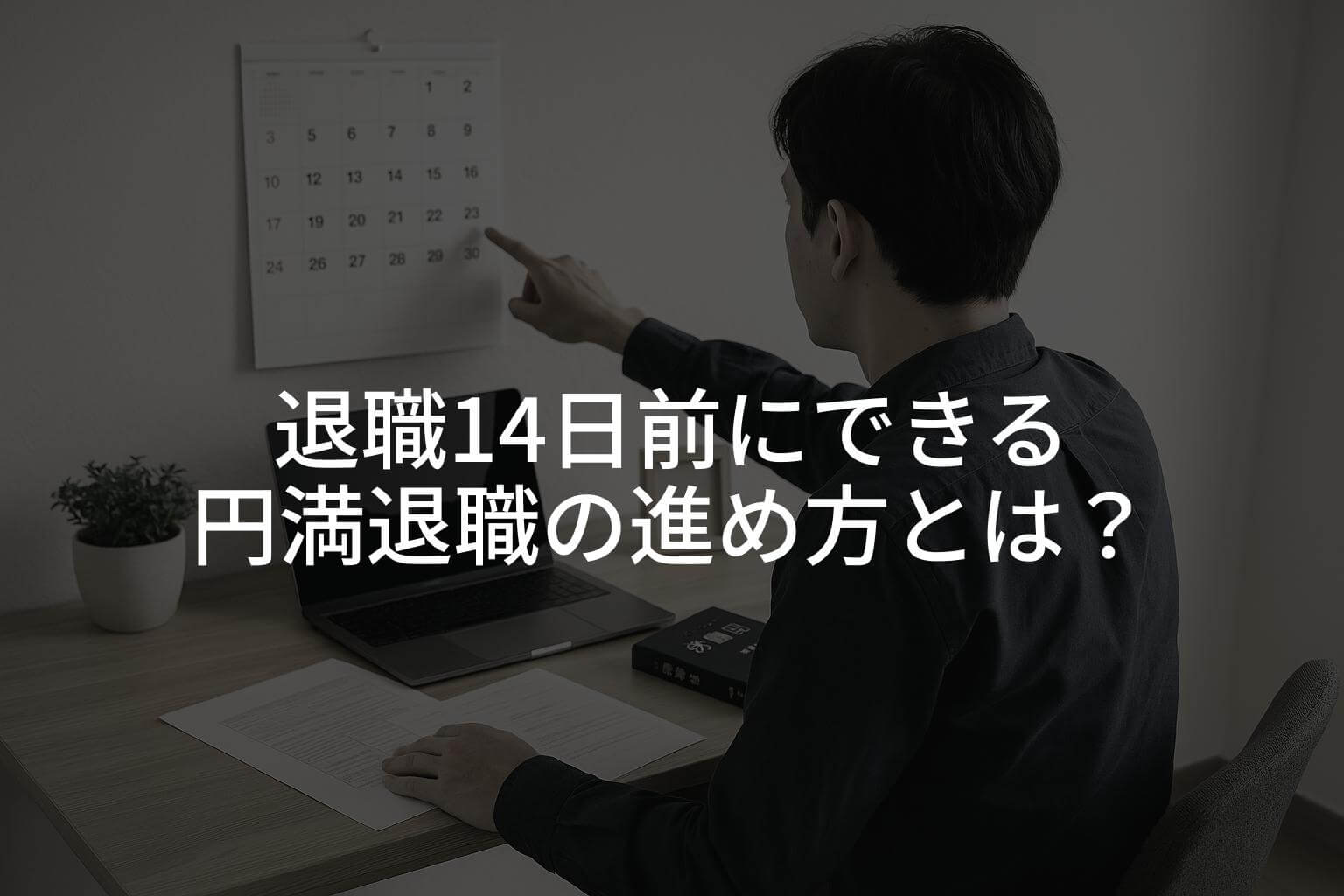「規則違反だ!」って言われたらどうしようって心配だよね。
放っておくと、辞めたあともゴタゴタするかもしれません。
そこで、今回は退職14日前にできる円満退職の進め方とは?について紹介します!
この記事で分かること!
- 就業規則との違い
- 必要な手続き一覧
- 円満退職のコツ
退職14日前とは何かをやさしく解説

退職14日前とは、民法に基づき自由に退職できる最短期間を意味します。
つまり、退職を伝えるのが14日前であれば、会社の了承がなくても法律上は退職が可能です。
この14日ルールには、会社員が守るべき就業規則と違いがあるため、誤解が生じやすいです。
法律と就業規則の関係を理解すれば、自信を持って退職手続きが進められます。
では次に、14日前の退職に関する具体的なポイントを見ていきましょう。
民法で定められた最低期間
民法では、退職の申し出から14日経てば、雇用関係は終了します。
このルールは正社員だけでなく、契約社員や派遣社員にも原則的に適用されます。
つまり、「申し出から2週間」で会社を辞められる根拠があるということです。
- 民法627条が根拠
- 雇用期間の定めがない場合が対象
- 使用者の合意は不要
- 14日後には自動的に契約終了
たとえば、4月1日に退職届を出した場合、4月15日には退職が成立します。
会社から「1か月前に言わないとダメ」と言われても、民法上は無効な主張となることもあります。
ただし、後ほど紹介する就業規則や契約内容により、例外も存在します。
まずは「14日ルール」が民法で保障された最低ラインであることを理解しましょう。
自分で判断できるようになると、会社とのやり取りもスムーズになります。

就業規則との違い
就業規則は会社ごとのルールであり、民法とは別に存在します。
たとえば、「退職は1か月前に申告」と就業規則に記載されている企業もあります。
しかし、民法627条は強行法規ではなく、当事者間で合意がある場合は就業規則が優先されることもあります。
- 就業規則は社内ルール
- 法的拘束力は状況次第
- 入社時の同意があれば優先
- 書面や契約書で要確認
たとえば、雇用契約書に「退職は30日前まで」と書かれていれば、それが有効となるケースもあります。
しかし、実務では多くの企業が「2週間で退職できる」ことを認めています。
会社によっては引き留めのために「規則違反」と伝える場合もあるため、冷静に対処が必要です。
円満に退職するためには、就業規則の内容を事前に確認しておくことが大切です。
就業規則と民法の違いを知ると、根拠を持って行動できます。

よくある間違い
退職14日前のルールを誤解して、トラブルになるケースが多くあります。
法律上は可能でも、会社との関係を悪化させてしまう可能性もあります。
知識不足や準備不足によって、損をしたり退職後に問題が残ることもあります。
- 就業規則を確認せずに退職
- 急な退職で引き継ぎが不十分
- 感情的な退職宣言
- 退職届を出さずに辞める
たとえば、感情的になって「もう辞めます!」とその場で言ってしまうと、関係が悪化します。
また、引き継ぎをせずに辞めると、後任者や同僚に迷惑がかかり、信用を失うこともあります。
会社に書類を出さずに無断退職してしまうと、離職票が発行されずにトラブルになります。
退職は法的に可能でも、現場対応は丁寧にする必要があります。
円満退職を目指すなら、段取りと礼儀を意識することが大切です。

退職14日前に必要な3つの手続き

退職をスムーズに進めるには、最低限やっておくべき3つの手続きがあります。
14日前という短い期間の中で、どれだけ準備できるかが重要です。
どれも難しくありませんが、段取りよく進めることでトラブルを避けられます。
それぞれの手続きについて、くわしく見ていきましょう。
退職届を出す
退職を正式に伝えるには、退職届の提出が必要です。
これが退職の意思を会社に明確に伝える第一歩になります。
提出のタイミングが遅れると、14日前ルールが適用できません。
- 必ず書面で提出する
- 提出日は記録に残る形で
- 直属の上司に提出する
- 会社の就業規則も確認
たとえば、退職届を口頭だけで済ませた場合、証拠が残らずトラブルの原因になります。
紙で提出し、コピーを手元に残しておくと安心です。
また、LINEやチャットでの報告はビジネスマナーとして適切ではないと判断されがちです。
直属の上司に、事前に口頭で伝えてから提出するのが丁寧です。
正式な書類として残すことで、法律的にもスムーズに退職できます。

引き継ぎの準備
次に大切なのが、業務の引き継ぎです。
自分がいなくなった後も業務が回るようにしておくのは社会人としてのマナーです。
引き継ぎが不十分だと、後任や同僚が困り、評価が下がることもあります。
- 業務内容を整理する
- 必要な資料をまとめる
- マニュアルを作成する
- 担当者に直接説明する
たとえば、営業職の方であれば、顧客とのやり取り履歴や納期などを文書で残すと後任が安心です。
IT職の方であれば、システムの設定方法やパスワード情報を安全に引き継ぐことが求められます。
事務職であれば、日々のルーティンや月次処理の流れを手順書にしておくと効果的です。
どの職種でも、「自分しか知らない情報」があるはずです。
それを残すことで、感謝され、気持ちよく送り出してもらえます。

会社との話し合い
退職の意思を伝えたら、会社との話し合いも大切です。
一方的に辞めるより、誠意を持って話すことで円満退職につながります。
とくに退職日や引き継ぎのスケジュールは、すり合わせが必要です。
- 退職理由を簡潔に伝える
- 退職日を明確に伝える
- 引き継ぎ計画を伝える
- 感謝の気持ちを伝える
たとえば、「一身上の都合で退職します」と伝えるだけで、角が立たず穏便です。
退職理由を詳しく話す必要はありませんが、前向きな表現にすると印象が良くなります。
また、退職日は法律上14日でも、会社の都合を考慮し調整するのもマナーです。
業務の迷惑にならない姿勢が、信頼と評価につながります。
良い印象のまま職場を去れば、退職後も関係を保ちやすくなります。

退職14日前に出すべき書類と出し方

退職時にはいくつかの書類が必要になります。
なかでも「退職届」は必須で、書き方や提出方法にもルールがあります。
書類の準備をしっかりしておけば、会社側とのやり取りもスムーズです。
それでは、ひとつずつ確認していきましょう。
退職届の書き方
退職届には決まった書式がありますが、基本はシンプルでOKです。
読みやすく、正しい形式で書くことが信頼感につながります。
内容にミスがあると受理されず、退職日が遅れるおそれもあります。
- タイトルは「退職届」
- 書き出しは「私事、」
- 理由は「一身上の都合」
- 日付と署名を忘れずに
例として、以下のように書くと問題ありません。
退職届 私事ですが、 このたび一身上の都合により、令和○年○月○日をもって 退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。 令和○年○月○日 ○○部 ○○課 氏名:山田 太郎(自筆で署名)
手書きが基本ですが、ワードなどで作成し署名だけ手書きでも構いません。
丁寧な言葉とレイアウトで、気持ちを込めて書くと印象が良くなります。

提出のタイミング
退職届の提出は、退職希望日の14日前が基本です。
このタイミングを守ることで、民法上の退職ルールに合致します。
逆に提出が遅れると、退職日が後ろ倒しになる可能性もあります。
- 最低でも14日前には提出
- 可能なら1か月前が理想
- 繁忙期を避ける配慮も大切
- 上司に相談後すぐ提出
たとえば、退職希望日が5月15日なら、5月1日までには提出する必要があります。
余裕を持って準備することで、引き継ぎや社内調整がスムーズになります。
企業文化によっては、1か月前の提出がマナーとされている場合もあります。
感情で動かず、冷静に準備してから提出しましょう。

メールか手渡しか
退職届の提出方法には、いくつかの選択肢があります。
ただし、会社や上司との関係性によって最適な方法は異なります。
大切なのは、「礼儀ある形」で提出することです。
- 基本は直接手渡し
- 出社が難しいなら郵送
- メール提出は非常手段
- 証拠を残すことも大事
たとえば、リモート勤務で直接渡せない場合は、郵送に加えてメール連絡も行うと丁寧です。
手渡しの場合は、封筒に入れて、上司に口頭で伝えたうえで渡します。
郵送する際は、配達記録が残る「簡易書留」などで送るのが安心です。
メールのみで提出すると、受理されない可能性があるため注意が必要です。

退職14日前に確認すべき3つのルール

退職時には、法律上確認しておくべきルールがいくつかあります。
知らないまま辞めてしまうと、損をしたり、後悔することになりかねません。
ここでは、退職前にチェックしておきたい3つのポイントを解説していきます。
有給休暇の取り方
退職前でも、有給休暇は法律上すべて取得可能です。
「退職日までに消化しないと無効」と勘違いしている方も多いです。
希望通り取得するには、早めの申請と上司との調整がカギになります。
- 有給は買い取りではなく取得が基本
- 退職日までに計画的に使う
- 就業規則を確認する
- 申請は書面で残す
たとえば、14日間の有給が残っていれば、出社せずに退職日を迎えることも可能です。
このとき「最終出社日」と「退職日」は異なるので、注意が必要です。
会社によっては、時季変更権を主張して休暇を拒否してくることもあります。
しかし退職前の有給に対しては、原則として時季変更権は使えません。
争いを避けるためには、あらかじめスケジュールを提示し、協力を仰ぐことが大切です。

社会保険の手続き
退職すると、健康保険や年金などの社会保険も手続きが必要になります。
放置してしまうと無保険状態になり、後で手続きが面倒になります。
健康保険は以下の3つのどれかを選ぶ必要があります。
- 国民健康保険に加入
- 家族の扶養に入る
- 任意継続で会社の保険を延長
たとえば、すぐに転職しない場合は、国民健康保険に加入するのが一般的です。
配偶者の会社の扶養に入ることで、保険料の負担を減らせる場合もあります。
また、退職後2年以内であれば、任意継続という選択肢もあります。
年金についても、厚生年金から国民年金へ切り替えが必要です。

トラブルにならない言い方
退職の意思を伝えるとき、伝え方を間違えると関係がこじれる原因になります。
角が立たないように、冷静で丁寧な言葉を選ぶことが大切です。
とくに感情的な言い方や責任転嫁はNGです。
- 「一身上の都合」でまとめる
- 会社や上司を責めない
- 前向きな理由を選ぶ
- お礼の言葉を添える
たとえば、「ステップアップを考えて退職を決めました」という言い方であれば、相手も納得しやすいです。
「この会社では将来が見えない」といった批判的な言い方は避けましょう。
お世話になったことへの感謝の言葉を伝えることで、円満に進められます。
話し合いの場でも、あくまで冷静に、落ち着いて話す姿勢が求められます。

まとめ 退職14日前にやるべき準備とは?
今回は、退職14日前にやるべき退職準備と手続きについて紹介しました。
この記事のポイント!
- 退職届の正しい出し方
- 民法と就業規則の理解
- トラブルを防ぐ言い方
退職する前に知っておくべき法律の決まりや、就業規則の確認ポイントを解説しました。
トラブルにならないように退職届の書き方や提出方法も詳しく紹介しました。

スムーズな退職のために、できることから始めてみてください。