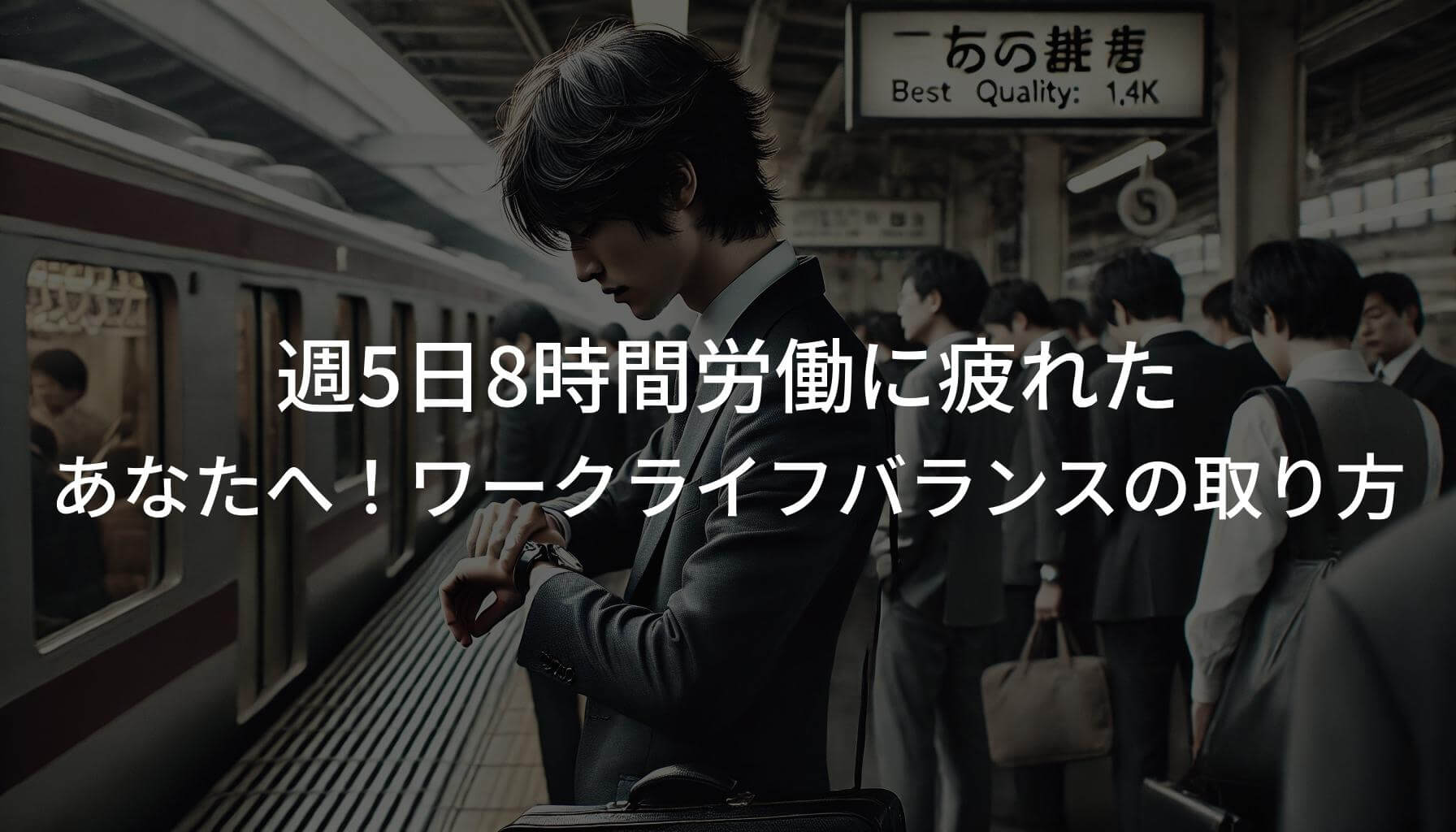家と仕事の往復だけの毎日に心がすりへってしまいますね。
このままじゃ心もからだももたないかもしれません。
週5日8時間労働がおかしいと感じるあなたへ、労働の歴史と見直し方について紹介します!
この記事で分かること!
- 週5日8時間労働の歴史がわかる
- なぜ今も続いているのか知れる
- 労働時間を変えるヒントがある
週5日8時間労働がおかしいと感じた人の本音
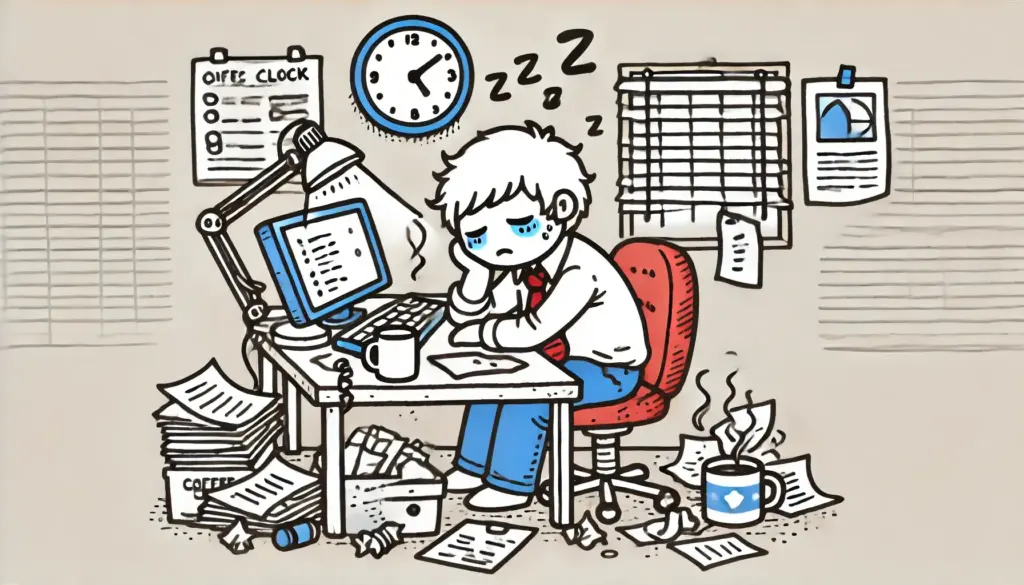
週5日8時間労働で働くのは、あたりまえじゃないと感じる人がふえています。
ほんとうにこの働き方でよいのか、疑問をもつのは自然なことです。
こんな思いを持つ人は、じっさいに日々の生活で「時間が足りない」と感じています。
まずは、多くの人が感じているリアルな声から見ていきましょう。
仕事中心の生活に躊躇(ちゅうちょ)
生活が仕事ばかりになるのは、おかしいと感じている人が多いです。
とくに家族や自分の時間を大切にしたい人にとって、バランスの悪い働き方はストレスになります。
「働くために生きてる気がする」という声もあります。
- 家族と過ごす時間がない
- 帰宅しても家事や育児でバタバタ
- 趣味や自分の時間が取れない
- 仕事のことばかり考えてしまう
たとえば、小さな子どもがいるパパの場合。
毎朝7時には家を出て、帰宅は20時すぎ。
子どもが寝る時間とほとんどかぶってしまい、顔を見られるのは週末だけ。
「なんのために働いているのかわからなくなる」と感じることも。
こんな毎日にちゅうちょを感じるのは、あなただけではありません。
まずは自分の気持ちに気づくことが大切です。
無理にがまんせず、バランスを考えることが第一歩。

時間が足りないと感じる日々
「1日24時間じゃ足りない」と思う人はとても多いです。
とくに働きながら家事や子育てをこなす人にとっては、毎日が時間とのたたかいです。
気づいたら寝る時間で、自分のことがなにもできないという声も少なくありません。
- 朝は出社の準備でバタバタ
- 昼は会議やタスクに追われる
- 帰宅後はすぐに夕食や片づけ
- 夜は疲れて何もやる気が出ない
たとえば、共働きの30代女性の場合。
朝6時に起きて弁当をつくり、子どもを保育園に送ってから出社。
仕事を終えたら保育園へお迎え、夕食の準備、洗濯と片づけ。
そのころには、もう夜10時近く。
やっと一息つけたと思ったら、また明日の準備で終わってしまう。
こうした生活が続くと、「何のために毎日を過ごしているんだろう」と感じやすくなります。
自分の時間をつくることは、こころの余裕にもつながります。
まずは、時間の使い方を見直すところからはじめましょう。

身体と心のつかれ
働きすぎによる「つかれ」が、からだだけでなく心にもあらわれます。
とくに休めない日がつづくと、いつのまにか元気がなくなってしまいます。
がんばっているのに、しんどいと感じることは、あなたが悪いわけではありません。
- 朝起きるのがつらい
- 何をしても楽しく感じない
- イライラしやすくなった
- 体調をくずしやすくなった
たとえば、フルタイムで働く40代の男性会社員。
毎日定時をすぎても終わらない仕事を家に持ち帰り、深夜までパソコン作業。
週末は疲れて寝てばかりで、出かける元気も出ない。
気づけば「会社と家の往復だけ」の生活になっていました。
そんなときに、めまいや頭痛が頻繁に起きるようになり、病院で「過労」と診断されました。
こうした体のサインは、心からのSOSかもしれません。
大切なのは、無理せず、休むことをゆるすこと。

週5日8時間労働はいつからつづく?

いまの「週5日×8時間」の働き方は、じつは100年以上前から続いています。
わたしたちが当たり前と思っているこのスタイルには、長い歴史があります。
この背景を知ることで、「なぜ今もこの形なのか?」というモヤモヤが少し晴れていきます。
それではまず、週5日8時間労働がどうやって始まったのかを見ていきましょう。
歴史と発しょう
週5日8時間労働のはじまりは、19世紀の工場労働にさかのぼります。
当時の労働者は1日12時間以上働かされることもあり、子どもまで過酷な環境で働いていました。
この状態に「人間らしい生活を」と声を上げたのが、労働時間短縮のきっかけです。
- イギリスの工場法(1833年)で子どもの労働時間を制限
- アメリカでは労働運動で「1日8時間労働」を要求
- フォード社が1926年に週5日勤務制を導入
- 日本では戦後に8時間労働が本格的に定着
たとえば、アメリカの自動車会社「フォード社」では、生産性を上げるために、あえて週5日制を取り入れました。
この改革により、社員の満足度が上がり、売上も伸びたそうです。
その後、この制度は世界中に広まりました。
日本では戦後、労働基準法の制定により、法的にも8時間労働が守られるようになりました。
でも、それは当時の「工場で働く人」が中心だった時代の話。
現代のわたしたちの働き方には、もっと合ったスタイルがあるかもしれません。

なぜこの形が定着したのか
週5日8時間という働き方は、企業側にとって「管理しやすい形」だったからです。
また、国の制度や教育とも相性がよく、長いあいだ変わらず続いてきました。
「みんなが同じ時間に働く」ことで、社会全体がまわるようにできていたという背景があります。
- 企業がシフトや給与を計算しやすい
- 学校の時間割と合わせやすい
- 通勤時間がある前提で動いている
- 社会全体がこのリズムに慣れている
たとえば、朝9時に出社し夕方6時に退社するスタイル。
この時間に合わせて電車のダイヤが決まり、子どもの学校や保育園の時間も同じように組まれます。
社会全体がこの働き方を「前提」として動いてきたのです。
だから、たとえ不便を感じても「それが普通」として受け入れられてきました。
でも、テレワークやフレックスなど、働き方が多様になった今。
「本当にこのスタイルじゃないとダメなのか?」と問い直す人がふえてきました。
変えるのがむずかしいのは、変わらないことに慣れてしまったからかもしれません。

今とのくらべかた
100年前と今では、働く環境も仕事の内容もまったくちがいます。
だからこそ「昔のままの働き方」が合わないと感じるのは自然なことです。
今の時代には、もっと柔軟で自由な働き方が求められています。
- ネットでいつでも仕事ができる
- AIやツールで効率化が進んでいる
- 成果重視の働き方が増えている
- 場所にしばられない時代になった
たとえば、IT企業で働く20代のエンジニア。
毎日オフィスに通う必要はなく、自宅やカフェでも仕事ができます。
タスク管理やチャットツールがあれば、上司や同僚との連携もスムーズ。
9時から17時にしばられる必要がないので、自分のリズムで働けます。
こうした「成果重視」の仕事では、時間ではなくアウトプットが評価されます。
つまり、短い時間で成果を出せれば、早く終わってもいいのです。
こういう働き方ができる職種がふえている今、昔の型にこだわる理由はなくなってきました。

働きすぎをへらすアイデア3選
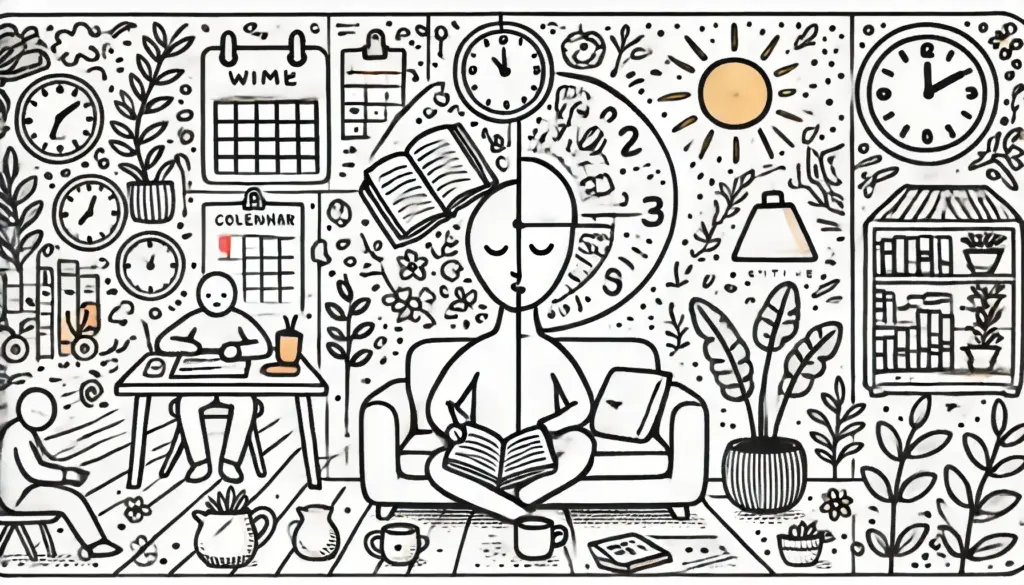
「なんだか働きすぎてるな…」と感じたら、すぐに生活を見なおすサインです。
無理をつづけていると、からだにも心にも負担がかかってしまいます。
ここでは、今すぐできる「働きすぎをへらす3つの方法」を紹介します。
まずは、一日の時間の使い方から見直してみましょう。
毎日のスケジュールを見なおす
まずは、1日の流れを見える化して、時間の使い方を整理しましょう。
なんとなく過ごしている時間を見つけることで、ムリやムダをへらせます。
「本当に必要なこと」に時間を使えるようにするのがポイントです。
- 朝と夜に使っている時間を書き出す
- スマホやテレビの時間をチェック
- ついダラダラしている時間に気づく
- スキマ時間にできることを考える
たとえば、毎朝スマホを見ながら30分ぼーっとしていた人。
その時間を使って「今日やること」を3つだけ書き出すようにしたそうです。
それだけで1日の流れがすっきりして、時間に追われる感じが減ったといいます。
また、夕食後のだらだらタイムを「読書かストレッチの時間」と決めるのもおすすめ。
「何にどれだけ時間を使っているか」を知ることは、生活をととのえる第一歩です。
まずは手帳やスマホのメモで、ざっくり記録してみてください。

集中できる時間をつくる
集中して取り組める時間をつくると、作業効率がぐんと上がります。
その結果、仕事にかかる時間をへらして、自由な時間を生み出せます。
ダラダラ続けるより、短く集中する方がずっと効果的です。
- 作業ごとにタイマーを使う
- 集中しやすい時間帯を知る
- 朝に頭を使う仕事を入れる
- 通知をオフにして環境を整える
たとえば、午前中の1時間だけ「スマホ・通知オフ」で作業するルールをつくった人。
その時間に大事な資料づくりをまとめて済ませたところ、午後がとても楽になったそうです。
夜にぼんやり作業するより、朝の短い時間で集中した方が効率もアップします。
「やることをしぼって、時間を区切る」のがコツです。
ポモドーロ・テクニックなども、簡単でおすすめです。
集中時間を味方につければ、自然と残業もへっていきますよ。

休む時間をふやす
しっかり休むことは、働くことと同じくらい大事です。
むしろ、よく休める人の方が、よく働けるともいえます。
「休む=悪いこと」と思わないことが、働きすぎを防ぐ第一歩です。
- 昼休みは席を離れて過ごす
- 10分だけ目をとじる習慣
- 週に1日は完全オフにする
- 定期的に有休を取る
たとえば、毎日10分だけ「昼寝タイム」をとるようにした会社員。
はじめは少しそわそわしていたけれど、数日後には午後の集中力がぐっと上がったと感じたそうです。
また、「休む日」をカレンダーにあらかじめ入れておくことで、罪悪感なく休めるようになったという声も。
しっかり休んだ方が、結果としてパフォーマンスも上がります。
「がんばらない日」をつくるのも、立派な自己管理です。
週末にふとんでゴロゴロしても、それはちゃんとした回復の時間ですよ。

自由に働ける方法を考えよう

今の働き方にしばられすぎず、自分に合った働き方を考える時代です。
「こうあるべき」より、「こうありたい」を大事にする人がふえています。
ここでは、いま注目されている「自由な働き方」について、わかりやすく紹介します。
まずは、今すぐにでも取り入れやすい「在宅・リモートワーク」から見てみましょう。
在宅やリモートを取り入れる
通勤のない働き方は、それだけでストレスがぐんと減ります。
さらに、自分のペースで働けることが、心にも大きなゆとりをもたらします。
在宅やリモートは、ワークライフバランスを整える一番の近道です。
- 通勤時間がゼロになる
- 服装や環境にしばられない
- 静かな場所で集中できる
- 休憩も自分のタイミングでOK
たとえば、週に3日だけリモート勤務を選べる会社で働く30代男性。
通勤のストレスがなくなったことで、朝の時間に余裕ができ、軽い運動を習慣にできました。
また、昼休みに買い物や家事をすませることができ、平日でも生活のゆとりが持てたそうです。
最初は不安もあったけれど、1か月たつころには仕事の成果も上がってきたとのこと。
自分のペースを大切にする働き方が、気持ちにも良い影響を与えてくれます。
「通勤がないだけで、毎日がこんなに楽になるんだ」と感じる人は多いですよ。

週4日勤務のメリット
週4日勤務は、最近とくに注目されている新しい働き方です。
「働く日を1日減らす」だけで、生活にも気持ちにも大きな変化が生まれます。
休みが1日ふえることで、人生のバランスが取りやすくなります。
- 週3日の自由時間ができる
- 疲れがたまりにくくなる
- 副業や学びに使える
- 生活にメリハリが出る
たとえば、実験的に週4日勤務を導入した企業では、社員の満足度が大きくアップしました。
ある女性社員は、「休みが1日増えただけで、こんなに気持ちに余裕ができるなんて」と驚いたそうです。
家事や通院、自己投資の時間を週に1日持てることで、生活のリズムが整ったとも話していました。
「1日はたった24時間」ですが、休みが1日増えると気力も変わってきます。
仕事のパフォーマンスも上がり、会社にとってもプラスになるという報告もあります。
週4日勤務がもっと広がれば、社会全体の働き方も変わっていきそうですね。

フリーランスという選び方
「もっと自由に働きたい」と考えたとき、フリーランスは大きな選択肢になります。
時間や場所にしばられず、自分らしい働き方ができるからです。
フリーランスは「じぶんの力で働く」新しい生き方です。
- 働く時間を自分で決められる
- 好きな場所で仕事ができる
- 得意を活かして収入を得られる
- がんばり次第で収入アップも可能
たとえば、会社員をやめてフリーのデザイナーになった30代男性。
最初は仕事が安定せず不安もあったけれど、少しずつリピートの仕事が増え、今では会社員時代より収入も上がったそうです。
自分でスケジュールを決められるので、午前中だけ働いて午後は自由に過ごす日も。
仕事のやりがいもあり、「生活そのものを自分でつくる感覚」があると話していました。
もちろんリスクもありますが、その分得られる自由も大きいです。
まずは副業からスタートして、少しずつチャレンジしていくのもおすすめです。

まとめ|週58時間働くのはおかしい?その理由とこれから
週58時間 おかしいと感じた理由とこれからの選び方について紹介しました。
■ この記事のポイント!
- 昔の働き方とのちがい
- やりすぎな労働のしんどさ
- 変えていくための方法
今の働き方に「おかしい」と感じるのは当然でした。その理由を歴史からひもとき、少しずつ変えていくための方法をまとめました。自分の時間を守ることの大切さも、あらためて伝えました。

毎日をもっと自分らしくするヒントを、生活に取り入れてみてください。