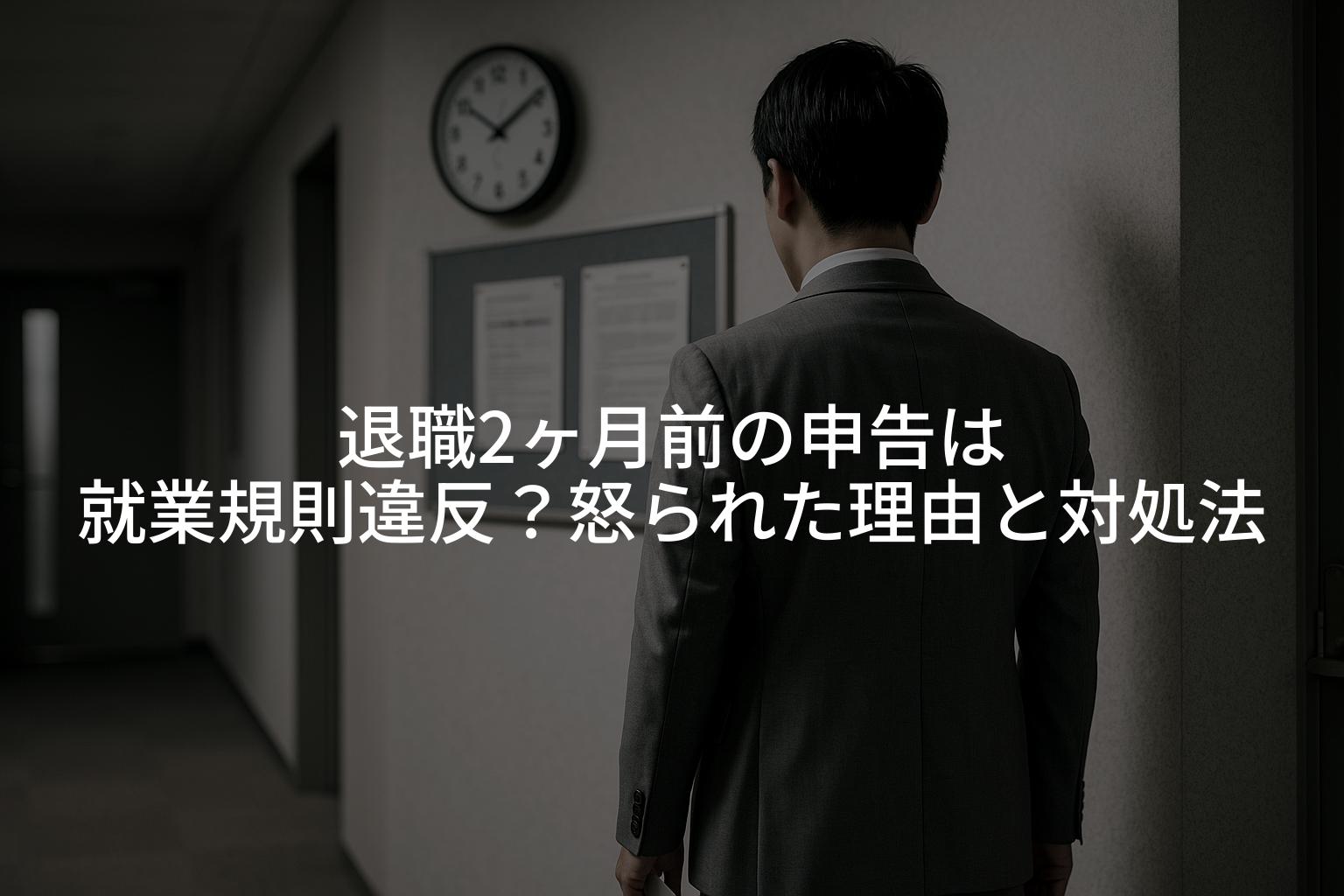でも、上司に怒られてしまうと不安になりますよね。
ルールを知らないと損をするかもしれません。
そこで、今回は退職 2ヶ月前 就業規則 にまつわる誤解と正しい対処法について紹介します!
この記事で分かること!
- 法律とのちがいが分かる
- 上司の本音が見えてくる
- 冷静に対処する方法
退職を2ヶ月前に伝えるのは就業規則違反?

退職を2ヶ月前に伝えたのに怒られたなら、就業規則の確認が必要です。
実は就業規則と法律には差があり、勘違いしやすい点でもあります。
まずは、退職意思の伝え方と会社との関係性について見ていきましょう。
怒られた背景には、意外な理由が隠れていることもあります。
退職の一般的な伝え方
退職の意思は、原則として「直属の上司」に伝えるのが基本です。
人事や同僚に先に話すと、トラブルの元になることがあります。
誠実な伝え方が円満退職への第一歩になります。
- 直属の上司に口頭で伝える
- 退職理由を簡潔に説明
- 希望日を明確に伝える
- 感謝の気持ちを伝える
たとえば、技術職で5年勤めたAさんの場合です。
ある日、家庭の都合で退職を決め、2ヶ月前に上司へ伝えました。
しかし、上司は「急すぎる」と強く反応し、不満を口にしました。
それでもAさんは、引き継ぎの計画と感謝の意を丁寧に伝え続けました。
結果的に、円満に退職することができたのです。
退職の伝え方は、タイミングよりも「丁寧さ」が重要です。

会社ごとの決まりとは
会社には「就業規則」によって退職申告の期限が定められています。
多くの企業では「1ヶ月以上前」と記載されています。
就業規則は会社独自のルールです。
- 就業規則は各社が独自に定める
- 法より厳しい場合もある
- 社内での優先度は高い
- 内容は入社時に同意済み
たとえば、サービス業のBさんは1ヶ月前申告が就業規則でした。
ところがBさんは、忙しい時期を避けて2ヶ月前に申告。
上司は「なぜもっと早く相談しなかったのか」と責めました。
事前に相談のタイミングを見計らうべきだったと後悔しました。
就業規則の確認と、上司との関係性が重要だと気づいたのです。

伝えるタイミングの考え方
退職の伝え方は「会社の状況」に応じてタイミングを選ぶべきです。
法律的には2週間前で十分ですが、職場では早い方が安心されます。
配慮の気持ちが信頼を高める鍵です。
- 繁忙期を避ける
- プロジェクト終了後を狙う
- 月初・月末に合わせる
- 直属の上司の予定も考慮
事務職のCさんは、異動直後のタイミングで退職を決めました。
ちょうど繁忙期にあたり、チームに大きな負担がかかる時期でした。
結果、上司から「今じゃない」と叱責され、関係が悪化してしまいました。
もし1ヶ月待っていれば、穏やかに進められたかもしれません。
退職の伝え方は、タイミングと空気を読むことが大事です。

就業規則と法律のちがいを知ろう

退職の申告について、就業規則と法律には明確な違いがあります。
この違いを理解しておかないと、無用なトラブルを招いてしまいます。
まずは労働基準法で定められている、退職の基本的なルールを確認しましょう。
会社のルールと混同しないことが、円満退職への第一歩です。
労働基準法の退職ルール
労働基準法では「退職の意思表示は2週間前でよい」と定められています。
これは正社員・契約社員に関係なく適用される基本ルールです。
民法627条が根拠となっています。
- 法律では2週間前でOK
- 労働契約の自由がある
- 退職の許可は不要
- 就業規則より法が優先される
たとえば営業職のDさんは、体調不良で急遽退職を決めました。
1ヶ月前と決められていましたが、2週間前に申告しました。
すると「法律上は問題ない」と人事が理解を示しました。
上司からの圧力はありましたが、Dさんは冷静に法律の話を伝えました。
結果、退職は認められ、トラブルにもなりませんでした。
法律で守られていると知っていれば、心に余裕が持てます。

就業規則とのちがい
一方、就業規則では「1ヶ月以上前の申告」が一般的です。
これは会社独自のルールであり、法的強制力は限定的です。
労使契約の一部として運用されています。
- 社内での秩序維持のため
- 人員補充や引き継ぎ準備
- 社員に義務として定める
- 違反すると評価や関係悪化の恐れ
技術職のEさんは、引き継ぎを考慮して2ヶ月前に退職を申し出ました。
ところが就業規則をよく読むと「3ヶ月前」が正式ルールでした。
それを理由に「社内規定違反だ」と責められたのです。
Eさんは事前に規則を確認しておけばと悔やみました。
就業規則は会社内のルール。軽視すると不利になることもあります。

法律と会社の優先順位
法律と会社の就業規則が異なる場合、どちらが優先されるのでしょうか?
結論から言うと法律>就業規則です。
会社の規則が法律を上回ることはできません。
- 法律は国のルール
- 就業規則は社内ルール
- 労働者には法律の保護がある
- 合理性がなければ無効になる
たとえば事務職のFさんが、2週間前に退職届を出しました。
会社の就業規則には「1ヶ月前」とありました。
しかし、Fさんは法律を根拠に主張を貫きました。
労基署に相談した結果、会社も強くは出られなくなりました。
法律知識があったことで、理不尽な引き止めを防げたのです。
会社とぶつかる前に、まずは「法の順序」を確認しましょう。

退職2ヶ月前で怒られた3つの理由

退職を2ヶ月前に伝えたのに、上司に怒られた経験は珍しくありません。
その理由には、感情的なものだけでなく実務的な事情もあります。
怒られた理由を正しく理解することで、適切に対応することができます。
まずは、よくある3つの理由から見ていきましょう。
繁忙期にあたる
退職の時期が繁忙期に重なると、上司は強く反応することがあります。
人手不足や業務への影響を考えると、当然の反応とも言えます。
繁忙期の退職は周囲の負担が増すリスクがあります。
- 通常より業務が多い時期
- 代替要員の確保が困難
- 周囲に迷惑がかかる
- 「わがまま」と誤解される
営業職のGさんは、年度末の3月に退職を申告しました。
この時期は繁忙期で、全社員が連日残業という状況でした。
上司は「今このタイミングか?」と声を荒らげました。
Gさんは事前相談していればよかったと後悔しました。
タイミングの悪さが、怒られた最大の要因だったのです。
繁忙期を避ける。それだけで反発は防げる場合があります。

引き継ぎの時間が足りない
引き継ぎ期間が短いと、上司は不安や焦りを感じます。
その結果、怒りとなって表れることがあります。
引き継ぎ不足は、職場に混乱を招く要因です。
- 後任がすぐ決まらない
- 業務知識の伝達が不十分
- 顧客対応に支障が出る
- 残されたメンバーに負担
技術職のHさんは、専門性の高い業務を担当していました。
退職を2ヶ月前に伝えたものの、後任がすぐに見つかりませんでした。
上司は「どうやって引き継ぐんだ」と怒りをぶつけました。
Hさんは資料をまとめ、逐一共有していきました。
なんとか無事に引き継ぎを終え、退職できました。
怒られないためには、「引き継ぎ計画」が必要です。

上司との信頼関係
退職の申告は、上司との関係性に大きく左右されます。
ふだんの関係が悪いと、少しのことで怒られることもあります。
信頼関係の有無が、対応の差を生みます。
- ふだん会話が少ない
- 感謝や報告が少ない
- 急な報告に驚かれる
- 不信感から怒られる
事務職のIさんは、上司とあまり関わりのない働き方をしていました。
退職の報告も、必要最小限の連絡で済ませました。
その結果「急に辞めるとは無責任だ」と言われてしまいました。
Iさんは「もっと早く相談しておけばよかった」と感じました。
コミュニケーションの少なさが、不信感を生んでしまったのです。
日頃からの信頼関係が、スムーズな退職を左右します。

上司に怒られたときの対応方法3選

退職を伝えて怒られた場合でも、冷静に対応すれば状況は改善できます。
大切なのは、感情的にならずに誠実に向き合うことです。
ここでは、怒られたときに実践したい具体的な対処法を紹介します。
どれも今日から使えるものばかりです。
話を最後まで聞く
怒られたときは、まず相手の話を最後まで聞く姿勢が大切です。
途中で反論すると、さらに怒りを買う恐れがあります。
傾聴の姿勢が、信頼回復の第一歩です。
- 相手の感情を受け止める
- 遮らずに話を聞く
- 表情や態度も大切
- 最後に「ありがとうございます」と返す
営業職のJさんは、退職の話で上司に叱られました。
最初は驚きましたが、黙って話を聞き続けました。
すると上司も冷静さを取り戻し、最後には「理解した」と言ってくれました。
Jさんの姿勢が、関係の修復につながったのです。
聞くことは、信頼をつなぐコミュニケーションの基本です。

冷静に理由を説明する
怒りに対して、感情的に返してはいけません。
冷静に退職の理由を説明すれば、理解を得やすくなります。
事実ベースの説明が、信頼を保つカギです。
- 退職理由を簡潔に
- 嘘をつかず正直に
- 会社への感謝を含める
- 将来のビジョンを伝える
事務職のKさんは、家族の介護を理由に退職を決意しました。
上司に怒られた後も、冷静に理由と今後の見通しを説明しました。
「納得した」と上司も態度を和らげました。
Kさんの誠実さが、職場との信頼を保ったのです。
冷静さと丁寧な説明が、相手の態度を変える力になります。

第三者に相談する
自分一人で抱え込まず、信頼できる第三者に相談するのも有効です。
客観的な意見をもらうことで、視野が広がります。
外部の力は、精神的な支えにもなります。
- 社内の人事部に相談
- 労働組合があれば活用
- 労働基準監督署へ相談
- 信頼できる同僚に話す
サービス業のLさんは、退職の件で毎日上司に怒鳴られていました。
精神的にも限界を感じ、労基署へ相談に行きました。
その後、会社側も態度を変え、冷静な話し合いが実現しました。
相談することで、守られるべき権利を知ることができたのです。
「助けを求めること」は、決して弱さではありません。

まとめ|退職2ヶ月前と就業規則の本当の関係
今回は、退職 2ヶ月前 就業規則 の正しい知識と対応法について紹介しました。
この記事のポイント!
- 労働法と就業規則の違い
- 怒られた理由の理解
- 上司との向き合い方
退職を2ヶ月前に伝えたことで怒られた背景には、会社側の事情や期待が関係していました。就業規則では1ヶ月前などの規定があることもあり、法律とはズレがあることが分かりましたね。
また、上司とぶつかっても感情的にならず、誠実な姿勢で話し合うことが解決の一歩でした。

今後の退職活動に役立つよう、今日の学びを行動につなげてください。