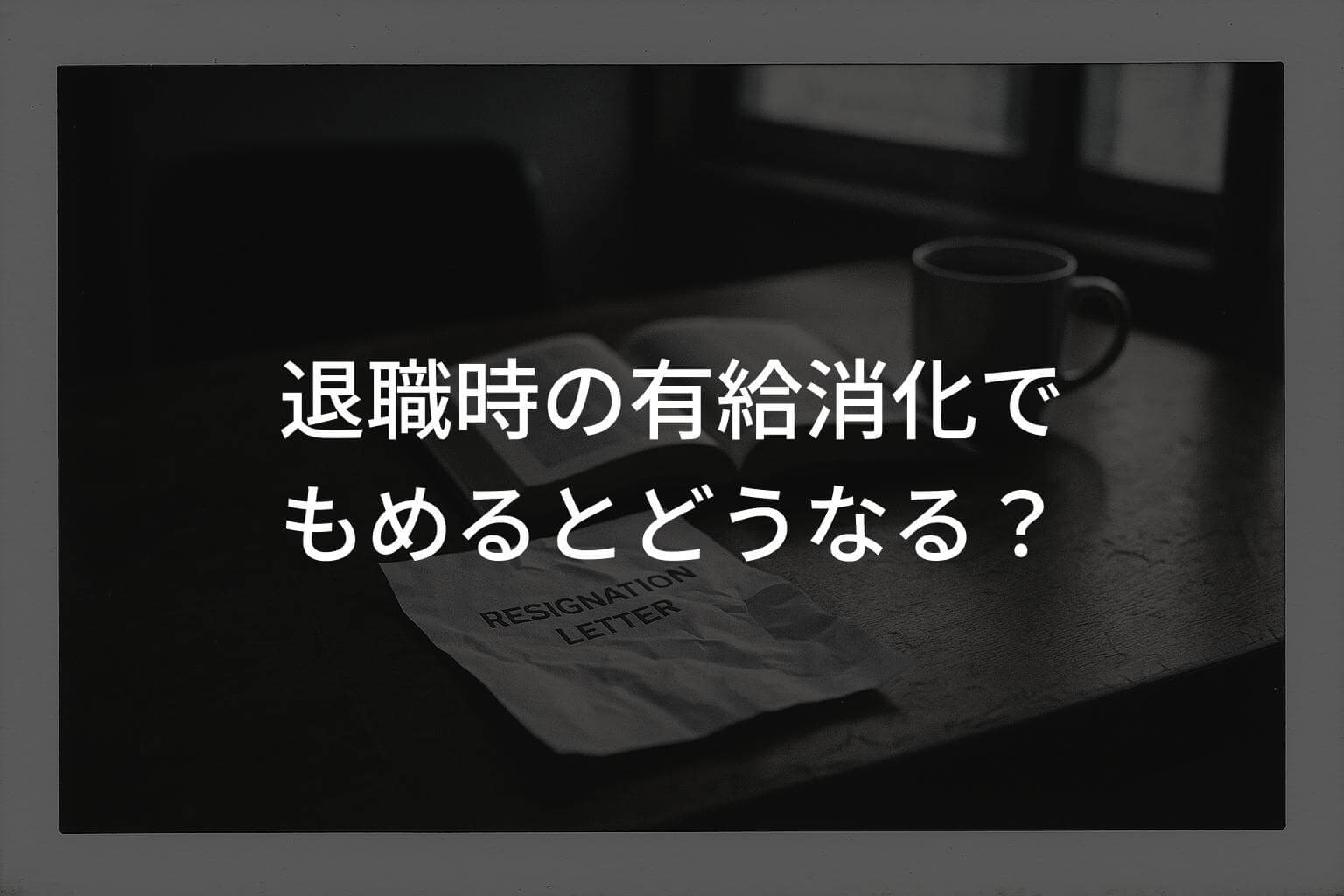このようなモヤモヤ、実はしっかり行動すればあなたの希望通りに進めることが可能です。
会社とのやり取りを記録に残す、労働基準監督署への相談など、有給を守る具体的な方法があります。
そこで、今回は退職時の有給消化でもめたときの対処法と損をしないポイントについて紹介します!
この記事で分かること!
- 退職時の有給休暇を拒否されたときの対処法
- 会社によくある言い分とその対抗策
- 労基署・弁護士相談など具体的な行動ステップ
退職有給でもめても、消化は可能です

退職時に有給休暇を使わせてもらえないケースは多くあります。
ですが、有給を使う権利は法律で守られており、拒否されても消化できます。
それでは、退職時の有給取得を会社に拒まれたとき、どのように行動すべきかを見ていきましょう。
退職が決まっているときでも、有給は正当に取得できます。
具体的な行動に移すために、まずは「なぜ取得できるのか」を理解しましょう。
有給を使うのは労働者の権利
退職前に有給休暇を使うのは、労働基準法で認められた当然の権利です。
会社側が「繁忙期だから」などを理由に拒否するのは、原則として違法です。
労働基準法第39条では、有給取得の希望日を「時季指定」できると定められています。
- 有給は法律で守られた権利
- 会社が一方的に拒否はできない
- 退職時も有効に使える
- 「繁忙期」でも原則取得可能
- 労働基準法第39条に明記
たとえば、退職を1か月後に控えた30代会社員Aさんが、残りの有給を使おうと申請しました。
しかし上司は「人手が足りないから出勤してくれ」と言い、取得を拒否。
Aさんは、労働基準監督署の相談窓口に状況を説明。
その結果、会社側は不当な拒否と認定され、有給取得が実現しました。
このように、正しい手続きを踏めば、会社側の都合だけでは拒否できません。
まずは「拒否されたから使えない」と思い込まず、法律を理解しましょう。
有給は退職前に使い切れるものだと、自信を持って動くことが大切です。
「退職する人は有給取れない」って思い込んでたけど、法律上は全然OKなんだね!

拒否されたときの3ステップ
会社に有給を拒否されたときは、焦らず順を追って対応すれば問題ありません。
特に退職時は、感情的にならず冷静に進めることが重要です。
ここでは、最短で有給を消化するための具体的な3つのステップを紹介します。
また、ここからのステップは多くの会社に対して適していますが、中には常識の通用しない会社もいます。
退職や有休消化を認めないと言ったり、あげくはパワハラのような脅しをかけてくる会社です。
そういった場合には有無を言わさず弁護士を味方につけられるサービスを使いましょう。
環境を変える選択肢を常に持っておこう
あなたが抜け出したい職場環境にいるのであれば、
当サイト推奨の必勝退職コンボを是非お伝えしたいです。
退職代行で円満退職?いいえそれだけではありません。
退職代行の後のお金の心配をなくすために、
国の給付金をフルで活用する方法をまとめています。↓↓
国の給付金制度の予算が尽きる前に、賢く使いましょう!
必勝退職コンボ解説記事: https://hojokin-webmarketing.com/recommendations-for-using-the-winning-retirement-combo/
- 口頭で言われた内容は必ずメモ
- 書面・メールでやり取りを残す
- 労基署や弁護士に早めに相談
たとえば、有給申請をしても「あとで話そう」と上司に流された場合。
そのときは、いつ・誰に・どう言われたかを記録しておきます。
次に、メールで「本日●時に、有給は使えないと伺いましたが」と事実を残します。
このように証拠を残すだけで、あとからの対応が大きく変わります。
さらに、それでも進展がなければ、労働基準監督署へ相談しましょう。
多くの人が「どうせ動いても無駄」とあきらめがちですが、それは誤解です。
相談がきっかけで、会社が手のひらを返すように態度を変える事例も多数あります。
書面化と相談、この2つを実行するだけでも流れが変わります。
「どうせ言ってもムダ」と思わず、やるべき手順をきっちりこなしましょう。
書面化するだけで、会社は急に慎重になるよ!

よくある「会社の言い分」に騙されないために

有給取得のトラブルでは、会社側がよく使う言い分があります。
一見もっともらしく聞こえますが、法的には通用しないことが多いです。
代表的な2つの主張について、正しい知識で対応できるようにしましょう。
会社の都合や口調に流されず、自分の権利を守る意識を持つことが重要です。
それぞれの主張にどう対処すべきか、具体的に見ていきましょう。
「繁忙期だから無理」は通用するのか?
「繁忙期だから」という理由で有給を拒否されることはよくあります。
ですが、退職時にはその主張はほとんど認められません。
なぜなら、すでに退職日が決まっており、代替手段を取る時間があるからです。
- 繁忙期でも拒否は原則NG
- 時季変更権は限定的な条件のみ
- 退職が決まっていれば使える
- 会社側は業務調整が必要
- 「人手不足」は理由にならない
たとえば、3週間後に退職する30代女性Bさんが、有給5日分を消化したいと申請。
すると上司は「今は忙しいから無理」と一言で拒否しました。
Bさんは労基署に相談し、会社の「時季変更権」は認められないと指導が入りました。
結果、有給は全日取得でき、Bさんは予定通りに退職しました。
「繁忙期だからダメ」は、あくまで会社側の都合でしかありません。
退職までに日数があれば、業務調整は会社の責任です。
自分の都合より会社の言い分が優先されるわけではないと知ってください。
繁忙期とか関係なく、有給は使えるんだよね!

「買い取りで済ませよう」に潜むリスク
「お金で払うから有給は使わなくていい」と言われるケースもあります。
これは一見ありがたい提案に見えますが、リスクも大きいです。
なぜなら、有給の買い取りは原則禁止で、退職時のみ一部例外があるためです。
- 有給買い取りは原則NG
- 退職時のみ例外あり
- 法律上の義務ではない
- 金額は会社側が決める
- 交渉しにくくなる
たとえば、契約社員Cさんが「有給全部買い取るから出社して」と言われたとします。
実際の金額は1日あたりの賃金×日数で、休むより少ないこともあります。
しかも、正式な計算書や明細もなく、口約束で終わるケースが多いです。
その結果、Cさんは2日分しか買い取ってもらえず、大きく損をしました。
このように、有給を「金で解決」しようとする話には注意が必要です。
使えるなら、原則として有給は消化する方が得です。
買い取りを選ぶ前に、必ず条件や金額を確認してください。
金額に納得できないなら、買い取りを断ろう!

退職有給トラブルに効く3つの行動

会社との有給トラブルを解決するためには、感情ではなく行動が大切です。
ここでは、実際に効果があった3つの行動をご紹介します。
これらの行動を組み合わせることで、会社にプレッシャーを与えられます。
順番に見ていきましょう。
1. 口頭→書面化する
最初のステップは、すべてのやり取りを「記録」に残すことです。
口頭のやり取りだけでは、証拠として残らず不利になります。
トラブル防止には、書面やメールを活用することが基本です。
- 口頭ではなく書面で残す
- メール・LINEでもOK
- 日時と相手の名前を明記
- 拒否内容も文章にする
- 「申請しました」と記録
たとえば、派遣社員Dさんが有給申請を口頭で行ったところ「今忙しい」と流されました。
その後、メールで「本日〇時に申請しましたが、確認いただけましたか」と送信。
すると、会社側は対応を変え、書面で「取得可」と回答しました。
証拠を残すことで、相手の態度が変わることはよくあります。
「言った」「言わない」のトラブルを避けるためにも、書面化は必須です。
書面やメールにするだけで、対応が変わる!

2. 労基署に通報
次に試したいのが、労働基準監督署への相談です。
会社が不当な対応をしている場合、行政に訴えることで流れが変わります。
特に退職時の有給拒否は、労基署でもよくある相談内容です。
- 相談は無料でできる
- 匿名でも可能
- 全国に窓口あり
- 会社へ指導が入る
- 労働者に不利益はなし
30代会社員Eさんは、上司に有給を拒否されたため、労基署に匿名で相談しました。
数日後、労基署から会社に連絡が入り、事情を確認するよう指導がありました。
その後、会社は有給取得を認め、Eさんはトラブルなく退職できました。
「通報しても意味ない」と感じるかもしれませんが、実際は効果があります。
行政からの指導は、会社にとって無視できない圧力です。
労基署って相談だけでも動いてくれるんだね!

3. 弁護士の無料相談
最後の手段として、有給トラブルに強い弁護士への相談があります。
「お金がかかりそう」と不安になるかもしれませんが、無料相談もあります。
特に退職トラブルを扱う法律事務所では、初回無料で対応してくれるところが多いです。
- 初回無料の法律相談あり
- LINEやメールで相談可
- 退職代行と連携も可能
- 会社に代理人として交渉
- 慰謝料請求も視野に入る
例えば、契約社員Fさんは退職時の有給を全て拒否され、弁護士に相談。
弁護士が会社と交渉し、10日分すべての有給を取得できました。
さらに、違法対応について慰謝料の請求も進められる状態となりました。
相談することで、感情的なやり取りを避け、法的な主張ができます。
「泣き寝入りしたくない」と感じたら、早めに相談しておきましょう。
弁護士の一言で会社が態度を変えることもある!

損をしないための有給取得チェックリスト
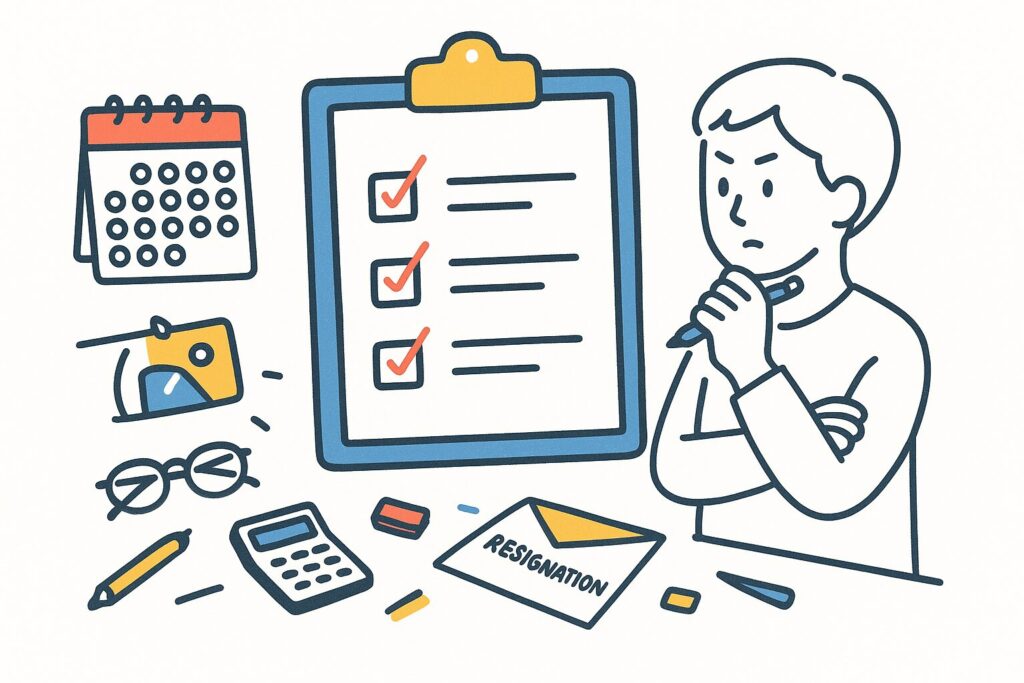
退職前に有給を使い切るには、いくつかの確認ポイントがあります。
うっかり見落とすと、消化できないまま退職日を迎えることもあります。
ここでは、損をしないために確認すべき2つのチェックポイントを紹介します。
事前準備をしっかりしておけば、焦らずスムーズに消化できます。
確認と書類管理がトラブル防止のカギです。
自分の有給残日数を確認する
まず確認すべきは「あと何日有給が残っているか」です。
残日数を把握していないと、正しく消化することはできません。
確認方法は、給与明細・勤怠システム・人事部への確認などです。
- 給与明細に記載されている
- 社内システムで確認できる
- 人事部にメールで問い合わせ
- 有給の期限切れに注意
- 使い残しを避けるために早めに確認
たとえば、40代会社員Gさんは「10日くらい残っているはず」と思っていたものの、
実際は4日しか残っておらず、希望通りに休めない事態に。
また、取得期限が過ぎた分は失効していたため、大きく損をしました。
このように、曖昧な把握はリスクが高く、具体的な日数確認が欠かせません。
特に退職時は、有給をどう使うかがスケジュール全体に影響します。
「だいたい○日ある」は危険!正確に確認しよう!

出勤日や退職日の書類管理
次に重要なのは、出勤日と退職日を明確に管理することです。
特に最終出勤日と退職日が異なる場合、日数計算がずれる可能性があります。
これを間違えると、有給申請が不備になり却下されることもあります。
- 退職日と最終出勤日は別物
- 有給で調整する日を明確に
- 書面やメールで証拠を残す
- 退職願や退職届の提出日も重要
- タイミングによって社会保険の影響も
たとえば、派遣社員Hさんは最終出勤日を会社に伝え忘れ、
会社側が「退職日=最終出勤日」と処理し、有給消化が無効になりました。
後日、社会保険の手続きにも影響し、予定より早く資格喪失となってしまいました。
こうしたトラブルは、日付管理のズレが原因です。
申請前に書類とスケジュールを照らし合わせ、ミスのないようにしましょう。
最終出勤日と退職日、間違えると損するよ!

退職時にやってはいけないNG対応とは?
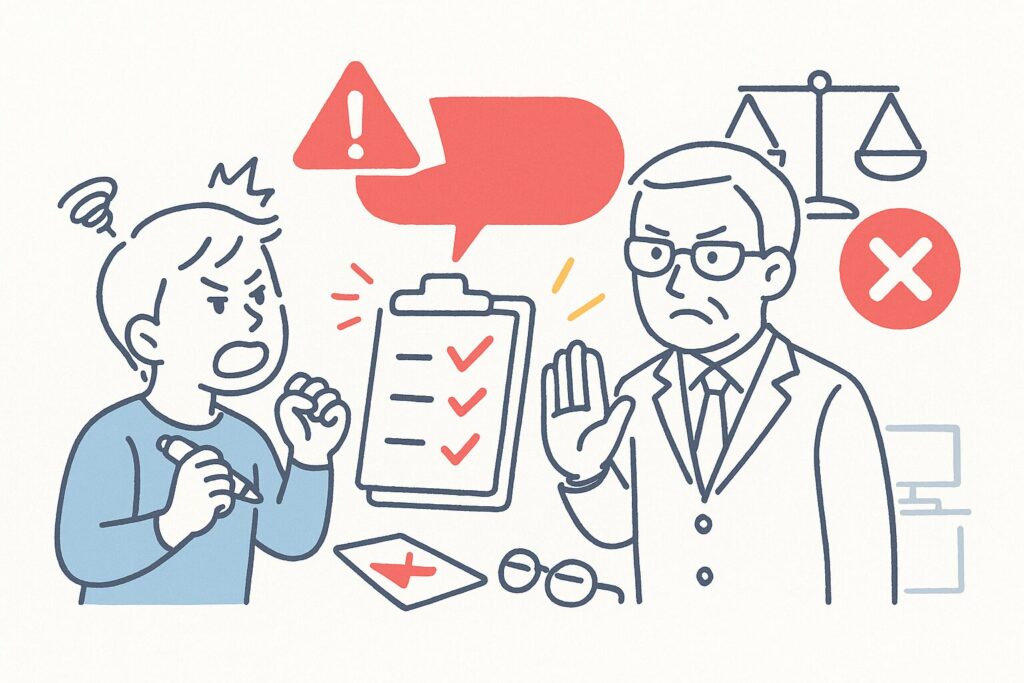
有給取得でもめたとき、感情的な対応をすると状況が悪化します。
退職時こそ冷静に、正しい手順で進めることが重要です。
ここでは、やってはいけない2つのNG対応を紹介します。
意図せず自分が不利になる行動を取らないよう、注意して行動しましょう。
感情的な交渉が不利になる理由
有給を拒否されたことで怒りがこみ上げてきても、感情的になるのは逆効果です。
相手を責めるような言い方をすると、会社側も強硬な態度になります。
その結果、有給取得どころか、退職手続き自体がこじれる可能性もあります。
- 怒りや不満をぶつけない
- 冷静で丁寧な言葉を選ぶ
- 証拠を示して主張する
- 第三者を交えることも検討
- 録音や記録で自分を守る
たとえば、50代男性Iさんは「こんな会社辞めてやる」と上司に怒鳴り、
会社側は「退職届を撤回されたとみなす」と判断し、有給申請を却下。
結果的に手続きがやり直しとなり、トラブルが長期化しました。
冷静に記録を残し、言葉を選ぶだけで相手の対応も変わってきます。
感情を抑え、事実と証拠で粛々と進めるのが一番の近道です。
感情をぶつけると、損するのは自分かもしれない!

脅し文句に屈しないための心構え
退職時、会社からの脅し文句に不安になる人も少なくありません。
「有給なんて認めないぞ」「退職金を出さないぞ」など、不安をあおる発言があるかもしれません。
しかし、これらは法的に通用しない脅しです。
- 違法な脅しは無視してOK
- 退職や有給は法律で守られている
- 不安な場合は第三者へ相談
- 記録を残すと証拠になる
- 自分の判断だけで動かない
たとえば、20代女性Jさんは「有給取ったら評価下げるよ」と言われ、
不安になって出勤を続けましたが、あとで相談し「明らかなパワハラ」と判断されました。
記録を残していたことで、会社は社内での対応を変更。
その後、全日程で有給が認められ、円満に退職できました。
脅しやプレッシャーを受けたときこそ、落ち着いて対応してください。
「退職金なし」とか言われたけど、全然そんなの関係なかった!

まとめ|退職時の有給消化トラブルを防ぐには?
今回は、退職時の有給休暇の消化トラブルとその対処法について紹介しました。
この記事のポイント!
- 有給取得は「権利」。拒否されても法的に消化できる
- 「繁忙期だから」「買い取りで済ませて」は通用しない可能性大
- 労基署や弁護士相談など具体的な行動が有効
「もう辞めるんだから…」と泣き寝入りする必要はありません。あなたの権利を守るために、今すぐ行動しましょう。

トラブルに巻き込まれないためにも、冷静かつ計画的に退職準備を進めていきましょう。