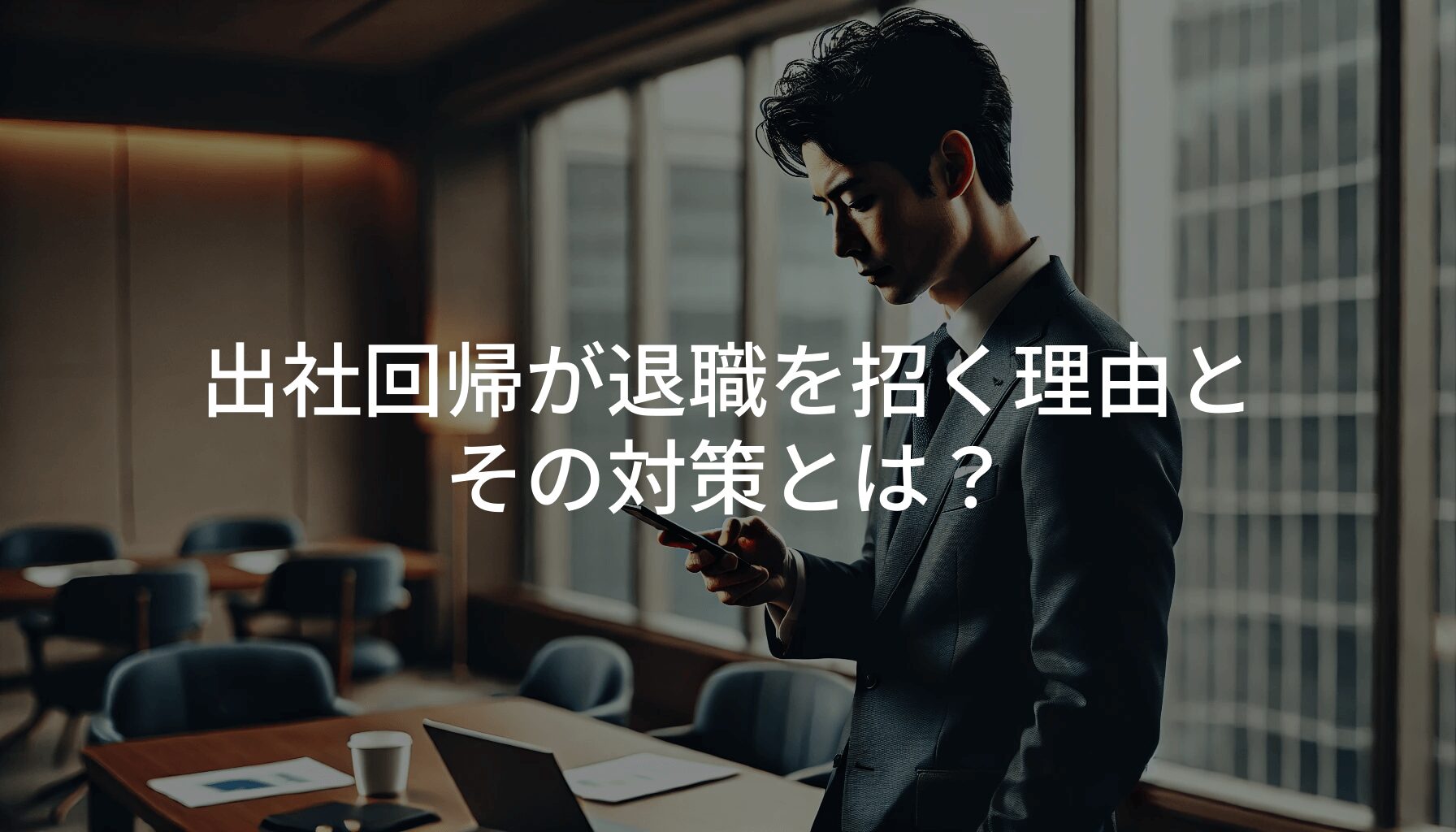リモートワークを経験した社員にとって、出社の義務化はストレスになりますね。
このままでは、企業の競争力にも影響が出るかもしれません。
そこで、今回は出社回帰が退職を招く理由とその対策について紹介します!
ポイント
もし現在のあなたが職場環境に辛さを抱えてしまっているのであれば、
環境を変える方法も解説しますね。
大丈夫、選択肢は自分で選んでいいんです。
以下からどうぞ。
この記事で分かること!
- 出社回帰が離職を招く理由
- 人材流出を防ぐためのポイント
- 成功企業の取り組み
出社回帰が進む背景とは?

近年、多くの企業がオフィス勤務へ回帰する動きを見せています。
リモートワークが定着しつつあったにもかかわらず、なぜ企業は出社を求めるのでしょうか?
出社回帰の背景には、以下のような要因が考えられます。
まずは、コロナ禍を経て働き方がどのように変化したのかを解説します。
コロナ後の働き方の変化
新型コロナウイルスの流行により、多くの企業がリモートワークを導入しました。
しかし、感染拡大が収束に向かうにつれ、出社を求める企業が増加しています。
この変化には、以下のような理由があります。
- 対面でのコミュニケーションの重要性が再認識された
- 企業文化の維持や組織の一体感が求められるようになった
- リモートワークによる生産性の低下を懸念する声がある
- オフィスの賃貸契約を維持する企業が多い
例えばある企業では、「雑談の減少」によるアイデア創出の機会損失が問題視されました。
また他には若手社員の育成や評価の難しさを理由に、オフィス勤務を推奨する企業も増えています。
このように、リモートワークの利点がある一方で、企業側は対面の価値を再評価しているのです。
では、具体的に企業はどのような理由でオフィス回帰を推進しているのでしょうか?
企業がオフィス回帰を推進する理由
企業が出社回帰を進める理由は、単なる「対面重視」の考え方だけではありません。
経営戦略や組織運営の観点から、オフィス勤務にメリットを見出しているケースが多いのです。
主な理由として、以下のポイントが挙げられます。
- 社員の生産性向上
- 企業文化の維持と組織力強化
- 新人や若手社員の育成
- 情報漏洩リスクの低減
- オフィス設備の有効活用
例えば、ある企業ではリモートワーク中に社員同士の連携が取りづらくなり、チームの生産性が低下しました。
特に、新入社員の教育や業務の引き継ぎが難しく、経験者との「学びの機会」が減少するという問題が発生しています。
また、セキュリティの観点からも、オフィス勤務を求める企業は少なくありません。
リモートワークでは情報管理の徹底が難しく、機密情報の漏洩リスクが高まるためです。
このような理由から、企業はオフィス回帰を進める傾向にあります。
しかし、海外では必ずしも同じ流れになっているわけではありません。
海外と日本の動向の違い
海外と日本では、出社回帰に対する姿勢が異なります。
特に欧米の企業では、リモートワークやハイブリッドワークを定着させる動きが強まっています。
その背景には、以下のような違いがあります。
- 成果主義の文化が根付いている
- リモートワークを前提とした評価制度が整備されている
- 通勤にかかる時間やコストが問題視されている
- オフィス縮小によるコスト削減を重視している
例えば、米国のIT企業では、完全リモートを導入してオフィスを縮小し、固定費削減に成功したケースもあります。
一方で、日本の企業は「対面での協力や調整」を重視する文化が根強く、オフィス勤務を維持したがる傾向があります。
このように、海外と日本では働き方に対する考え方が異なり、出社回帰の流れにも違いが生じているのです。
では、実際に出社回帰によって従業員の退職が増えるのはなぜでしょうか?
出社回帰で退職が増える3つの理由
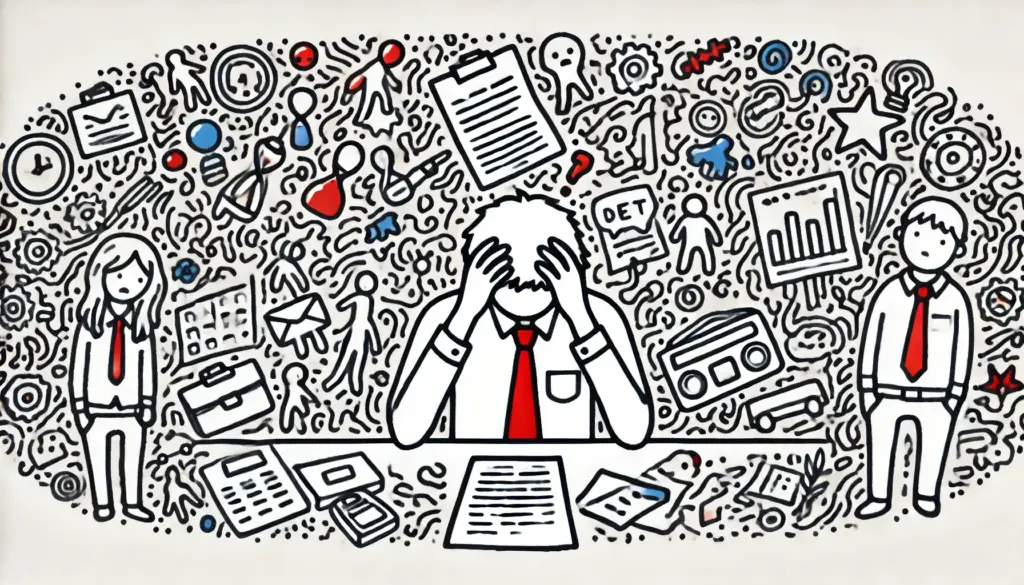
企業が出社回帰を推進する一方で、従業員の退職が増えているという現象も起きています。
なぜ、オフィス勤務の復活が退職の引き金になってしまうのでしょうか?
主な理由は、以下の3つです。
ここからは、それぞれの理由について詳しく解説していきます。
柔軟な働き方の消失
リモートワークが普及したことで、多くの人が「時間や場所に縛られない働き方」に慣れました。
しかし、出社回帰によって再び「決められた時間・場所」で働くことを強制されると、不満を感じる人が増えてしまいます。
特に以下のような人にとっては、大きなストレス要因になります。
- 育児や介護と仕事を両立している人
- 地方や郊外に住んでいる人
- 通勤時間を削減して生産性を向上させていた人
- 自己管理のもとで効率的に働くことに慣れていた人
例えば、小さな子どもを育てながらリモートワークをしていた人が、突然フル出社を求められると、家事・育児との両立が難しくなります。
結果として、「今の職場では続けられない」と判断し、転職を決意するケースが増えているのです。
では、次に「通勤負担とワークライフバランスの悪化」について見ていきましょう。
通勤負担とワークライフバランスの悪化
リモートワークの大きなメリットのひとつが「通勤の負担がなくなること」です。
しかし、出社回帰によって毎日の通勤が再び必須になると、多くの人が「以前より負担が大きくなった」と感じるようになります。
特に、以下のような要因が退職の決断を後押しします。
- 長時間の通勤による疲労の増加
- 通勤コスト(交通費・ガソリン代・駐車場代など)の負担
- 通勤時間の増加によるプライベート時間の減少
- コロナ禍で在宅勤務に慣れた人のストレス増加
例えば、片道1時間以上かけて通勤していた人がリモートワークでその負担から解放されたのに、再び満員電車に乗らなければならないとしたらどうでしょうか?
多くの人が「この生活には戻れない」と考え、リモートワークを続けられる企業へ転職を検討するようになります。
このように、通勤の負担は従業員の離職率を高める大きな要因の一つとなっているのです。
最後に、「従業員のエンゲージメント低下」について解説します。
従業員のエンゲージメント低下
出社回帰が進むことで、従業員の「エンゲージメント(会社への愛着や意欲)」が低下するケースが増えています。
リモートワークに慣れた人にとっては、オフィス勤務が「柔軟性のない働き方」に感じられるためです。
特に、以下のような点が不満につながる要因となります。
- 会社の方針変更による信頼感の低下
- 出社によって自由度が制限されるストレス
- リモートワークのメリットを享受できなくなる不満
- 他社との比較による「転職」の選択肢が浮上
例えば、リモートワーク中は「仕事の合間に家事ができる」「自分に合った働き方ができる」と感じていた従業員が、出社回帰によってそのメリットを奪われたと感じた場合、不満を抱きやすくなります。
また、最近では「リモートワーク可の企業」が増えており、出社を求める会社に対して「競争力が低い」と感じる人もいます。
結果として、「この会社では自分の望む働き方ができない」と判断し、転職を考えるようになるのです。
では、こうした退職リスクを防ぐために、企業はどのような対策を取るべきなのでしょうか?
出社回帰による離職を防ぐための対策5選

出社回帰による離職を防ぐためには、従業員の不満やストレスを軽減する対策が必要です。
企業が取り組むべき具体的な施策として、以下の5つの方法が挙げられます。
しかし、下記に記載する対策をどこまで実施してくれるかは企業によります。
企業のトップが積極的に旗振りをしないと実現できない施策も含まれているので、
ただ待っているだけでは実現しない可能性も高いです。
実際には退職率が高くなってから、
初めて対策を検討する会社がほとんどのため、
自ら選択肢を増やすアンテナを張っておくことが重要です。
環境を変える選択肢を常に持っておこう
あなたが抜け出したい職場環境にいるのであれば、
当サイト推奨の必勝退職コンボを是非お伝えしたいです。
退職代行で円満退職?いいえそれだけではありません。
退職代行の後のお金の心配をなくすために、
国の給付金をフルで活用する方法をまとめています。↓↓
国の給付金制度の予算が尽きる前に、賢く使いましょう!
必勝退職コンボ解説記事: https://hojokin-webmarketing.com/recommendations-for-using-the-winning-retirement-combo/
それでは、企業に推奨される対策の説明に戻ります。
ここからは、それぞれの対策について詳しく解説していきます。
ハイブリッドワークの導入
出社回帰による離職を防ぐために、多くの企業が「ハイブリッドワーク」を導入しています。
ハイブリッドワークとは、出社とリモートワークを組み合わせた働き方のことです。
この制度を導入することで、以下のようなメリットが得られます。
- 従業員の柔軟な働き方を実現できる
- 通勤負担を軽減し、ワークライフバランスを向上させる
- 対面コミュニケーションとリモートの利点を両立できる
- 従業員満足度が向上し、退職率の低下につながる
例えば、週3日はオフィス勤務、残りの2日はリモートワークを認める「週2リモート制」を導入する企業も増えています。
これにより、通勤負担を減らしつつ、必要な対面コミュニケーションも確保できます。
企業が従業員の希望を柔軟に取り入れることで、退職リスクを低減できるのです。
次に、「通勤手当や福利厚生の充実」について詳しく解説します。
通勤手当や福利厚生の充実
出社回帰による負担を軽減するために、「通勤手当や福利厚生の充実」を図ることも有効です。
従業員が「出社しても損をしない」と感じる環境を整えることで、退職を防ぐことができます。
具体的には、以下のような施策が考えられます。
- 通勤手当の増額(交通費全額支給・ガソリン代補助など)
- フレックスタイム制の導入による通勤ラッシュ回避
- オフィス内のカフェ・食堂の充実
- リモートワーク時の在宅勤務手当支給
例えば、ある企業では「出社する日には無料ランチを提供する」ことで、出社率を向上させつつ従業員満足度を高めています。
また、コワーキングスペースの利用補助を出すことで、従業員が自宅以外の場所でも快適に働けるようにしている企業もあります。
このように出社のデメリットを軽減し、働きやすい環境を整えることで、離職リスクを下げることが可能です。
次に、「オフィス環境の改善」について詳しく見ていきましょう。
オフィス環境の改善
リモートワークに慣れた従業員にとって、「オフィスの居心地の良さ」は非常に重要なポイントです。
オフィス環境が改善されれば、「出社したい」と思う人も増え、退職を防ぐことができます。
具体的な改善策として、以下のようなものがあります。
- フリーアドレス制の導入で快適な座席を選べるようにする
- リラックススペースや集中スペースの設置
- オフィスのデザインをカフェ風にするなど、居心地の良さを向上
- オンライン会議専用ブースの設置で、リモートワークとの併用をしやすくする
例えば、大手企業では「オフィスをカフェのような空間に改装」し、従業員が出社したくなる環境を整えたことで、出社率が向上しました。
また、フリーアドレス制を導入し、固定席をなくすことで「その日の気分や業務内容に応じて快適な場所を選べる」ようにした企業もあります。
このように、オフィスを「ただ働く場所」ではなく、「快適に過ごせる空間」に変えることで、従業員の満足度を向上させることができます。
次に、「従業員の意見を反映した制度設計」について解説します。
従業員の意見を反映した制度設計
出社回帰を進める際に、最も重要なのは「従業員の声をしっかり聞くこと」です。
トップダウンで一方的に決めるのではなく、従業員の意見を反映した制度を設計することで、納得感を高めることができます。
具体的な方法として、以下のような取り組みが有効です。
- 定期的なアンケートを実施し、従業員の意見を収集
- 出社回帰の方針を柔軟に変更できる仕組みを導入
- 部門ごとに最適な勤務形態を選択できる制度を設ける
- 社内コミュニティを活性化し、意見交換の場を増やす
例えば、ある企業では「出社日を自分で選べる制度」を導入し、従業員の意見を最大限尊重する形で運用を行っています。
また、定期的に「オフィス勤務の満足度調査」を実施し、その結果をもとに改善策を打ち出すことで、離職を防いでいる企業もあります。
このように、従業員と対話しながら制度を設計することで、出社回帰に対する不満を最小限に抑えることができます。
次に、「柔軟な勤務形態の選択肢を増やす」方法について解説します。
柔軟な勤務形態の選択肢を増やす
出社回帰による退職を防ぐためには、「勤務形態の選択肢」を増やすことも重要です。
全員に一律の勤務形態を強制するのではなく、個々のライフスタイルや業務内容に合わせた働き方を選べるようにすることで、従業員の満足度を向上させることができます。
具体的な取り組みとして、以下のような制度を導入する企業が増えています。
- 週複数回のリモートワークを選択可能にする
- フレックスタイム制を導入し、出勤時間を柔軟に調整できるようにする
- ワーケーション(旅行先や地方での勤務)の許可
- パートタイム勤務や時短勤務の選択肢を増やす
例えば、ある企業では「週2回までリモートワーク可能」とすることで、通勤負担を軽減しつつ、対面でのコミュニケーションも確保するバランスの良い制度を実現しています。
また、別の企業では「早朝勤務・夜間勤務を選べるフレックスタイム制」を導入し、個々のライフスタイルに合わせた働き方を提供することで、離職率の低下につなげています。
このように、柔軟な働き方を提供することで、出社回帰に対するネガティブな印象を和らげることができます。
次に、「ハイブリッドワークの導入で離職を防ぐ方法」について詳しく解説します。
ハイブリッドワークの導入で離職を防ぐ方法
ハイブリッドワークは、出社とリモートワークのメリットを両立させる有効な手段です。
この仕組みを適切に導入すれば、従業員の満足度を向上させつつ、企業の生産性も維持することができます。
成功するハイブリッドワークのポイントとして、以下の点が挙げられます。
それでは、それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。
成功するハイブリッドワークのポイント
ハイブリッドワークを成功させるためには、単に「リモートワークと出社を組み合わせる」だけではなく、明確なルールやサポート体制が必要です。
適切な制度を設計しなければ、リモートワークと出社の間で不公平感が生じ、逆に不満が高まるリスクもあります。
成功のポイントとして、以下の点が重要になります。
- 出社・リモートのルールを明確にし、社内で統一する
- 業務内容に応じた最適な勤務形態を選択できるようにする
- リモートワーク時の評価制度を整備し、働き方の公平性を保つ
- オンライン会議やチャットツールの活用でコミュニケーションの質を高める
例えば、ある企業では「週に1回は必ず出社する日を設ける」ことで、対面でのコミュニケーションを確保しながら、リモートワークの自由度も維持するバランスを取っています。
また、業務ごとに最適な勤務形態を選べるようにし、「リモートで問題なく進められる仕事は在宅勤務OK」とする柔軟なルールを導入する企業も増えています。
このように、ハイブリッドワークを適切に設計することで、企業の生産性を維持しながら、従業員の満足度を向上させることが可能です。
次に、「効果的なコミュニケーションの取り方」について解説します。
効果的なコミュニケーションの取り方
ハイブリッドワークでは、オフィス勤務とリモートワークの間でコミュニケーションのギャップが生じやすくなります。
このギャップを解消するために、企業は意識的に「効果的なコミュニケーション手法」を導入する必要があります。
具体的には、以下のポイントが重要です。
- オンライン会議のルールを明確にし、無駄な会議を減らす
- チャットツールを活用し、リアルタイムで情報共有を行う
- 出社組とリモート組が公平に情報を得られるように工夫する
- 1on1ミーティングを定期的に実施し、個々の課題を把握する
例えば、ある企業では「会議をすべて録画し、後から視聴できるようにする」ことで、リモートワーカーが情報の取りこぼしを防げるようにしています。
また、「オフィス勤務の人もあえてオンライン会議に参加する」ことで、リモート組と出社組の情報格差をなくす工夫をしている企業もあります。
このように、適切なツールの活用とルールの整備により、ハイブリッドワーク下でも円滑なコミュニケーションを維持することが可能です。
次に、「チームの生産性を維持する工夫」について詳しく見ていきましょう。
チームの生産性を維持する工夫
出社とリモートを組み合わせるハイブリッドワークでは、「生産性の低下」を防ぐための工夫が必要です。
オフィス勤務の従業員とリモートワークの従業員がスムーズに協力できる環境を整えることが求められます。
生産性を維持するための具体的な施策として、以下のような方法があります。
- 業務の進捗を可視化するツール(プロジェクト管理ツール)の導入
- 業務のマニュアル化を進め、属人化を防ぐ
- リモートワークでも評価が適正に行われる仕組みを整備する
- 成果ベースの評価制度を導入し、勤務時間よりも成果を重視する
例えば、ある企業では「タスク管理ツールを活用し、チーム全体の業務進捗をリアルタイムで共有」することで、リモートと出社の差をなくすことに成功しました。
また、「リモートワークでも成果を正当に評価できる制度を導入」することで、オフィス勤務者との不公平感を解消する企業も増えています。
このように、適切なツールと評価制度を導入することで、ハイブリッドワークでも高い生産性を維持することが可能です。
次に、「企業の成功事例から学ぶ出社回帰の工夫」について解説します。
企業の成功事例から学ぶ出社回帰の工夫
出社回帰を進める企業の中には、従業員の負担を最小限に抑えながら成功しているケースもあります。
ここでは、出社回帰をスムーズに進めるための工夫を取り入れた企業の事例を紹介します。
まずは、「大手企業のハイブリッドワーク成功事例」について見ていきましょう。
大手企業のハイブリッドワーク成功事例
大手企業の中には、出社回帰を進めつつも、従業員の働きやすさを確保するための工夫を行っている企業があります。
特に、ハイブリッドワークを活用して成功した事例が注目されています。
具体的な成功事例として、以下のような取り組みが行われています。
- 週3日オフィス勤務+週2日リモートのハイブリッド制を導入
- オフィスをフリーアドレス化し、より快適な環境を提供
- リモートワークでも社員同士が交流できる仕組みを構築
- 対面での会議を減らし、オンラインで完結できる業務を増やす
例えば、ある大手企業では「出社する曜日を個人の裁量で選べる制度」を導入し、柔軟な働き方を可能にしました。
また、出社を促すために「オフィス内にカフェスペースを設ける」「ジムやリラックスルームを用意する」などの施策を行い、出社のメリットを感じられる環境を整えています。
このように、従業員の自由度を確保しながら出社回帰を進めることで、退職を防ぐことができます。
次に、「中小企業が取り入れた柔軟な働き方」の事例を紹介します。
中小企業が取り入れた柔軟な働き方
大手企業ほどのリソースがない中小企業でも、柔軟な働き方を取り入れることで出社回帰をスムーズに進めた事例があります。
特に、従業員の働きやすさを重視した取り組みが成功の鍵となっています。
中小企業で実施された具体的な工夫として、以下のような事例があります。
- リモートワークと出社の選択肢を部署ごとに柔軟に設定
- 小規模なサテライトオフィスを設置し、通勤時間を短縮
- チームごとに出社日を決め、業務の進め方を最適化
- 出社するメリットを明確にし、働き方の自由度を確保
例えば、あるIT企業では「週1~2日は必ず出社するが、それ以外はリモート可」とする制度を導入し、業務の効率と自由度を両立させています。
また、別の企業では「出社した際にはランチ代補助を出す」ことで、オフィス勤務の負担を軽減し、出社意欲を高める工夫をしています。
このように、中小企業でも従業員のニーズに合わせた柔軟な制度を取り入れることで、退職を防ぐことが可能です。
次に、「従業員満足度を高めた企業の取り組み」を見ていきましょう。
従業員満足度を高めた企業の取り組み
出社回帰を進める際に、従業員満足度を高めることが成功の鍵となります。
単に「オフィス勤務を義務化する」のではなく、従業員が納得し、モチベーションを維持できる環境を整えることが重要です。
実際に成功した企業では、以下のような取り組みを行っています。
- 出社したくなる職場環境(カフェ風オフィス・リラックススペース)を整備
- 出社時にはチームでランチミーティングを実施し、コミュニケーションを促進
- リモートワーク時と出社時の業務効率を比較し、最適な働き方を個別に設計
- 「働き方に関する定期的なヒアリング」を実施し、フィードバックを反映
例えば、ある企業では「出社した日は勤務時間内にジムが利用できる」制度を導入し、健康管理の面でもメリットを感じられるよう工夫しています。
また、「チームビルディングを目的とした社内イベント」を増やし、出社の意義を感じられるようにする企業もあります。
このように、従業員が「出社して良かった」と思える環境を整えることが、出社回帰を成功させるポイントです。
まとめ:出社回帰を進めるなら従業員の声を大切に
出社回帰が進む中で、多くの企業が「従業員の離職増加」という課題に直面しています。
退職を防ぐためには、単に「出社を義務化する」のではなく、従業員の不満や負担を軽減する取り組みが欠かせません。
本記事で紹介した対策をまとめると、以下のポイントが重要になります。
- ハイブリッドワークを導入し、柔軟な働き方を確保する
- 通勤負担を軽減するために手当や福利厚生を充実させる
- オフィス環境を改善し、出社のメリットを感じられるようにする
- 従業員の意見を反映した制度設計を行い、納得感を高める
- 成功事例を参考に、自社に合った最適な働き方を模索する
出社回帰を進める企業にとって、従業員の満足度を高めることは「人材の定着率」や「生産性向上」にも直結します。
「どのような働き方が、従業員にとって最適なのか?」をしっかりと考え、企業と従業員双方にとって最良の環境を作っていきましょう。
出社回帰による退職を防ぐために
今回は、出社回帰による退職増加の原因と、企業が取るべき対策について紹介しました。
この記事のポイント!
- 通勤負担が働きやすさを損なう
- 出社強制が従業員の不満を招く
- 柔軟な勤務制度の導入が重要
オフィス回帰が進む中で、通勤の負担増や在宅勤務の利点喪失により、従業員の不満が高まり退職が増えていました。しかし、ハイブリッドワークの導入やオフィス環境の改善により、離職を防ぐ工夫が可能でした。

労働環境の最適化を進め、組織の生産性向上に取り組んでください。