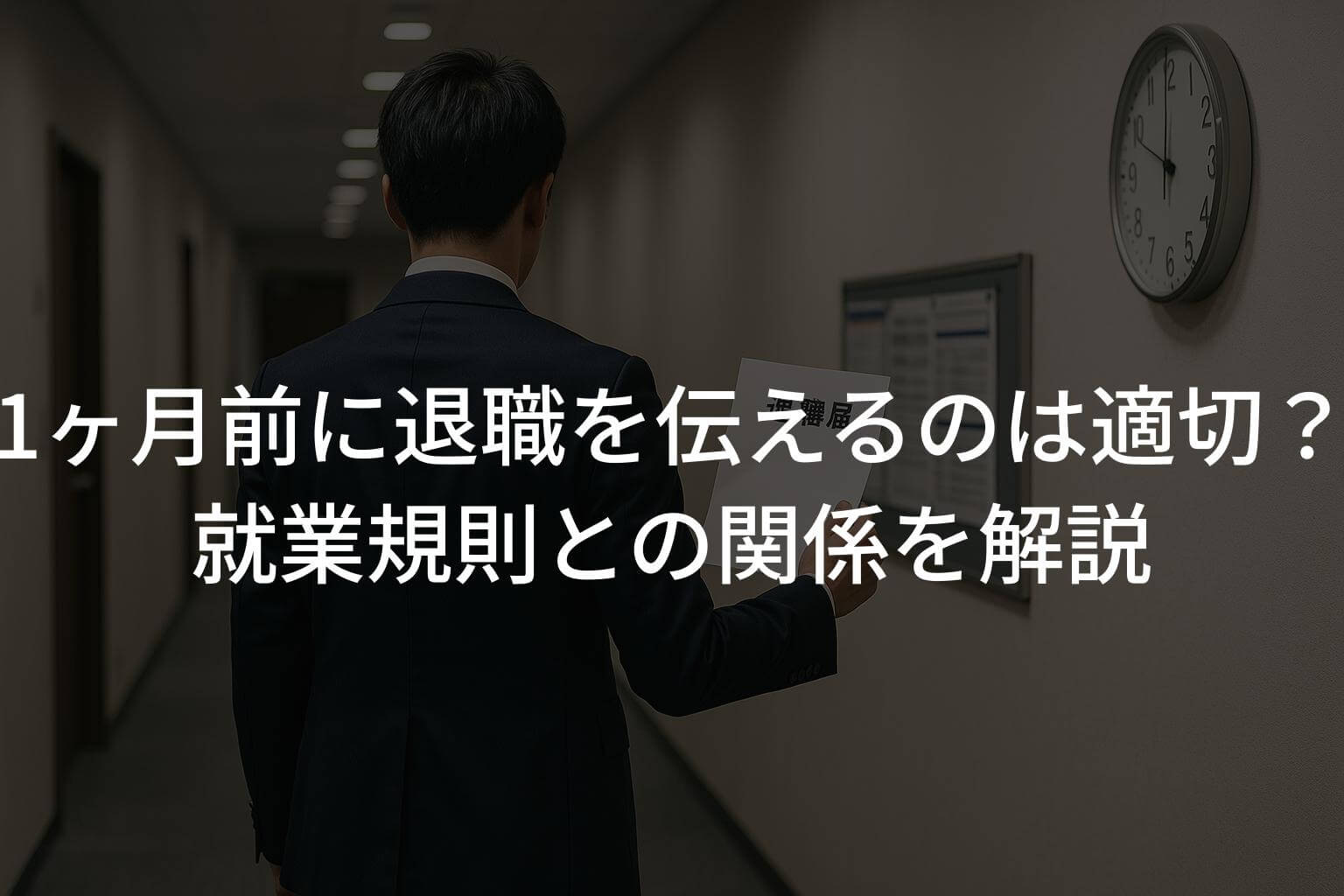対応を間違えると、会社とのトラブルや引き止めの長期化につながる可能性があります。「1ヶ月前に退職を伝える」ときの法的ルールと、円満に終える実務の型を先におさえましょう。
この記事で分かること
- 結論:原則は民法627条で「2週間前でも可」。ただし就業規則/契約が優先される場合あり
- 1ヶ月前に退職を伝えるときのケース別(試用/有期/繁忙期/有給消化)の現実解
- 揉めないための手順(上司への伝え方、引き継ぎ設計、メール文コピペ可)
【先に結論】「1ヶ月前に退職を伝える」で迷う人は、まずは全体設計(必勝退職コンボ)を3分で確認
- 1ヶ月前に退職を伝えるのは法律上OK?(民法627条)
- 民法627条と就業規則のどちらが優先?
- 退職届を出すベストなタイミングと段取り
- 1ヶ月前に退職を伝えるときのケース別チェック
- 円満退職のためにやるべき3つのこと
- FAQ|「1ヶ月前に退職を伝える」でよくある質問
1ヶ月前に退職を伝えるのは法律上OK?

結論:期間の定めがない雇用契約であれば、民法627条により2週間前の意思表示で退職可。したがって、1ヶ月前に退職を伝えるのは法律上はまったく問題ありません。
- 対象:期間の定めがない雇用(正社員など)
- 最短ライン:2週間前の退職意思表示
- ただし就業規則/契約の特約があれば優先される場合あり
実務では引き継ぎや人員調整の観点から、円満退職を狙うなら「1ヶ月前」の申出が最適解。まずは自社の就業規則・雇用契約書の該当条項を確認しましょう。一次情報はe-Gov(民法)。
民法627条と就業規則のどちらが優先?

就業規則の効力とは
就業規則は労働基準法に基づく社内ルールで、周知されていれば労働契約の内容として扱われます。そこに退職申出の期限(例:1ヶ月前)が明記されていれば、従う必要が生じます。
- 10人以上の事業場は作成義務
- 周知=契約へ組み込みの効果
- 退職の申出期限が記載されることが多い
補足:「周知されていない/説明がない」就業規則は、効力が否定される可能性があります。
民法との優先順位の考え方
原則、個別合意(契約書・就業規則)が民法の一般規定より優先。あなたが内容を理解し受け入れている(周知・合意)と判断されると、「1ヶ月前」以上の申出義務が有効になります。
- 就業規則/契約の特約>民法(一般原則)
- 有効要件は周知・合意
- 不明な場合は一次情報と人事への確認を
補足:周知・合意の有無はトラブル時の争点になりやすいポイントです。
判例からの示唆(簡易)
周知・説明が不十分な就業規則の申出期限は無効とされた例がある一方、明確な説明と同意があれば会社側が優先された例もあります。まず自社規程と説明履歴をチェックしましょう。
- 争点:周知・説明・同意の有無
- 証跡:配布/閲覧環境/入社時説明
- 疑義時は人事/労務へ相談
補足:ケースは事情により異なるため、断定は避け、一次情報と担当部門へ確認を。
先に全体設計を確認する ≫ 必勝退職コンボ(退職代行→給付金→リスキリング)
退職届を出すベストなタイミングと段取り

退職届と退職願の違い
退職願=交渉の余地、退職届=意思確定。まずは上司へ口頭相談→必要なら退職願→条件が固まったら退職届、の順が安全です。
- 最初は直属上司へ口頭相談
- 交渉段階は退職願で意思表明
- 決定後に退職届を提出
補足:感情的な勢いでいきなり退職届を出すのは非推奨です。
出すタイミングの目安(完全一致KWをH3に1回)
就業規則/契約の定めが最優先。定めがなければ、1ヶ月前に退職を伝えるのが引き継ぎ実務上も現実的。遅くとも民法の2週間前には提出を完了しましょう。
- 原則:就業規則/契約の期限に合わせる
- 実務:引き継ぎを見越して1ヶ月前に申出
- 最終ライン:2週間前(民法627条)
補足:有給消化を想定するなら、提出はさらに前倒しが無難です。
トラブルを避けるコツ
「誰に」「どの順番で」「何を持って」伝えるかで、印象と進行が大きく変わります。文面/記録を残し、感情的な衝突を避けるのが鉄則です。
- 直属上司→人事の順で伝える
- 理由は前向きに(キャリア/家庭/健康)
- 書面・メールで記録を残す
補足:ハラスメントや強い引き止めには、第三者の支援や退職代行の活用も検討を。
【コピペ可】上司への退職連絡メール例(1ヶ月前に退職を伝える)
件名:退職のご相談(◯◯部 ◯◯) ◯◯部 ◯◯様 お世話になっております。◯◯部の◯◯です。 このたび一身上の都合により、◯月◯日を最終出社日として退職したく、 ご相談の機会を頂けますでしょうか。 業務への影響を最小化するため、引き継ぎ計画(概要)を用意しております。 お忙しいところ恐縮ですが、今週◯曜〜◯曜のいずれかで お時間をいただけますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。
1ヶ月前に退職を伝えるときのケース別チェック
試用期間中に1ヶ月前に退職を伝える場合
試用期間は比較的柔軟に退職が認められやすい一方、就業規則/契約の定めがあればそれに従います。最短は民法の2週間だが、円満狙いなら1ヶ月前申出+引き継ぎ最小化が無難。
- 試用規程の申出期限を確認
- 評価中のため態度/勤怠に注意
- 引き継ぎは最小限かつ文書化
補足:人事評価中のため、印象管理が特に重要です。
有期契約で1ヶ月前に退職を伝える場合
満了退職が基本。期間途中の退職は「やむを得ない事由」等が問題となるケースがあり、契約書の解除条項/ペナルティを事前に確認。
- 解除条項/違約金の有無
- 満了退職のスケジュール化
- やむを得ない事由の立証難度
補足:判断が難しい場合は労務/専門家へ相談を。
繁忙期・管理職で1ヶ月前に退職を伝える場合
代替困難性が高く、引き継ぎ計画書の提示が摩擦を減らします。体制影響を数値で可視化し、後任/スケジュール/権限移管をセットで提案。
- 役割・案件棚卸しを先行
- 後任候補×教育工数の見積
- 権限移管(承認/各種ツール)
補足:相手の懸念(責任の空白)を潰す資料作りが鍵。
有給消化を前提に1ヶ月前に退職を伝える場合
有給取得は権利だが、業務の正常な運営との調整が必要。逆算して提出を前倒しし、同時に取得計画を提示すると通りやすい。
- 残日数/消化計画を提示
- 繁忙/代替要員の調整案
- 最終出社日を明確化
補足:同僚への負担感を下げる配慮コミュニケーションを。
円満退職のためにやるべき3つのこと

引き継ぎの準備をする
引き継ぎの出来=あなたの最終評価。タスク棚卸し→手順書→権限移管→日程調整の順で抜け漏れを潰します。
| 項目 | 具体例 | 完了 |
|---|---|---|
| タスク棚卸し | 定例/臨時・期限・依存関係の一覧化 | □ |
| 手順書 | 作業マニュアル/連絡先/保管場所の明記 | □ |
| アクセス権 | 権限移管/パスワード返却/共有設定 | □ |
| 有給計画 | 逆算した取得スケジュールの提示 | □ |
| 後任調整 | OJT日程/同席ミーティング設定 | □ |
- 口頭説明だけにせず文書化
- ファイル構成/保管場所を明示
- 期限/責任者が分かる形で引き渡す
補足:「これを見れば大丈夫」と思える資料作りを意識しましょう。
感謝の気持ちを伝える
送別メールや口頭で、上司・同僚・関係者へ短く丁寧に。立つ鳥跡を濁さずの姿勢が最後の印象を決めます。
- 直属上司へ個別に
- チーム/関係部署に一言
- 関係者全体にはメールで
補足:ネガティブな理由は具体化しすぎず、前向きに。
退職日まで責任を持つ
最終週ほど態度/勤怠は見られます。最後まで一貫したプロ意識で、惜しまれる終わり方を。
- 遅刻・欠勤をしない
- 礼儀と基本の徹底
- 手抜きをしない
補足:去り際ほど人間性が伝わります。
FAQ|「1ヶ月前に退職を伝える」でよくある質問
Q&A
- 1ヶ月前に退職を伝えるのは法律的に問題ない?
- 原則、民法627条により期間の定めのない雇用は「2週間前」でも可。就業規則や契約で1ヶ月前以上の定めが周知・合意されていればその限りではありません。
- 繁忙期でも1ヶ月前に退職を伝えてよい?
- 伝えること自体は問題ありませんが、引き継ぎに時間を要するため、計画書とスケジュールの同時提示が現実的です。
- 有期契約の途中で1ヶ月前に退職を伝えるのは可能?
- 期間途中は「やむを得ない事由」等が必要になるケースがあります。契約書・就業規則・ペナルティ条項を必ず確認しましょう。
- 退職代行はいつ検討すべき?
- ハラスメントや強い引き止めがあり、正常な手続きが困難な場合は早期に相談を。全体設計は必勝退職コンボで確認できます。
要点まとめ
- 1ヶ月前に退職を伝えること自体は原則OK(民法627条は2週間)。
- ただし就業規則/契約が周知・合意されていればそちらが優先。
- 試用/有期/繁忙期/有給消化はケース別の現実解で対応。
一次情報:民法(民法627条)